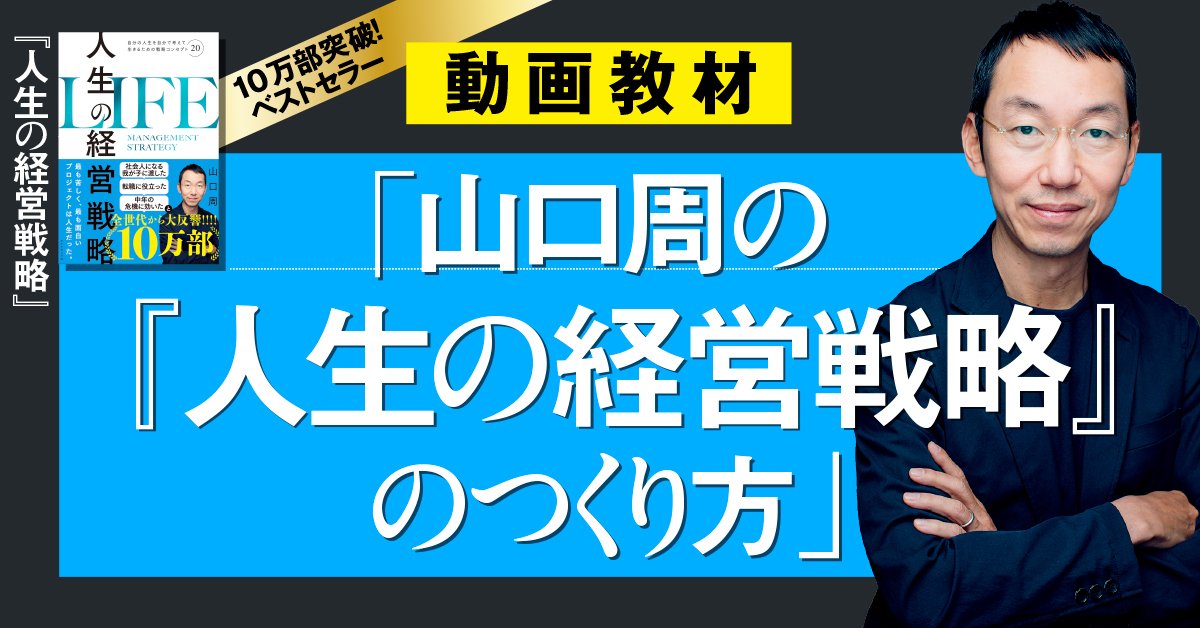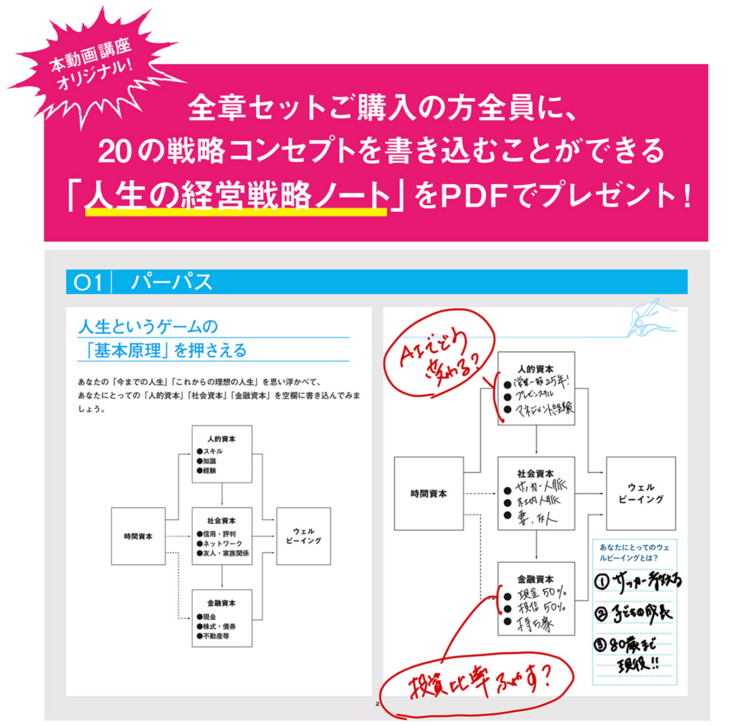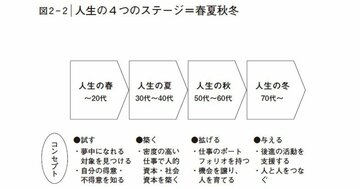「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
その仕事が「できる人」ではなくその仕事で「成長する人」に仕事を任せる
発達指向型組織とは、ハーバード大学教育学大学院のロバート・キーガン教授と、研究パートナーであるリサ・ラスコウレイヒーが提唱している組織コンセプトです。キーガンらは、高収益性と人材育成の両立を果たしている企業を研究対象とし、それらの企業が成人発達理論の原則に適合した形で組織運営されていたことから、その特徴を学術的な見地から捉えて体系化しています。
具体的には、発達指向型組織は、通常の組織と比較して、次のような特徴を持っています。
最大のポイントは、通常の組織が、最もその仕事で安定した成果が出せる人に仕事を任せるのに対して、発達指向型組織では、そのような考え方を取らないということです。なぜなら、その仕事がすでに上手にできるということは「その仕事を通じて成長する余地が少ない」ことを意味するからです。
したがって、発達指向型組織においては、仕事は、その仕事をやらせることによって最も成長できそうな人に任せる、という考え方を取ります。
当然ながら、このようなアサインメント(=仕事の割り振り)を行えば、最も上手にやれる人にアサインメントを行った時よりも、組織全体としてのパフォーマンスは一時的に低下することになります。
しかし一方で、このようなアサインメントを行うからこそ、人材の成長が促進され、組織全体の人的資本が中長期的に向上することになります。そして組織全体のパフォーマンスもまた、従前の状態よりも向上することになります。これが、発達指向型組織が、高い収益性と人材の成長を両立できている理由です。