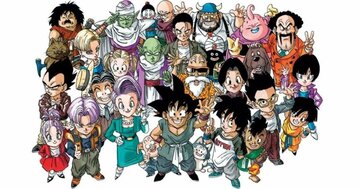Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
ほのぼのした日常が描かれているように見えるムーミン・シリーズだが、シリーズ第8作『ムーミンパパ海へいく』をよく読めば、ムーミンの家族それぞれが内省を深め自閉的な行動に出る姿が見えてくる。それに加え性的な隠喩までもが散りばめられた大人の物語だったのだ。文学研究者の横道誠氏が、発達障害者的観点からムーミンの物語を読み解く。本稿は、横道 誠『なぜスナフキンは旅をし、ミイは他人を気にせず、ムーミン一家は水辺を好むのか』(ホーム社)の一部を抜粋・編集したものです。
原作者が抱える「父権制」への
問題意識をテーマにした物語
シリーズ第8作『ムーミンパパ海へいく』(原題はPappan och havet『パパと海』)は、1965年に刊行されました。献辞は原稿の段階では「私のパパに」となっていましたが、最終的には「父親たる人へ」と落ちつきました。父ファッファン(編集部注/原作者トーベの父親、ヴィクトル・ヤンソンの呼び名)への個人的な思いを核としながらも、より一般的な問題意識へと――いかつい言い方をすれば「父権制」にまつわる問題意識へと――開かれた本だということを示そうとしたのだと思います。
『ムーミンパパ海へいく』はファッファンが亡くなってから7年後に刊行された本です。トーベ(編集部注/トーベ・ヤンソン。ムーミン・シリーズの作者である女性)はこの本を子どもの頃に家族と過ごしたフィンランドの島々を思いだしながら、また実際に島々に住みながら書いていきました。そのために『ムーミンパパ海へいく』は、たっぷりの島風と海の波音を吸収した本へと仕上がりました。
8月末、自分が不必要なものになってしまったという不安に苛まれ、家族から頼ってもらえないことを不満に感じるムーミンパパは、ムーミンママ、ムーミントロール(編集部注/ムーミン族の男の子で、アニメ版の主人公・ムーミンの原型)、養女になったミイを連れて、灯台のある島に向かいます。灯台には明かりが灯っておらず、一家は漁師と出会います。
荒れ狂う海や嵐といった自然の脅威にさらされている島で、ムーミンパパは家族からの尊敬を取りもどそうと張りきりますが、やることなすこと失敗だらけで、だんだん物思いに耽るようになります。ムーミントロールは美しい2頭のうみうま(編集部注/美しい花模様を身にまとった、馬に似たムーミン谷の生き物)と出会って思春期を迎え、ムーミン一家を追ってきたモランと頻繁に交流し、やがて家族を離れてじぶんで見つけた空き地でひとり暮らしを始めます。
ムーミンママはムーミン谷にあった世界を恋しがって、灯台の壁一面に、植物がいっぱいあるなかにじぶんが動いている絵を描きはじめ、絵のなかに入ってしまいます。自然の脅威が収まり、家族の回復が描かれます。漁師はじぶんが灯台守だということを思いだし、灯台に明かりが灯されます。
全キャラクターが原作者の分身であり
内省的かつ自閉性が高まった世界観
『ムーミン谷の冬』に始まり、『ムーミン谷の仲間たち』で加速した内省化の方向は、『ムーミンパパ海へいく』でさらに高まります。小学生時代の私は、本作の内容をほとんど理解できないままでした。