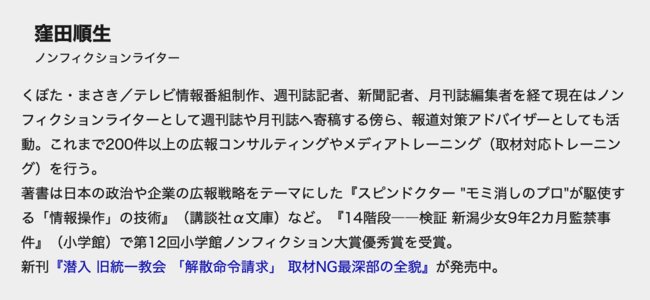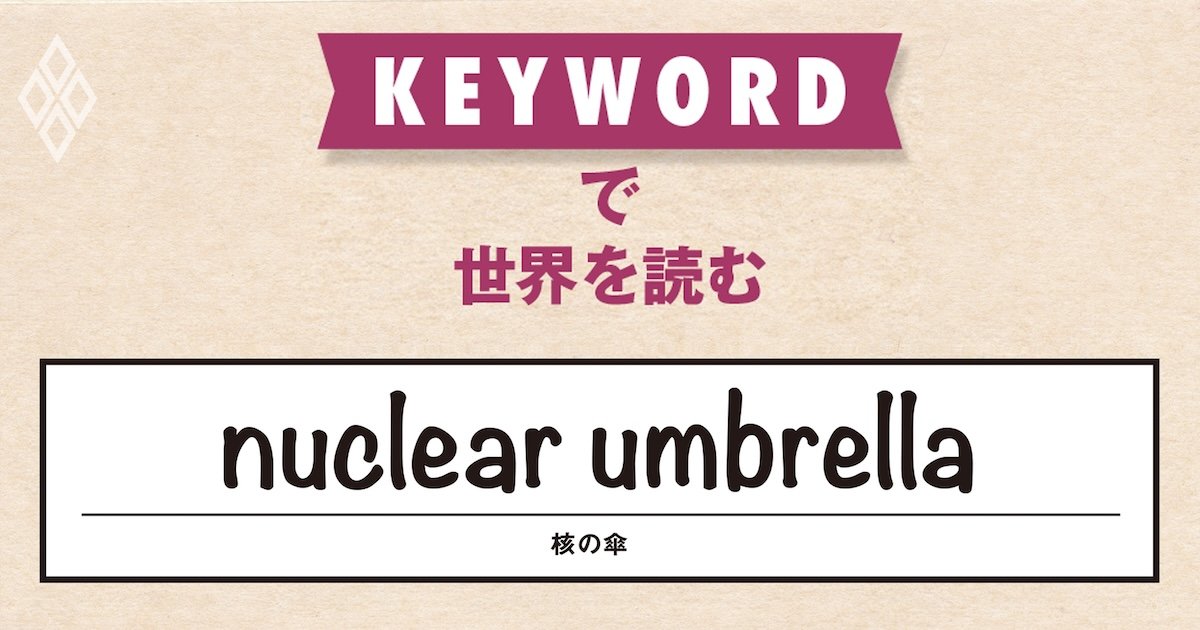「外国のテレビは制作も編成も報道もすべて、2年や3年の契約で雇う。プロデューサーもよそからヘッドハンティングして、よければ続くし悪ければなくなる、スタッフ丸ごと総取っ替えも日常的。番組を作る人と経営陣は切り離していますし、個人のプロ意識や責任感は彼らの生活に直結しています。一方で日本はみんな社員でしょ。テレビ局の社員が全部決める。もちろんいい部分もありますけど、上司と部下の関係や芸能事務所との仲に優先順位が置かれています」(ここが変だよ日本のテレビ デーブ・スペクターふるう愛のムチ Yahoo!ニュースオリジナル 21年9月3日)
これは他のマスコミにも当てはまる。終身雇用とゼネラリストを求める風潮から、新聞記者もある程度出世した人は、経営企画などを経て、経営に携わるようになる。海外ではジャーナリストは死ぬまでジャーナリストというのが普通なので、メディア企業の経営は「プロ」を招くことが多いが、日本はジャーナリストに経営者をやらせるのだ。
こういう日本独自のキャリアパスは「現場の声を経営に生かす」と好意的に語られてきた。しかし、今回のフジテレビ問題のように、「元制作マン社長」「元ドラマプロデューサー取締役」が昭和のテレビ制作現場の悪しきセクハラ・性暴力カルチャーを引きずった危機管理対応をしているのを目の当たりにすると、「もはや時代錯誤ではないか」という気もする。
テレビマンは番組制作に集中し、経営陣は芸能界のおかしな慣習や現場の古い体質などに惑わされず、会社と社員のためにしっかりと目を光らせる。そろそろ昭和を引きずる日本のマスコミも「経営と現場の完全分離」が必要なのではないか。
(ノンフィクションライター 窪田順生)