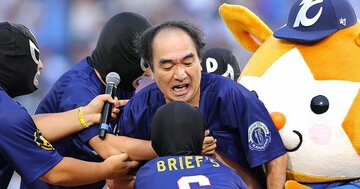たしかに、公開直後のド深夜は再生回数が伸びにくいですが、朝起きてから観る人もいるし、朝・夕の通勤時間帯に観る人もいれば、お昼休みに観る人もいる。この長時間はライバルが少ない状況なのではないでしょうか。
そもそも、「定説」や「マーケティング」は、前例を踏まえて導き出されるもの。でも、何か新しいことに挑戦する場合、前例を踏まえた「マーケティング」理論だと、それはもう遅いのではないでしょうか。もはやそれはチャレンジでもなんでもない。
動画公開の時間帯だけでなく、「テレビ的な編集は嫌われる」と言われていた中、そんなことは無視して、自分のストロングポイントであるテレビ的な編集で勝負してみました。
また、定説により「ユーチューブは毎日投稿したほうがいい」が当たり前でしたが、テレビクオリティの編集をしようとすれば、毎日投稿は無理。なので、チャンネル開設当初は週3回の投稿、それでもカツカツで余裕がなかったので、すぐに週2回の投稿に変更しました。
最近のユーチューブは全体的に、週1回や週2回アップのチャンネルが増えてきたと感じます。その点はひょっとしたら「エガちゃんねる」の影響も少しはあるのかもしれません。
「壁」にぶち当たりまくり
ユーチューブで花開いた日
カンファレンスのような場に出席した際に、ユーチューブのイロハよりも大事なこととして、考え方を伝えることがあります。
先日は参加者から「やりたいことがあるけどいろんな壁があってどうすれば……」というような相談をされました。その時に僕が話したのが、「一見『壁』に見えるもの、それは次のステージへの『ドア』かもしれない」という考えです。
「エガちゃんねる」は、誕生までにさまざまな「壁」にぶち当たりました。
そもそも、江頭さんと何か面白いことをしたい、と企画書を作っても、コンプライアンス至上主義の今の時代、キー局・地方局にかかわらず、地上波テレビはもちろんダメ。盛況な映像プラットフォームに企画書を持っていっても苦い顔。携帯電話のキャリアなどが展開する媒体でもけんもほろろ。
仮に現場担当者が面白がってくれても、決裁権のある上の人たちから止められる。どこに行っても壁ばかりの行き止まり状態で、最後の最後にたどり着いた場がユーチューブでした。