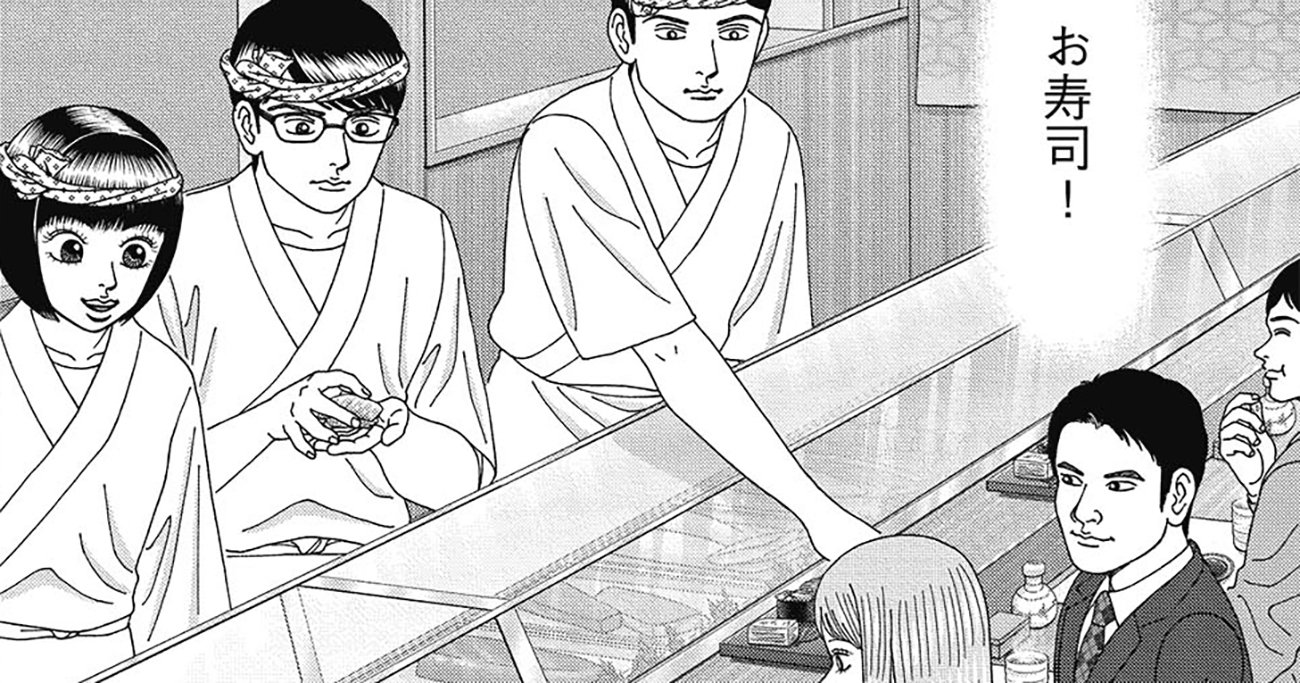 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第45回は、試験問題における「隠れたキーワード」の重要性を説く。
「隠れキーワード」を見極めろ!
読解力を育てるために、『走れメロス』の要約を課題とした国語科講師の太宰府治。ところが、生徒たちの要約は不正解の連続だった。そこで太宰府は、要約のコツは「キーワードを並べたり繋げたりして文章を作ること」と述べ、寿司を彩りよく並べることにたとえる。
東京大学では、あらかじめ指定されたキーワードを解答に含めるよう求める入試問題がよく出題される。本編で例に挙げられている通り、世界史の論述問題はその代表例である。しかし、提示された語句をただ並べて繋ぐだけでは、十分な答案にはならない。
いわゆる「指定語句」は、単にそれを組み合わせただけでは不十分な解答になるように設計されていることが多い。もし指定語句だけで模範解答に達してしまうのであれば、すべての受験生の答案が似通ってしまい、採点に差がつかないからである。
指定語句は、模範解答の中核というよりも、むしろ考察を深めるための「手がかり」や「通過点」として機能していることが多い。だからこそ、提示されていないが論述に不可欠な「隠れたキーワード」を見つけ出す力が問われる。
例えば、「イギリスとフランスの政治を比較せよ」という問題で、「大統領制」と「ブレグジット」という語句が指定されていたとする。
「比較」という設問であれば、同じ基準・観点で両者を論じる必要がある。フランスが「大統領制」であるという事実だけを述べても、それは一方的な記述に過ぎず、比較にならない。したがって、イギリスの「立憲君主制」についても必然的に触れることになる。この「立憲君主制」こそが、設問に対する「隠れたキーワード」である。
一方、「ブレグジット」についてはどうか。イギリスがEUを離脱したという事実に対し、フランスにはそれに相当する政治的事象が存在しない。だとすれば、比較対象としては「フランスはEU加盟国としての立場を維持している」といった形で記述するのが妥当である。このように、隠れたキーワードは必ずしも単語とは限らず、状況や文脈を補う一文や概念の場合もあるのだ。
「書かれなかったこと」が重要なワケ
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
現実の文章では、「これがキーワードです」と親切に教えてくれることはほとんどない。かえって興ざめだ。ましてや「隠れたキーワード」などというものは、意識しなければ気づくことすらない。しかし、私はこれが重要な視点だと考えている。この考え方は、文章を書くときだけでなく、読むときにも役立つ。
例えば、大学合格者の「数」ばかりを強調する文章があったとする。しかし、実は「合格者数」そのものよりも「受験者に対する合格者の割合」の方が、真の意味を持つかもしれない。この「割合」が、見落とされがちながらも重要な「隠れたキーワード」となりうる。
また、「○○は××である」と事実のみを述べる文章においては、「それが良いことなのか、悪いことなのか」という価値判断の部分が、文脈全体を通じて伝えたい主張であることも多い。ここでも、明示されていない要素が読解のカギを握る。
文章には常に、書き手の意図や選択が反映されている。すなわち、書かれていること以上に、書かれなかったこと、あえて省略されたことに注目する姿勢が重要となる。
情報を俯瞰(ふかん)し、本来存在すべき要素を推測し補完すること。これこそが、読解における「隠れたキーワード」を見つけ出すという行為なのだ。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







