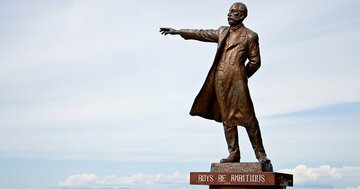単に「いい人だなぁ」では、人望には結びつかず。また、職位・職階と人望は比例しないことも自明の理。敬愛される人間的魅力で引き付けてこそ、部下は上司の意向に従う。同様に、学生は教員の指導に従う。その典型的な例は、人を動かすときに表れるのでは。
軽率の謗りを免れないことを承知であえて言うならば、上司が命令で部下を動かすことは最終手段ではないでしょうか。
「やれ」という命令的口調ではなく、「やってもらえますか」という依頼型口調、あるいは「やってみてはどうだろうか」という提案型口調の方が、人望に裏打ちされた効果が発現すると思います。と考えることは、いささか甘い考えでしょうかね。
さらにもう1つ、人望が見て取れる場面としては、正直さや潔さがあることです。
部下の手柄を横取りしたり、部下に責任を転嫁したりする上司は、悪評と軽蔑あるのみ。自分に誤りがあるならば、素直に非を認めて謝罪することが正道。そして、失敗が部下に起因するか否かに関係なく、部下の心理的安全性を担保する上でも、上司としての責任を認めることが大切ではありませんか。
高度先端技術を活用した社会変革の構想「Society5.0」が叫ばれる昨今は、逆に人間としての力量が問われる時代であると言っても過言ではありません。
私の未熟さを棚に上げて言うならば、アナログの力ともいえる人望を身に付けることは、人間社会を生きる技の1つを持つことになるかもしれませんね。
好感度の高いリーダーは
信頼感から生まれるもの
拙著『リーダーが優秀なら、組織も悪くない』の読者の方から、「コロナ禍の息苦しい時代にあって、好感度の高いリーダーは、どのようなリーダーでしょうか」との質問をいただいたことがありました。難問ですが、あくまでも私の独断と偏見に基づいて、お答えしました。
まず不可欠なのは、何よりも信頼感。そう思うのです。
好感は、原理原則にのっとって行動する人への信頼から生まれるのではないでしょうか。リーダーの行動原理を構成メンバーが理解して共有する。そしてその組織の行動規範になることが、究極的には理想型といえるでしょう。とはいえ、最近の若手社員に暗黙知で伝えることは、ほぼ不可能と思われますから、リーダーには発信力が必要になります。