宇宙飛行士を冬眠させれば
宇宙開発は大きく飛躍する
また、宇宙開発分野への期待も大きい。宇宙開発にとって人工冬眠は大きなテーマであり、NASA(アメリカ航空宇宙局)やESA(欧州宇宙機関)もその研究に力を入れている。
宇宙船は燃料をたくさん積むことができれば、そのぶん、遠くまで行くことができる。そのため、燃料以外の積載量をいかに減らすかが課題となる。必要な食料や酸素、あるいは健康状態を維持するための運動スペースを減らす、その1つの手段として、人工冬眠に期待がよせられている。
もし、宇宙飛行士の体温を30℃まで下げることができれば、宇宙船に搭載する食糧などの必要物資(payload)を半分に減らすことができる。
人類は火星到達を目指しているが、地球から火星までもっとも接近したときでその距離は約5600万キロメートル。技術開発が進められているが、現在の技術では火星と地球を往復するには2年かかるといわれている。火星を目指すには人工冬眠の技術は必須なのだ。
仮に、宇宙船に乗って冬眠状態で火星にたどり着いたとして、目覚めたときに体は動くのか?という疑問があるかもしれない。
無重力環境では体を支える必要がなくなるため、筋肉や骨が衰える。いわば、寝たきりになって生じる「廃用症候群」と同じような状態になってしまう。それを防ぐために、宇宙飛行士は宇宙船の中でもトレーニングを欠かせない。
では、冬眠しながら宇宙に行くと、やはり、筋肉が落ちて足腰が萎えてしまうのかといえば、そういうことにはならない。
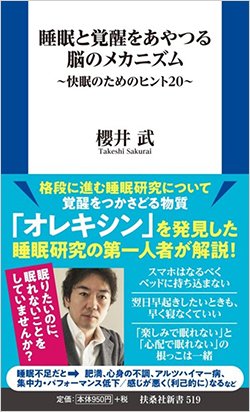 『睡眠と覚醒をあやつる脳のメカニズム~快眠のためのヒント20~』(扶桑社)
『睡眠と覚醒をあやつる脳のメカニズム~快眠のためのヒント20~』(扶桑社)櫻井武 著
春になって冬眠から目覚めたリスのことを想像してみてほしい。冬の間、まったく運動をしていないが、なんら問題なく普通に野原を駆け、木に登り活動しているではないか。冬眠をしても、筋肉量や骨量が減ることはない。
というのも、冬眠はすべての生理機能のスピードを遅くするから。じつは筋萎縮や骨量の低下も生理的な代謝過程なのだ。おそらく冬眠状態であれば、重力がほとんどない微小重力環境でも廃用性筋萎縮などは阻止できるはずだ。
また、冬眠状態になって意識レベルを下げたほうが、地球から遠く離れた火星へと旅する孤独、危険と隣り合わせの日々や課せられたミッションへのプレッシャーなどから生じる強烈なストレスに耐えることができるだろう。







