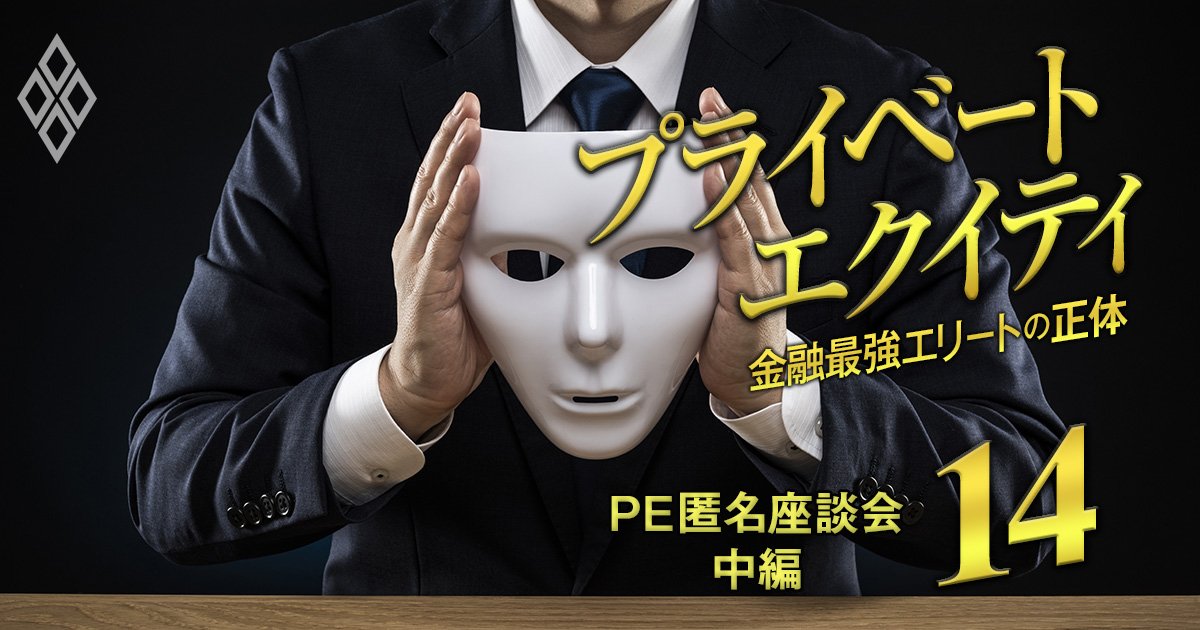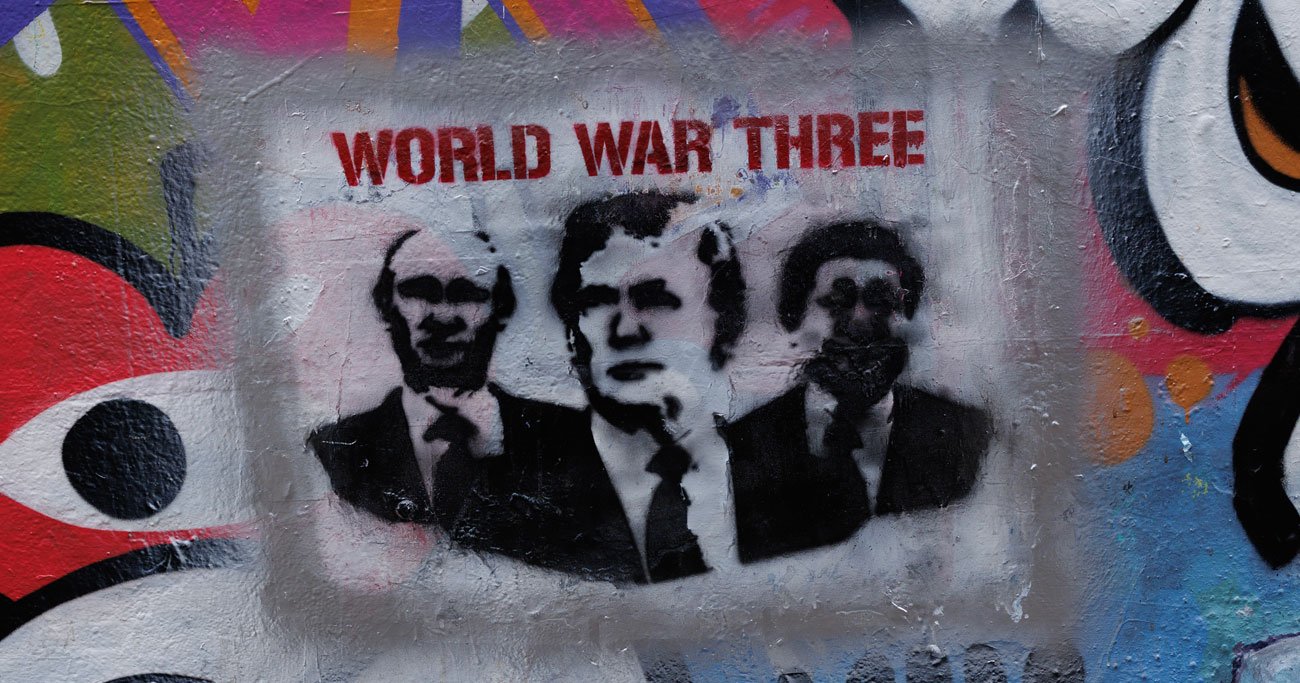確かに、転職希望者と接していて、35歳を境に「自分を変えることができない人間」が増えると感じます。その結果、転職に失敗する人が増えている問題を私は「シン・35歳転職限界説」と呼んでいます。
入社後に失敗する転職者に共通する
「残念すぎる思考グセ」
この「シン・35歳転職限界説」は経営者同士でよく議論になるテーマです。
35歳といえば新卒入社から12年ほど経過し、ある程度成功も失敗も経験し、世の中の渡り方も理解して自分なりのやり方が確立される時期です。学歴と実績に対する評価が逆転し、周囲からはプロフェッショナルとして認識され、給与も高くなります。
その半面、自分なりのやり方が確立される弊害として、アンラーニングをしながら外部環境へ柔軟に変化する姿勢が薄れていくことがあるのです。それは些細な局面で姿を現します。
たとえば、転職先の職場で上司への報告の頻度を上げることを求められたとします。さらに、前職は自由放任主義で上司への報告の頻度は低く、それでうまく回っていたとします。すると、「前は報告しないでうまくいっていたのだから、そんなに報告する必要はないだろう」と報告を怠ってしまう。
20代の若手なら「このタイミングで確実に報告を入れてください」と指示すれば、「分かりました」といって素直に応じる人が多いと思いますが、35歳前後から素直に受け入れない人が目立ってきます。
「自分はこのやり方でうまくやってきたのだから、なんの問題があるのか?」と考えているわけですが、それは新しい組織のルールに従わないことを意味します。
些細なことに見えるかもしれませんが、言い方を変えると、これはカルチャーフィットの問題です。つまり、35歳あたりから「カルチャーフィットしない転職者」が目立ってくるようになるのです。
入社面接では「ぜひ御社の発展に貢献したい」と言っておきながら、いざ入社してみるとその会社のローカルルールや仕事の進め方を軽んじてしまう。これでは、チームに自分勝手な人間であるという印象を残してしまうばかりか、「コイツは当てにできない」という空気を漂わせてしまいます。1人だけ組織への貢献意識が弱くて、チームの中で浮いているような状況になってしまうのです。
これでは転職した本人も会社も不幸になってしまいます。