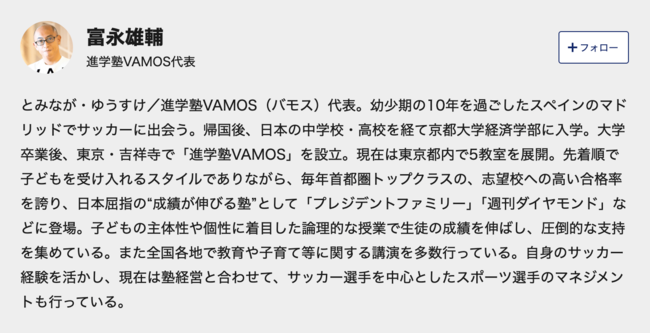塾ごとに
「生徒の特徴」はあるのか?
富永:○○の塾に通っている子はこういう特徴があるというようなことはあるのでしょうか。
渋田:実はあまり見えないんです。SAPIXは漢字と計算が盤石という印象はありますが。例えばグノーブルは選択肢がなくて記述が中心なので、そこが弱いと思うこともありますが、偏差値の高い低いも塾によって基準が違うので比較が難しいです。
富永:保護者の塾への向き合い方で、こうするとよいということは。
渋田:やはり、大切なのは、子どもを預けている以上はその塾を信頼することだと思います。塾に行きながら、オンライン家庭教師にも依頼したりして失敗するのは、結局現在の塾を信頼していないから。いろいろ手を出すのですが、結局、あら捜しをするだけで、不満が募る一方です。
富永:まずは今行っているところを信頼して任せてみないと、どこへ行っても不満を持つことになる。
渋田:模試の成績が悪くても、最後はなんとかなるだろうと信頼してくれる保護者の子どもの方が伸びます。塾は完璧ではないですし、学校も完璧ではありません。ある程度信頼して、本当に合わないと思ったならやめるという判断をすればいいんです。保護者には子にその塾を辞めさせる権利があるわけですから。
信頼してくれれば、塾側もそれを意気に感じて、信頼を裏切らないように一生懸命やります。悪いようにするはずがない。
富永:たとえば、通常はこの順番で教えるけれど、そのクラスの雰囲気を見て、ちょっと順番を変えて教えるとか、教材の課題を現場の判断で全部やらないといったことも当然あるわけです。
ところが、熱心な保護者の中には「なぜこの順番でやらないんだ」とか「なぜこの問題を全部やらないのか」と責める人もいますよね。我々も人間なので、気持ちよく仕事をさせてもらえると、それだけ頑張れます。
渋田:たとえば、病院に行ったとして、医師の見立てや処方に対して、「それはちょっと違うんじゃないか」などと言ったりはしないでしょう。どうしてもおかしいと思ったら、病院を変えるだけですよね。
それと同様、専門家に任せるという姿勢が大切です。教育に対してはなぜか、保護者は「評論家」になってしまうことがある。保護者は焦らず長い目で見守り、塾には信頼して任せる。その中で子どもが自分のペースで成長していけば、必ず結果はついてくると思います。
富永:今日はなにより僕自身が本当に勉強になりました。ありがとうございました。
渋田:こちらこそ、富永先生の見解をじかにうかがえて励みになりました。また、先生のファシリテートの上手さから、喋りすぎて辛口になっている内容もあるかと思いますが、毒にも薬にもならない内容よりは良いのではとご容赦いただければと思います。本日は、楽しい時間をありがとうございました。