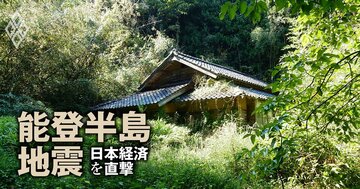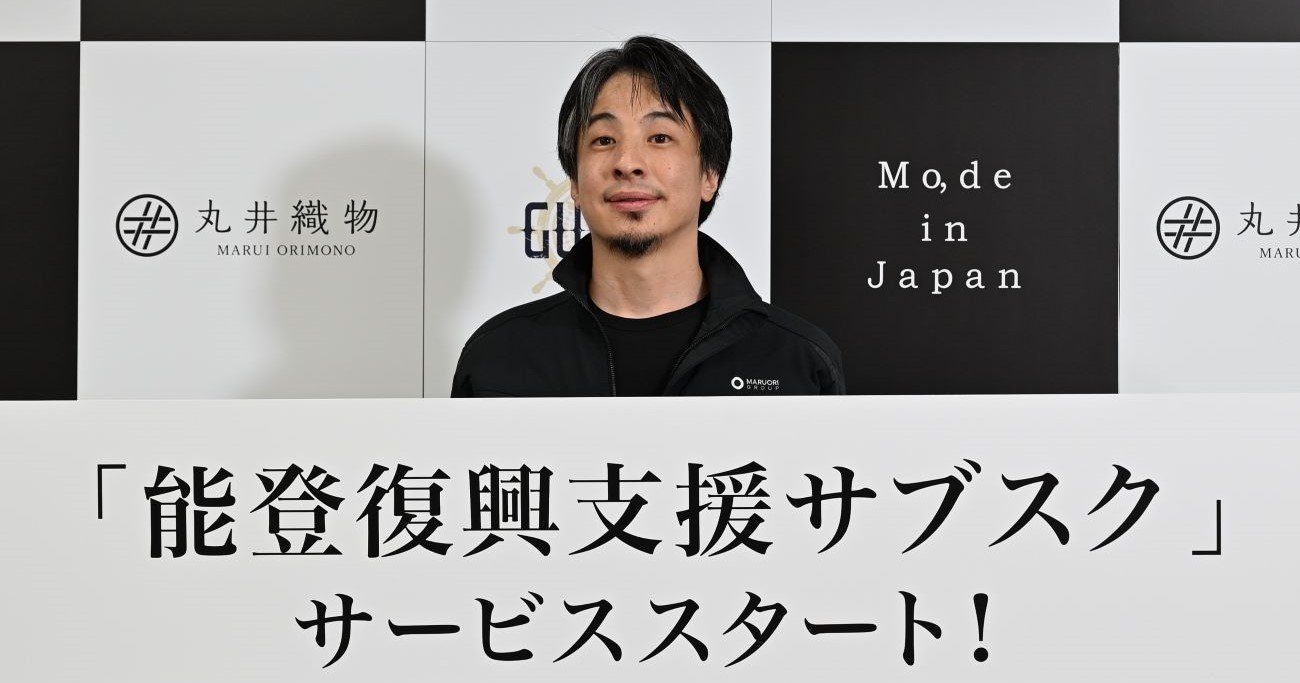 「能登復興支援サブスク」サービス発表会
「能登復興支援サブスク」サービス発表会
2024年1月に発生した能登半島地震。インフラは復旧しつつあるが、地域経済の再生は進まず、仕事を失った若者たちが町を離れ、人口は確実に減っている。「このままでは地方が“戻れない場所”になる」――そんな危機感を持ったひろゆき氏が、「能登復興支援サブスク」を立ち上げた。寄付やチャリティではなく、“買うこと”で支える。「ビジネスとして成立する復興」こそが持続可能だという冷静な視点と、地方への熱いエールについて話を聞いた。(ライター 池田鉄平)
行政にはできない「選択と集中」
だからこそ民間が、ひろゆきが動く
「能登復興支援サブスク」を始めようと思った背景を尋ねると、ひろゆき氏はこう話し始めた。
「構想は、2024年の夏頃からすでに考えていました。地元では、インフラが戻っても、ビジネスが戻らなければ生活が成り立たない。特に若い人たちは、仕事がなければ地域を離れてしまう。実際、仮設住宅が撤去された後も産業の回復は遅れ、結果として人口はすでに1割も減っているんです」
復興における問題は、「誰が」地元のビジネスを立て直すのかということ。行政は公平性の観点から特定の企業だけを支援することが難しいが、民間ならそれができるという。
「例えば、『この商品を事前に○個買い取ります』と、明確な需要を示せば、作り手はリスクを恐れずに再建に取り組めます」
サブスクの利用料は1カ月5500円(送料込み)で、6カ月分を支払い、毎月5日に「被災地の美味しいもの」が届く仕組み。商品が売れれば人手が必要になり、仕事が生まれ、お金が地域を循環する。その循環こそが、本当の意味での復興だとひろゆき氏は考えている。
『ファイナルファンタジー14』の
復活劇から学べる事
今回の震災に際して、ひろゆき氏が強く感じているのは、「復興しなくても仕方がないよね」という、諦めにも似た空気が社会に広がりつつあることだ。