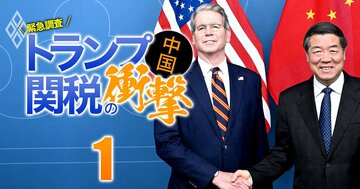Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
トランプ関税後の課題は構造的な成長力低下
輸出シェア低下、消費はコロナ禍前の水準
トランプ政権の関税政策を巡る日米交渉は相互関税15%、自動車関税12.5%(既存税率含めて15%)で合意に至ったが、日米間で合意内容の説明・解釈の食い違いや実施時期などで不透明感が残っている。
現時点では、合意を受けて日本経済が景気後退入りするリスクはいったん後退したとみるが、関税による景気下押しの影響は避けられず、当面の日本経済は停滞局面(踊り場)が続く公算が大きい。
トランプ関税は自動車など製造業を中心とした企業収益に打撃を与え、来年の賃上げにも波及する。足元では、7月の雇用統計が大幅に下方修正された米国経済の減速も懸念され、引き続き影響を注視する必要がある。
しかし、より目を向ける必要があるのは、トランプ関税の裏側で忘れがちになっている日本経済の構造的な「実力」の低迷だ。
例えば、中国の競争力向上に伴う輸出シェアの拡大などを受けて、日本の主要な輸出はトランプ政権が関税を引き上げる前からシェアの低下が目立っている。
加えて、実質賃金の低迷に伴う個人消費の伸び悩みが続いており、近年は高水準の賃上げが実現する中でも足元の個人消費は依然としてコロナ禍前(2019年平均)と同じ水準にとどまっている。
他国・地域も関税を引き上げられることで他国・地域対比で見た相対価格という点で日本の輸出競争力がそがれることは回避されるとしても、日本経済・日本企業のそもそもの「実力」が伸び悩んでいる状況では、「トランプ後」を見据えた中期的な成長力を楽観することはできない。
政府が掲げる「実質1%成長」の壁はなお高いと考えられ、輸出競争力の再構築と、消費回復を支える実質所得を増やすための戦略が鍵になる。