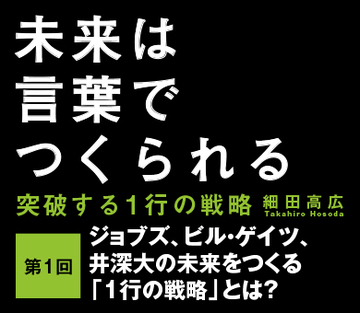すべての書籍を、60秒以内に手に入るようにする。
(Every book ever printed in every language, All available within 60 seconds.)
「キンドル」アマゾン
電子書籍市場を牽引している、アマゾンの「キンドル(Kindle)」。地球最大の書店であるアマゾンが、自らのビジネス基盤とも言える紙の本の「宿敵」をつくったのは、スティーブ・ジョブズの影響だと言われています。ジョブズがiTunesで音楽を物理的な制約から解放したように、アマゾンは本というコンテンツを紙の制約から解放しようとしたのです。
iTunesミュージックストアのオープン翌年、2004年にアマゾンは携帯情報端末パームの開発者であり、アップルで働いた経験を持つグレッグ・ゼールを引き抜いて、電子書籍の開発を始めます。「本のiPod」をつくるというのが当初の目的でした。
そもそも、今のカタチにつながる電子書籍の元祖は、アラン・ケイに遡ります。1977年の時点でダイナブックは、デジタル化したゲームや書籍をダウンロードして持ち歩くことまでが想定されていました。
製品として電子書籍が市場に登場するのは、1990年頃のことです。90年にはソニーからCD‐ROMを使ったデータディスクマンが登場。93年にはデジタルブック社がフロッピーディスクに書籍データを入れて販売しました。
インターネットが本格化してからは、2004年にグーグルが著作権の切れた書籍の電子化を始め、2006年にはソニーがソニー・リーダーで電子書籍に参入。しかし、まだまだ「人は物理的な本を好み、手が届くところに置いておくことを好む」という見方をする人が多く、電子書籍は一般的な製品とは言いがたい状況でした。
アマゾンがキンドルを発表したのは、2007年のことです。当初は否定的な見方をする人も数多くいましたが、バージョンを追うごとに出荷台数は伸び、2011年にはアマゾンの紙の書籍を電子書籍の売上が追い越すようになりました。
出版をめぐる状況は大きく変わり始め、業界は電子書籍に対する何らかの対応をとらざるをえなくなりました。発売からわずか数年で、キンドルは電子書籍を取り巻く環境そのものを変えてしまったのです。一体何が、それまでの電子書籍と違ったのでしょうか。
アマゾンの創業者ジェフ・ベゾスは、キンドルについて「これはデバイスではない。サービスだ」と話し、アマゾンがキンドルを通じて目指す未来は「すべての書籍を、60秒以内に手に入るようにする」ことだと明言しています。
それまでの電子書籍の争点といえば、いかに「紙の読みやすさに近づけるか」や「紙の体験を超えるか」といったデバイスの中の話でした。だからこそユーザーも批評家も、紙との比較でしか電子書籍の未来を想像できなかったのです。
一方、ベゾスは、電子書籍の外側にある未来を想像していました。世界中の、あらゆる言語の書籍が一分と数えないうちに手のひらにやってくる。キンドルは、そんな未来を実現するツールのひとつとして捉えられました。
だからこそ、アマゾンは他の電子書籍で手薄だった書籍のラインナップを充実させ、発売当初から9万冊もの本が手に入るようにしたのです。通信会社との契約を不要にし、パソコンに接続しないで使える設定にしたのも、どこにいても一分以内に本を手に入れられるように、との考えから決められたものです。
アマゾンは、電子書籍に「読むための次世代デバイス」という役割に加えて「本を手に入れる次世代サービス」という針路を与えました。つまりキンドルとは「電子書籍」というよりも「電子書店」だったのです。
2011年、高精細度カラーディスプレイを搭載した「キンドルファイア(KindleFire)」の投入によって、今ではiPadに対抗するタブレット端末とも捉えられるようになってきています。
かつては「電子書籍が必要なのか?」といった切り口で議論されていたものが、今では「紙の本は必要なのか?」という議論に移行していることに驚きます。やはり紙にも利点が多くあり、紙の本が絶滅することは想像できませんが、あらゆる書籍が一分以内に手に入る未来に反対する人は少ないのではないでしょうか。