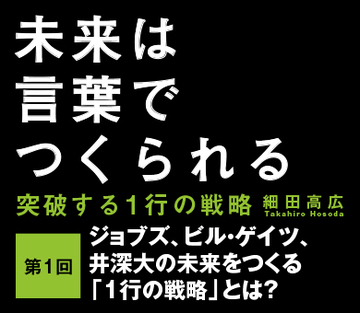世界を変える商品には、技術革新の前に必ず発想革新がある。大ヒット商品が生まれる前に、新しい目的地を表現する「言葉の戦略」が先に存在するのだ。今求められる、イノベーションを生み出す「1行の戦略」とは何か?
ポケットに入るラジオをつくれ。
「トランジスタ・ラジオ」井深大・盛田昭夫
その一言は、ソニーを世界に知らしめ、日本製のイメージを安価な模倣品から独創的で最先端なものへと変えました。20世紀の日本で、最もビジネスにインパクトを与えた言葉と言っても大げさではないかもしれません。
1952年、ソニーの創業者である井深大氏はテープレコーダーを売るために訪れた米国で、あるニュースを耳にします。それはアメリカのベル研究所がトランジスタの特許を他社に使わせることを検討している、というものでした。
トランジスタの応用は難しいとされていましたし、特許のライセンス料だけで当時のソニーの年間の売上が吹き飛ぶほどの大金を支払わなければいけません。トランジスタの利用は、ベンチャー企業には大きすぎるリスクでした。
しかし、井深氏はトランジスタこそ120人いるソニーの技術者を熱中させ、才能を引き出す格好の素材だと考えます。何より井深氏と盛田氏のふたりの頭にはトランジスタの利用法、つまり常識を覆すラジオの姿が徐々に具体的なカタチになり始めていました。
それまでのラジオに主に使われていたのは、真空管。真空管が大きいせいで、当時のラジオは大きくならざるをえず、一家に一台の家具として扱われていたのです。実際、ラジオ工場には専任の家具職人が雇われていました。
井深氏が「トランジスタ・ラジオを使えば超小型のラジオがつくれるかもしれない」と話すと、盛田氏は「日本は小さくまとまるものが好きだ。掛け軸は丸く収まるし、屏風も畳んでしまうことができる」と返します。こうしてふたりは「ポケットに入るラジオ」という着想に至るのです。
ラジオが家具だった時代ですから、「ポケットに入るラジオをつくれ」と言われた社員や下請け会社の技術者は驚き、一度は「無理だ」と話を突っぱねました。しかし、ふたりは絶対に引き下がりません。実際に開発してみると、確かにトランジスタの扱いは難しく、井深氏が「何度も中止しようと思った」と漏らすほどでした。
1955年、どうにか商品化にこぎつけたのが、TR‐55というトランジスタラジオです。日本で初めてのトランジスタ・ラジオでしたが、まだまだポケットには入りませんでした。ソニーはさらに改良を加え、1957年、ついにポケットに収まるラジオTR‐63を完成させます。これを境にラジオは家族のものから、個人のものへと変わっていきました。
ソニーはただ小さいラジオをつくったのではなく、「ひとりで聴く」という新しいラジオの聴き方までつくってしまったのです。このラジオは、世界で50万台以上も売れて、ソニーが躍進するきっかけとなりました。
「ポケットに入るラジオ」という言葉はそのまま広告のキャッチコピーとしても使われ、海外ではポケッタブル・ラジオ(pocketable radio)という言い回しが採用されました。
ちなみに、この「ポケッタブル」という単語は、当時の英語には存在しませんでした。完全なる和製英語だったのです。それでも今では、複数の英語辞書に正式に記載され、「ポケッタブル・ラジオ」が代表的な使用例として紹介されています。ポケットに音楽を入れて持ち歩く。このとき生まれた「ポケッタブル」の思想は後のウォークマンにつながり、そしてアップルのiPodに受け継がれていくことになります。
井深氏と盛田氏は、新しい商品を考えるとき、必ず情景の浮かぶ言葉を使いました。たとえば、カラーテレビの開発時もそうです。かつて暗いシャドーマスク方式のカラーテレビが一般的だった時代。テレビの輝度が低く、カーテンを閉めてテレビの前にかじりつかないと、映像はキレイに見えませんでした。
そんなときに井深氏は「人々が夕飯を食べながら見られる、明るいカラーテレビをつくろうじゃないか」と技術者に伝えたのです。カラーテレビを担う技術者たちの間で、目指すべき商品像が一瞬で共有されたと言います。
他にもテレビの画像をくっきりさせることに関しては、「キリリティ」を上げろと指示していました。解像度や鮮明度という言葉では伝わりきらないソニー独自の色彩感覚が、こうした言葉からつくられていったのです。井深氏も盛田氏も、頭の中にあるイメージを、そのまま伝えようとあの手この手で言葉にしてきました。ソニー製品の発明の歴史は、言葉の発明の歴史でもあったのです。