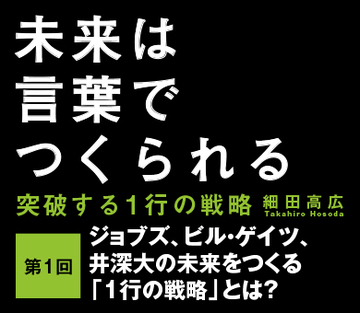個性的な組織は、個性的な言葉を持っている。時代を切り拓いたソニー、ディズニー、アップルという組織にも、過酷な職場を愉快な職場へ、儲け主義を人格主義へ、タテ社会をフラットな組織へ変えるビジョナリーワードがあった。それぞれの創業者の「1行の戦略」から、組織の発明について学ぶ。
自由闊達にして愉快なる理想工場
井深大(ソニー創業者)
イノベーションを生み出す組織として、21世紀の前半に最も注目された組織のひとつに、アメリカのグーグルが挙げられます。
その特徴は、上下関係に縛られない「フラットさ」と、優秀なエンジニアたちが思う存分に創造性を発揮できる「自由さ」にあると言えるでしょう。
フラットな組織という点では、グーグルのCEOを務めたエリック・シュミットの「命令が欲しいなら、海兵隊にでも行けばいい」という言葉が物語っています。肩書きにしばられず、誰に対しても言いたいことを言える風土をグーグルは大切にしているのです。
また、自由さに関しては自分の仕事時間の20%を好きな研究に使えるという20%ルールを持ち、そこからいくつかの革新的なサービスが生み出されていたことを、ご存知の方も多いかと思います。
その半世紀ほど前の日本にも、自由で風通しのいい、技術者中心のイノベーティブな組織を思い描いていた人物がいました。ソニーの創業者である井深大氏です。
戦時中、日本測定器で技術者をしていた井深氏は、レーダーや無線操縦のための技術を開発して国に納品していました。やがて終戦を迎えると、それまで培った技術を民間の商品に転用することを考えます。
終戦後の1946年に、気の合う仲間たちと立ち上げたのが、東京通信工業でした。当時の工場の様子について井深氏は「ひどいあばら屋のバラックで、床はがたがた、屋根は板ぶきでそれもスキ間だらけ、雨が降り出すとへやの中でかさをさすやら、機械に板をかけるやらの始末だった」と、日本経済新聞の連載「私の履歴書」の中で回顧しています。
大した設備も、近代的なビルも、もちろんカフェテリアもありません。入り口にはいつも隣家のオムツが干してあって、工場の中のトイレはすぐに汚れてしまう。資金繰りに明け暮れ、頭を下げて借金をする毎日。だけどその場所でみんなが集まって仕事ができることを、井深氏は「嬉しくてしょうがなかった」と述べています。
その頃、井深氏がまとめた設立の趣意書に書かれているのが「自由闊達にして愉快なる理想工場」という言葉でした。戦後間もなく多くの人がまだうつむいていた時代です。工場と言えば過酷な職場で、人が手足のように扱われることも少なくありませんでした。
そんな暗い工場を、理想の工場へ。労働をつらいものから、愉快なものへ。国や軍の仕様書に合わせてつくるのではなく、自分たちのつくりたいものをつくろう。技術者として縁の下で誰かを支えるだけではなく、檜舞台へと自ら躍り出よう。そうやって井深氏は頭の中に、技術者の理想郷を思い描いていたのでした。
経営方針には、儲け主義を廃すること、いたずらに規模を追わないこと、従業員は実力本位、人格主義の上に置き、個人の能力を最大限に発揮することなどが記されました。自由でフラットな組織を思い描いていたことがわかります。実際に「ソニーではみんなが同じ仲間なのだから『さん』付けで呼べ」というのが、井深氏と盛田氏の方針で、ふたりとも井深さん、盛田さんと呼ばれていました。
また社内だけでなく、下請けの工場に対しても、上下関係を持つのではなく「独立自主的経営」に導いていくことが方針のひとつとして記されていました。ソニー製品に関わるすべての人がフラットに自由に働ける未来を目指していたのです。
「会社」ではなく「工場」という言葉を選んだのも重要なポイントでした。手を動かして試行錯誤を繰り返す場所が、あるときまでのソニーにはオフィスの中に存在したそうです。ソニーの本質は、会社というよりも、「理想工場」なのでしょう。
そんな自由で風通しのいい「工場」から日本初のテープレコーダー、世界初のトランジスタ・ラジオ、そしてウォークマンが飛び出しました。そして、ソニーの躍進がメイド・イン・ジャパンを見る世界の目さえ変えていったことはみなさんもご存知の通りでしょう。
設立趣意書に書かれた多くは現実となりました。ただひとつ、「経営規模としては、むしろ小なるを望み」の一文だけは叶わず、大成功の宿命として大企業への道を進んでいくことになるのです。