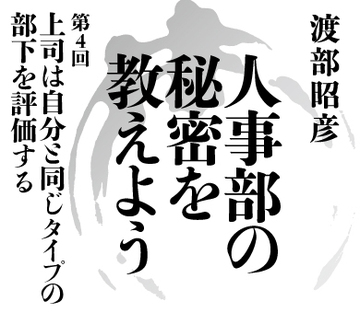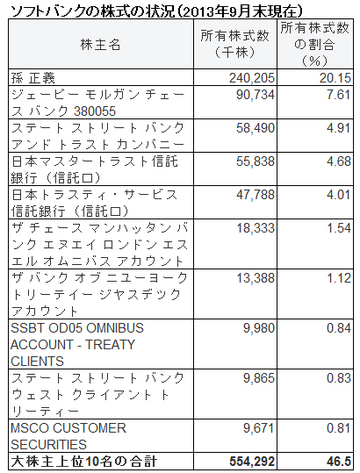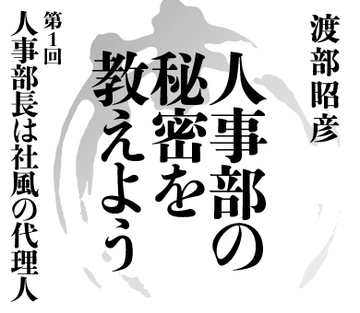大手銀行、セブン‐イレブン、楽天で、人事部長や人事担当役員を経験した渡部昭彦氏に、人事部や人事制度の裏側を教えてもらう連載の最終回。多くの会社で「珍現象」を引き起こした多面評価(360度評価)の実態と現状を解説してもらう。
いかにも日本的な「多面評価の使われ方」
1990年代のバブル崩壊以降、長期化する景気低迷下、日本の企業においては人事制度面でのさまざまな試みがなされた。低成長経済への移行を受け、戦後の終身雇用・年功型賃金に対する新機軸を打ち出そうとしたのである。その代表例が成果主義概念の導入だった。その重要なツールとして「目標管理制度」や「コンピタンシー評価」などが導入された。
これらのなかで、やや異彩を放っていたのが「多面評価」、いわゆる360度評価ではないだろうか。ご存じのとおり、上司のみならず部下や同僚、場合によっては顧客も含む周りの関係者が、対象者の仕事振りや行動を評価するのである。人事上の評価は上司が部下に対してするものという既成概念を覆し、「部下が上司を評価する」というのを初めて聞いたときには、私もさすがに「本当?」と驚いた。
多面評価は、もともとはアメリカにおいて能力開発のツールとして導入されたコンセプト。周囲のより多くの目で観察された人物像をベースに客観的な評価と分析を行ない、育成すべき能力を浮き彫りにする。成果主義のツールの一つとして導入されたのは、成果にもとづいて評価・処遇する以上、まずは評価自体の客観性と公平性を確保する必要があるとの考え方が根底にある。
この多面評価は新し物好きな大企業を中心に、かなりの数の会社が導入した。導入に先立ちトライアルと称して人事部が部内で試験的に実施、「結構面白いのでは」といったノリで具体化させた企業も少なからずあったようだ。
だが、当初よりいくつかの問題点が指摘された。たとえば、誰しも考えることだが、上司が部下に気をつかってしまい、日常のマネジメントがうまくいかないのではないかということだ。確かに部下に評価されることになれば、日常の業務中になかなか厳しいことが言いづらくなる。また、部下の評価が本来の仕事である管理職とは立場の異なる者が、いわばサイドワークとして人を評価することに、どの程度の信頼性を置いてよいかということもある。いつも自分をいじめている上司であれば当然厳しい見方をするだろうし、よく飲みに行く仲よしの同僚であれば思わず褒めてしまうだろう。このような恣意性の排除は人のやることである以上、なかなかむずかしいのは事実だ。
多面評価が導入された初期のころは、評価実施期間になると、やたらに部内の飲み会が多くなるとか、チーム全員で「談合」して全員がお互いに一番いい評価をつけるといった珍現象が結構見られた。なぜなら、なされた評価が給与・ボーナスなどの処遇に反映する仕組みだからだ。となれば「珍現象」も経済合理性のある行動と考えることもできる。
そこで最近、多面評価を活用する会社は、処遇に直接結びつけることはせず、もともとの趣旨である能力開発のコンセプトに立ち返り、あくまで社員にとっての「自己分析」「気づき」の目的で用いるようになっている。それは処遇との関連性がいわば「ポピュリズム(人民主義)」を生じる原因となったという認識と反省にもとづいている。
私は、これこそ日本の人事風土の特徴をストレートに現したものだろうと考えている。先ほど述べた欧米型の外部労働市場では、専門能力にもとづく採用とそこから創出される成果(ほぼイコール儲け)の分配というシンプルな仕組みが作用している。上司の権限は強力だが、ポピュリズムの入り込む余地は限られているのだ。
一方、日本の企業においては、背後に存在する社風が人事のすべてを決めている。とはいえ、通常の人事評価においては、たまたま会社の伝統的なDNAを体内に持っていない上司の場合、部下に対して社風に合致しない評価をする可能性は否定できない。その点、この多面評価は双方向や放射線状に形成される世論を反映するわけだから、社風の感性により近い評価がなされる。処遇が絡むと随所に煩悩が顔を見せるが、そこを切り離せば、多面評価は「気づき」を目的とする「能力開発型」として、いわば純化される。こうなると周囲の評価者は結構まじめに取り組むようで、多少の強弱はあってもかなり実際の人物像に近い線での結果が出てくる。
これをポピュリズムというのか真のデモクラシーというのかは率直なところよくわからない。ただ、一つだけ言えることは、多面評価が、ナルシストになりがちなわれわれの感性に対して、「他人の目で冷静に自分を分析する」という意識を持ち込んだ意義は大きいということだ。