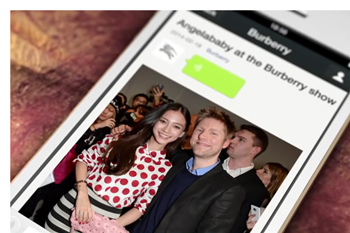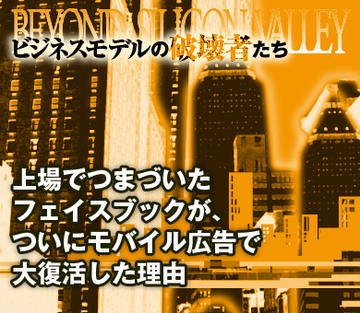「モバイル広告大賞」から
名称変更した理由
 「コードアワード2014」表彰式の様子
「コードアワード2014」表彰式の様子
2002年から昨年まで計12回、弊社主催で「モバイル広告大賞」を実施してきた。これは、それまで存在しなかったモバイルを活用したマーケティング・コミュニケーションの普及と発展のために寄与すべく、秀逸な企業事例を選出し、新たなチャレンジを試みた企業を表彰することを目的として実施してきたものだ。お陰様で、回を重ねるごとにこの賞は広く認められるところとなり、業界の普及と発展に一定の貢献ができたように思う。
しかし、時代は常に先に進んでいる。もはや、モバイルマーケティングは珍しいものではなく、マーケティング施策の中の一部として、組み込まれている。そんな時代の流れを受けて、審査委員の中からも、「モバイル広告大賞」という名称は、もう適切ではないのではないかという声が聞こえ始めていた。
D2Cのビジネスを考えても、それは同じで、モバイル専門の広告会社としてスタートしたが、すでに事業としてはデバイスで区切るという考え方はしていない。そこで今年からは賞の名称も内容も一新した。名付けて「コードアワード(CODE Award)」。CODEとは、デジタル世界を形成するソースコードを意味すると同時に、Creativity Of Digital Experience(デジタル体験の創造性)の略となっている。
つまりは、もはやモバイルだ、PCだということではなく統合デジタル施策が重要であるということと同時に、顧客の体験という観点に重きを置くことを意味している。
昨今、広告枠から人へとターゲットをより意識したデジタルマーケティングを意識すべきである論調や、カスタマージャーニーを通して、顧客価値を追求し、顧客の生涯価値を高めることを主眼としたマーケティング施策の重要性が高まっている。
デジタルマーケティングはO2Oやオムニチャネルといったリアルな概念も取り込んで、統合したマーケティングに突き進んでおり、広告賞のあり方も現在を象徴する各事例にスポットを当てようと考えた。