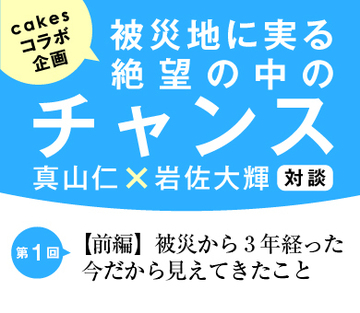――でも当時、書けなくなった、という作家が結構いっぱいいました。
真山 そのようですね。ミュージシャンでも、歌えなくなった人がいっぱいいたとか。こんな時に小説なんて書いてる場合かって思うんでしょうけど、私は書いてる場合だと思った。
もちろん、表層的なことで被災地を励ますだけなら、やめたほうがいい。それはあまり力にならないですね。だから、自分が立っているフィールドの中で、真摯に起きていることと向き合って考えていく、それを言い合うことが大事じゃないかと思います。
今こそ小説の力が試されています。大震災も原発事故も、もちろん起こるべきではない。でも、現実から目をそらさずに、今何が起きているかのど真ん中を考える時、小説という媒体は、とても適していると思いますね。
作中の登場人物にみる
自画像としての記者の姿
――今後、『そして、星の輝く夜がくる』(講談社、2014年)のように、内側から出てくるような小説をふたたび書く予定はありますか?
真山 来年1月に出す『雨に泣いてる』(幻冬舎)という書き下ろし小説では、一人称のハードボイルドを書いているんですが、主人公が新聞記者なんです。自分の中の理想の記者像というのが出てると思います。
――『コラプティオ』(文藝春秋、文春文庫)の神林裕太記者はどうだったんでしょう。
 真山氏の作品群をチェック!
真山氏の作品群をチェック!拡大画像表示
真山 彼は経済部なので、私にとっては距離がある。彼を書くのは楽でした。神林もこれから成長していくんでしょうけれど。
逆に自分に近すぎたのは、『虚像(メディア)の砦』(角川書店、現講談社文庫)に出てくる報道ディレクターの風見敏生です。あれは難しかった。一般読者が知りたいマスコミのツボと、私が伝えたいツボがずれてたんです。あと、やっぱり風見の動き方がバランスを欠いていた。
――風見は自己像に近い感じですか?
真山 彼は近いです。私もたぶん同じことをやると思いますね。でも、近すぎて暑苦しい。『虚像の砦』を読んだ方の中には、「いい大人が組織の中で、こんなハネ返った行動をするのか」って思った方もいると思います。でもするんですよ、記者は。ただ、小説ではその説得力が足りませんでした。
『雨に泣いてる』の主人公は大嶽というんですが、実は未刊行のまま眠っている2つの作品に出てくるキャラクターなんです。年季をかけて育てている、そのキャラクターを被災地に持って行くのがこの作品です。彼は、もし私が記者であり続けていたら、こうなりたかった男です。
――ある意味、自画像というわけですね。
真山 たらればワールドの自画像ですけれどね。新聞社を辞めなければ、もしかしたら、こうなっていたかもしれないと。
これができると思ったのは、『コラプティオ』で無頼記者の東條謙介を書けたからです。東條は、私がもっと年を取ったらこうなるだろうという記者像ですね。『雨に泣いてる』は震災当日から被災地に入った記者たちの物語です。
プライベートアイ、私立探偵ものはリアルな意味では日本ではできないので、それを大嶽という新聞記者を使ってやろうと思います。