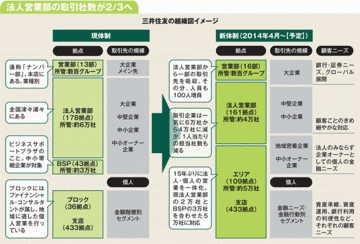しかし、銀行経営の本流といえば、やはり国内の企業向け貸出です。企業サイドでも、本業の設備投資だけでなく、値上がりを続ける不動産や株などの財テク用に銀行借入れを積極化するようになり、バブルが進行していく中で銀行と企業の皮相的な「ウィン・ウィン」の関係が築かれていきました。
特に急増したのは、中小企業やノンバンク、不動産、建設、そして個人といったセクターへの貸出です。その後、不動産市況の急速な悪化の下で銀行が処理に頭を抱えることになる不良債権の種は、こうして撒かれていったのです。
そうした国内事情を抱え、巨額の不良債権処理に全エネルギーを注力せざるを得なくなった邦銀は、一斉に海外から撤退をはじめ、国際金融市場を席巻したその短い全盛時代をあえなく終えました。
金融破綻のドミノ現象が始まった
1990年代の日本における金融破綻として最初に挙げられるのは、最後の相互銀行となった愛媛県の東邦相互銀行であり、1992年に伊予銀行によって吸収された際に行われた資金援助が、日本における預金保険制度の適用第1号となりました。
その後、大阪に本店を置く東洋信金の破綻などが続き、1994年には東京協和信金や安全信組が、1995年には木津信用組合やコスモ信組、そして兵庫銀行と、金融破綻は規模の大きな金融機関へと拡大していきます。
ただし、日本の金融破綻を概観する上で見逃せないのは住宅金融専門会社、いわゆる「住専」です。そもそも個人向け住宅ローン専門銀行としてスタートした住専は、銀行や信販そして公的機関である住宅金融公庫にシェアを奪われて苦戦し、次第に企業の不動産事業に対する融資を拡大するようになっていきました。
株価とともに上昇ペースを加速しはじめた不動産市況は、住専にとって願ってもないビジネス環境となりました。さらに、1990年に不動産向け融資抑制のための行政指導として銀行に発動された総量規制は住専を対象外としていため、銀行や農林系金融機関が競って住専に融資を行うようになったのです。
ただし、金利の上昇とともに、不動産価格はすでにピークに近付いていました。1991年頃から大都市圏を中心に地価が下落しはじめて1992年1月の全国公示価格は前年比4.6%低下となり、その後も下落幅を拡大しながら不動産市況は悪化の一途をたどっていきます。
銀行や農林系金融からの借入れをもとに急増していた住専の不動産担保融資の焦げつきが発覚するのは、もはや時間の問題でした。そして時間をおかず、1995年8月の当局検査によって、総資産の約半分の6兆円超という巨額の損失が判明したのです。その結果、大手住専7社は消滅することになり、最終的な損失処理には公的資金も投入されることになりました。
この住専問題は海外メディアでも「Jusen」として大きく報じられ、市場の注目を集めました。ただし、それは日本の金融機関の凋落の最終段階ではなく、始まりに過ぎなかったのです。
1997年11月には、豪華なディーリングルーム建設に象徴される過剰投資や、子会社による多額の不動産関連投資が問題視されていた三洋証券が破綻して、無担保コール資金がデフォルトするという前代未聞の事件が起きました。直後には「飛ばし」と呼ばれた巨額の簿外債務が発覚した山一證券が自主廃業を発表。そして都市銀行の一角であった北海道拓殖銀行が不良債権処理を行う体力が尽きて経営破綻するなど、日本経済に激震が走ったのです。
特に、北海道拓殖銀行の破綻は、ほかの都市銀行や長信銀に対する不安を募らせることになりました。どの銀行も、程度の差こそあれ、相当額の不良債権を抱えていることは明らかだったからです。