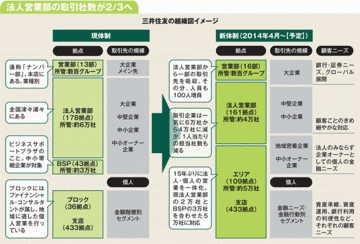しかし、海外市場における業務拡大や証券会社と競う形での国債取引などは、市場知識や市場経験がモノを言う戦場であり、規制に守られて生きてきた邦銀にとっては不得意な分野でした。
かろうじて大手邦銀には、外国為替取引において市場ビジネスに関わるノウハウが蓄積されていましたが、それをほかの業務分野にまで応用する経営力や人材は、決定的に不足していたのです。海外投資銀行への出資や買収は結果を出せず、有価証券取引も証券会社に太刀打ちできないまま、銀行は自分自身の専門分野である「融資」に光を見出すしかありませんでした。不動産価格の上昇は、銀行にとって願ってもない、そして残された唯一の救世主だったのです。
ただしその不動産も、本来は市場需給や景気動向などよって価格が決まるものです。融資の際に判断される担保価値は、その不動産が今後どれだけの収益を生むかという点で推測されるべきものでしょう。ところが、株価と同様に上昇を続ける不動産市場を眺め、銀行経営の管理意識から「不動産価値の下落リスク」はすっぽりと抜け落ちていきました。銀行が不良債権の山に埋もれていったのは、時代の不運な巡りあわせという見方もありますが、市場ビジネス感覚の欠乏から来る必然でもありました。
海外業務は引き潮のように撤退へ
1990年代半ば以降、国内で不良債権問題が深刻化すると、海外業務に対しても本部からの強力なコミットメントは消え、銀行系現地法人が欧米勢と戦い続けるための戦力は次第に失せてしまいました。銀行の大型合併によって、海外の支店や現地法人も再編やリストラの対象となり、優秀な人材も続々と去っていきました。
当時の邦銀による海外金融関連会社への出資や買収の例として、住友銀行によるゴールドマン・サックスへの出資、長銀によるグリニッジ・キャピタルの買収、富士銀行によるヘラー・フィナンシャル買収、第一勧業銀行によるCIT買収といった案件が挙げられますが、いずれのケースも大成功には至りませんでした。
当時の邦銀海外戦略を振り返れば、融資や為替、資金だけでなく証券など新規分野に関しても、経営は日本人が行うのが一般的でした。ですが、市場という刻々と変動する座標軸で動いている国際金融の世界を、市場感覚の乏しい経営者が指揮することは明らかに競争力の面で劣後していたのです。
当時の邦銀経営者の市場感覚の欠乏は、国内だけでなく海外でも致命傷になりました。海外金融を買収しても、その実質的経営に入り込めない、というもどかしさも打破できないままでした。それは、21世紀にまで積み残された大きな課題として、いまなお邦銀経営を悩ませています。