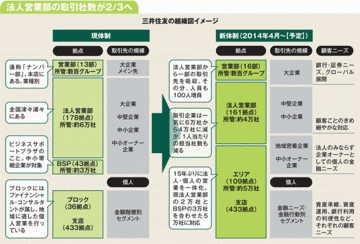日本発の金融システム不安が起きるのではないか、という不安すら高まる中で金融監督庁が発足し、大手銀行に対する厳しい集中検査が行われました。そして結果として、日本長期信用銀行と日本債券信用銀行の2行が大幅な債務超過とみなされ、国有化されるという衝撃的な結末を迎えたのです。
日本政府はパニックを収束させるため、生き残った大手行すべてに公的資金を投入する方針を固め、21世紀に入ってようやく金融システムは落ち着きを見せはじめます。最終的に、2003年にりそな銀行への2兆円規模の公的資金投入で、日本の金融問題は一応の決着をみました。株価がピークを打ってから15年という、実に長いトンネルでした。
市場感覚の欠如が招いた不幸
銀行というのは、家計などから預金を集めて企業にカネを貸す業態です。実際には、企業が必要としている資金を家計などから集める、という逆の説明の方が現実的ですが、いずれにしてもその間の金利差、つまり利ザヤで稼ぐのが銀行であり、そこに一定の規制が働いていれば、貸出先がつぶれない限り収益性は確保できるはずです。
日本の場合、戦後の経済復興を支えるための安全な金融システムを構築しようと、政府は「護送船団方式」と呼ばれる銀行政策を採りました。預金金利の上限を定めて無用な預金獲得競争が起きることを回避し、1年未満の貸出金利に関しては臨時金利調整法によって規制が敷かれてきたのです。こうした中で、弱小の金融機関も落伍することなく、銀行は安定的な収益構造が確保されていました。
また預金調達ルートが債券に限定される長期信用銀行には、主要調達手段である金融債の金利に一定のスプレッドを乗せた貸出金利を長期プライムレートとして設定し、利ザヤを確定するシステムを導入しました。すなわち、銀行は潰さないというのが、日本の金融行政の鉄則だったのです。
1970年代に入ると、徐々に金融の自由化の波が押し寄せてきます。企業は余裕資金を現先市場で運用するようになり、銀行預金よりも有利なリターンを得るようになりました。一方で社債市場の自由化によって、優良企業は銀行借入れよりも低いコストで資金調達を行えるようになったのです。
1984年には、外為市場における実需原則が撤廃されて為替取引の自由度が増すと、企業は外債を発行して円ヘッジを行う新たな円資金調達方法に注力するようになりました。特に、株高を背景として転換社債やワラント債を使った実質的なゼロコスト(場合によってはマイナスコスト)の資金調達は日本企業に大人気となり、ロンドンやスイスなどの欧州市場では連日のように、日本企業の債券が発行されました。
バブル景気に乗った内部留保の蓄積や新株発行による資金調達なども、企業の手元流動性を厚くすることになり、1980年代には一気に「銀行離れ」が加速しました。銀行経営は、海外進出や証券取引、あるいは不動産関連融資といった、新たな拡大戦略を検討せざるを得なくなっていたのです。