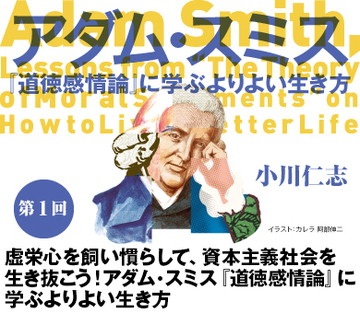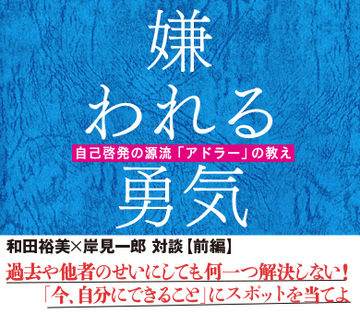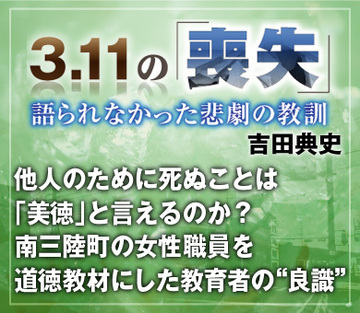スミスによると、他人の気持ちに対する私たちの想像力は、「かれの身体にはいりこみ、ある程度かれになって、そこから、かれの諸感動についてのある観念を形成する」(上P25)ことで生じるようです。これが同胞感情の源泉だとされるわけです。あたかも他人に憑依し、みずから同じ経験をしているかのようなイメージですね。
たしかに、私たちは悲惨な目に遭った人たちの話をニュースで聞いただけで即、疑似体験して、胸が締め付けられる思いをするものです。交通事故、誘拐、殺人……。まさにスミスが「恐怖と懸念は、人間の胸の大拷問者」(上P33)と表現する通り、まったくの他人事であるにもかかわらず、私たちは苦しみます。ほかでもない自分自身の想像力が、心に拷問を加えているわけです。
そしてもちろん、逆に他人が喜んでいるようなときは、私たちも嬉しい気持ちを感じることができますし、他人が誇らしく思っているときは、こちらも誇らしく思うのです。皆さんも、自分の国のオリンピック選手がメダルを獲ったとき、まるで自分のことのように誇らしく感じたことはありませんか?
この他人の感情や行為について適切性を判断する心の作用を、スミスは「同感(sympathy)」と呼んだのです(なお、「共感」という訳もありますが、引用文との整合性を図るためにも、底本として利用した岩波版『道徳感情論』に合わせています)。
スミスの「同感」概念の新規性とは?
同感という概念自体は、当時の道徳哲学者の間ではよく知られていたようで、スミスのオリジナルというわけではありません。ただ、『アダム・スミスとその時代』の中でフィリップソンは、スミスの概念の新規性を次のように表現しています。
スミスにとっては、このお馴染みの考えは、了解されていたよりも多くのことを説明する力をもっていたのである。彼の素晴らしい功績は、これを商業の一般理論にとって土台となる社交性理論の、支配的な原理へと変えたことであった。(『アダム・スミスとその時代』P196)
つまり、スミスは同感という語が持つ意味内容を特別なものにしたわけです。しかもそれは、社交性理論の支配的原理になったといいます。実はこれは、歴史上の大発見といっても過言ではありません。なにしろこの概念は、古代ギリシア以来、「私」すなわち個人を中心に展開してきた哲学の歴史を大転換するものだからです。
「私」を中心に展開してきた哲学のひとつの到達点は、近世フランスの哲学者ルネ・デカルトのコギトだといわれます。コギトとは「コギト・エルゴ・スム」、いわゆる「我思う、ゆえに我あり」のラテン語訳です。あらゆるものは疑えるけれども、自己意識としての「私」だけは疑えない、だから自己意識としての「私」こそが一番大事だという意味です。