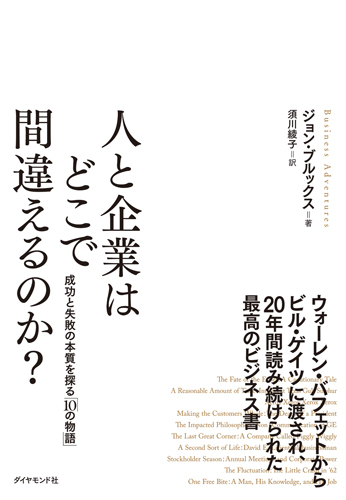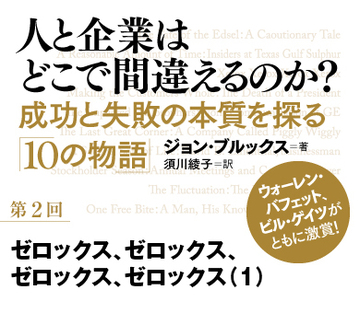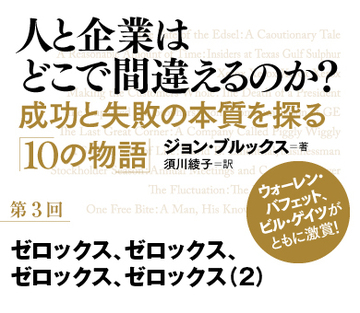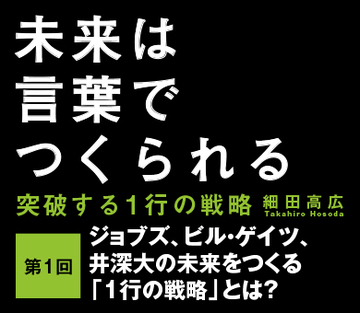2014年夏、マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツは、自身のブログ「gatesnotes」で『Business Adventures』という1冊の本を紹介した。20年以上前にウォーレン・バフェットから推薦されたもので、以来「最高のビジネス書」として愛読し続けているという。世界で1、2を争う大富豪であり、伝説的なビジネスマンと投資家である2人がそろって絶賛する本ということで、世界的に大きな話題となった。
今回、その邦訳である『人と企業はどこで間違えるのか?』の出版にあわせ、ビル・ゲイツが「最も教訓的なストーリー」と評するエピソード、「ゼロックス、ゼロックス、ゼロックス、ゼロックス」を公開する。
私はこうして、ゼロックスの製品について知り、それが社会にもたらす影響について考察する一連の作業を終えた。そこで今度は、ロチェスターのゼロックス社を訪れ、社内の様子をじかに観察し、関係者が具体的な問題や道徳的な問題についてどう対処しているのか確かめることにした。私が訪れたとき、差し迫っていたのはもちろん具体的な問題だった。というのも、株価が42と1/2ドルも下落した週からまもなくのことだったからだ。行きの飛行機のなかで、私は最新の株主総会招集通知のコピーを眺めていた。そこには1966年2月の時点で各取締役がどれだけ株式を保有しているか1覧が載っているので、数が変わっていないと仮定し、10月の株価急落の週に彼らがどれほどの資産を失ったか計算して楽しんだ。たとえば、ウィルソン会長は2月に普通株式を15万4026株保有していたので654万6105ドルの損失。リノウィッツは3万5166株で149万4555ドル、研究開発部門の責任者で上級副社長ジョン・デッサウアー博士は7万3845株で313万8412.5ドルの損失という計算になった。これだけの額ともなれば、ゼロックスの重役といえどもけっして小さな額ではない。彼らはすっかり悲観的になっているのだろうか。少なくとも動揺の色は見られるのではないだろうか。
ロチェスターのゼロックス本社は、1階が屋内ショッピングモールになっているミッドタウン・タワーにあり、役員室は上層階に位置していた(この年の末、本社は通りの向かいのゼロックス・スクエアに移転した。31階建てのオフィス棟に加え、市民も利用できるホールや半地下のスケートリンクなどもある複合施設だ)。ゼロックスのオフィスに上がる前に、まずはショッピングモールを見て回った。さまざまな店舗やカフェが並び、新聞や雑誌を売るスタンドに人工池、植栽、ベンチなどもある。館内は退屈なくらい穏やかで豊かな雰囲気に包まれていた。きっと館内に流れているのどかな有線放送のせいだろう。ところがベンチを見ると、まるで野外のショッピングモールのように浮浪者が陣取っている。光と空気が足りないのか植物は元気がなかったが、浮浪者は快適そうだ。
エレベーターでオフィスへ上がると、約束していた広報担当者が待ち受けていた。私はさっそく、株価の下落を受けて会社がどんな様子か尋ねた。「ああ、そのことなら誰も深刻にとらえていませんよ」と彼は応じた。「ゴルフクラブでは、みんなのんきなことばかり言ってます。『1杯おごってくれよ――こっちは昨日また、ゼロックスで8万ドル損したんだから』なんてね。ウィルソン会長は証券取引所で取引が中断した日はさすがにちょっとショックを受けていましたが、その後は冷静に受け止めています。現にこの前、株価が急落している最中にパーティーがありまして、会長は大勢の招待客からどうなっているんだと問い詰められていましたが、『そうだな、チャンスは一度しか訪れないと言うからな』、なんて応じてました。社内では、ほとんど話題にもなりません」。実際、私がゼロックスを訪れているあいだこの話を耳にすることはなく、やがてこうした冷静な対応が正しかったことが明らかになった。なぜなら、1ヵ月もすると株価はすっかり回復し、数ヵ月後には史上最高値をつけたからだ。
広報担当者への取材を終えると、今度は午前中いっぱいをかけて、3人の科学技術系のスタッフからゼログラフィ開発時のなつかしい話を聞かせてもらった。まずはデッサウアー博士だ。博士は前の週に300万ドルを失っているはずだが、あくまでも落ち着いていた。もっとも、当然といえば当然のことかもしれない。株価が下がったとはいえ、彼の持ち株の価値はおそらく950万ドルを超えていたものと思われるからだ(数ヵ月後、その額は推定で2000万ドル近くに膨らんだ)。ドイツ生まれのデッサウアー博士はゼロックスの古株だ。1938年から研究開発を担当し、やがて取締役副会長に就任した。45年に技術雑誌でカールソンの発明に関する記事を読み、ジョセフ・ウィルソンに最初に知らせたのが彼である。私は彼のオフィスで、壁に飾ってあるカードに目を留めた。スタッフから送られたもので「魔法使いへ」とある。博士は笑顔を絶やさないはつらつとした人物で、魔法使いにふさわしい独特のアクセントで話す。
「昔の話を聞きたいそうだね」とデッサウアー博士は言った。「まったく、刺激的な毎日だったよ。素晴らしい日々だった。だが、苦しい思いもした。大げさじゃなく、ときどき頭がおかしくなりそうになることもあった。いちばんの問題は資金繰りだ。会社は幸いにもとりあえず黒字だったが、十分ではなかった。われわれのチームはコピー機の開発にすべてを賭けていた。私は自宅まで抵当に入れたんだ――何もかも注ぎ込んで、残るは生命保険だけになった。まさに危ない橋を渡っていた。うまくいかなければウィルソンも私も事業に失敗することになるが、私の場合はエンジニアとして失格の烙印を押されることになる。もうどこにも雇ってもらえなくなるわけだ。そうなったら科学をあきらめて、保険のセールスマンにでもなるしかないと思っていた」
デッサウアー博士は思い出にふけるようにひとしきり天井を見つめ、それから先を続けた。「最初の何年かはみんな弱気だった。チームのメンバーの誰もが私のところにきて、絶対に無理だと訴えたものだ。最大の懸念は、湿度が高いところでは静電気が起きないのではないかということだった。ほとんどすべての技術者がそう考えていた――よく『ニューオーリンズじゃコピーできない』と言っていたな。それに、マーケティング部門の連中からは、仮に開発に成功したとしても、需要はせいぜい数千台だと思われていた。専門家たちからは、こんなプロジェクトを進めるなんて正気じゃないと言われたものさ。ところが知ってのとおり、すべてがうまくいった――914が完成し、ニューオーリンズでもちゃんと動いた。しかも飛ぶように売れた。それで今度は卓上型の813を発売したわけだが、専門家から壊れやすいと指摘されたデザインにこだわって、またもや危ない橋を渡ることになったんだ」
私は博士に、今も新しい研究で危ない橋を渡っているのか、またそうだとすれば、それはゼログラフィと同じくらいすごいものなのかと尋ねた。すると博士は言った。「どちらの質問も答えはイエスだ。しかし、何の研究かは明かせんよ」
次に会ったのは、デッサウアー博士のもとでゼログラフィの開発プロジェクトの現場責任者を務めていたハロルド・クラーク博士だ。彼はカールソンの発明が1つの製品へと育まれていった様子をさらに詳しく語ってくれた。「チェスター・カールソンは形態学的でした」。そう語り始めたクラーク博士は学者的な雰囲気が漂う小柄な人物だ。実際、1949年にハロイド社に加わる以前は物理学の教授だった。きっと私が戸惑った表情をしていたのだろう、クラーク博士は小さく笑ってこう続けた。「『形態学的』という言葉の意味は、本当のところ私にもよくわからない。私が言いたいのは、組み合わせによって新しいものをつくるということです。とにかく、チェスターはそれをやってのけた。ゼログラフィには基礎となるような過去の科学的研究がほとんどありません。彼はありふれた現象を寄せ集めました。どれも地味な現象で、それまで誰も組み合わせて利用しようとは思わなかったものばかりです。結局、画像処理の分野では、写真技術の登場以来、最大の発明となりました。しかも、科学的研究を行うのにかなり不利な環境のなかで成し遂げたのです。科学の歴史を遡れば同じくらい重要な発見はいくつもありますが、チェスターはずば抜けた発明家です。彼の発見について初めて耳にしたときは目を見張りましたが、その驚きは今でも変わっていません。それは鮮やかなアイディアでした。ただし、製品化となると厄介でしたね」
クラーク博士はまた少し笑い、説明を続けた。転機はバテル記念研究所で訪れたという。昔から科学の進歩は何気ないことからもたらされてきたが、このときも例外ではなかった。カールソンが考えた硫黄を塗った感光板は、数回コピーしただけで性能が低下し、使いものにならなくなる。そこでバテルの研究者たちは、何の科学的根拠もなく、勘だけに頼って硫黄にセレンをほんの少し加えてみた。セレンとは非金属性の元素で、かつては主に電気抵抗器に用いられたり、ガラスを赤く染める着色剤として利用されたりしていた。セレンを加えた硫黄の感光板は、硫黄だけのときより性能がわずかに向上した。さらに少し量を増やしてみるとまた少し向上した。そこでセレンの割合を少しずつ増やしてゆき、最終的にセレンだけにしたところもっともよい結果が得られた。こうして地道な手順を踏んだことで、セレンによって、しかもセレンさえあれば、ゼログラフィを実用化できることが明らかになった。
「考えてみてください」とクラーク博士は感慨深そうに言う。「セレンは単純な物質です――地球上に存在する100種類ほどの元素のなかでもとりわけありふれたものです。それが鍵になるとは。その効果が明らかになると、開発はあと1歩でした。もっとも、そのときはどうしてそういう効果が得られるのかわかりませんでした。私たちは今も、ゼログラフィでセレンを使用する方法についていくつかの特許を保有しています――いわば、元素の1つについて権利を保有しているようなものです。なかなかすごいことだと思いませんか? セレンが作用する仕組みについては今でも正確にはわかっていません。たとえば、どうして記憶効果がないのかわからない――セレンを塗ったドラムには前のコピーの跡が残らないのです。それから、理論的には永久に使用できるように思われますが、それもまた不思議です。実験室でならセレンを塗ったドラムは100万回コピーしても性能が落ちないのです。しかし、実際に試してみたところで、なぜそれだけ耐えられるのかはわかりません。つまり、ゼログラフィの開発は、ほとんど経験的に進められたわけです。私たちは経験を積んだ科学者であって町の職人ではありませんが、職人技と科学的探究をうまく両立することができたのです」
最後に話を聞いたのは技術者のホレス・ベッカーだ。914の製品化にこぎつけるまでの過程で中心的な役割を果たした人物である。ブルックリン生まれの彼は、難しい仕事をやり遂げるまでの苦労話を生き生きと語ってくれた。1958年、彼がロチェスターのハロイド・ゼロックス社で働き始めたとき、開発室は園芸用種子を梱包する作業所の屋根裏にあった。屋根が傷んでいて、気温が高くなるとすきまからタールがにじみ出し、技術者や機械にしたたり落ちた。1960年の初めに914がついに完成したとき、開発室はオーチャード・ストリートに移っていた。「そこも古くてみすぼらしい建物の屋根裏だった。エレベーターはひどい音を立てるし、窓の外には鉄道の側線が走っていて、豚を詰め込んだ貨物列車がひっきりなしに行き交ってたもんさ」。ベッカーはそう振り返る。「でも、広さは十分だったし、タールも落ちてこなかった。どういうわけか、オーチャード・ストリートに移ってからというもの、俺たちのやる気に火がついた。そろそろ本腰を入れなきゃならないってね。みんな生き生きしてたよ。組合員はしばらく不満を訴えるのを忘れ、上司は勤務評定をつけ忘れるくらいだった。技術者も組立工も1緒になって働いた。みんな現場から離れられなかった――日曜はラインが停止するんだが、こっそり覗いたら、誰かが機械をいじっているところや、ただ歩き回って自分たちの作品にほれぼれしてるのを目にしたはずさ。そしていよいよ、914が世に出たんだ」
ところが、ベッカーによると、914がいざ発売されてショールームや顧客のもとに届けられるようになると、そこからが苦労の始まりだったそうだ。なぜなら、故障と設計上の欠陥の責任がすべてベッカーの身に降りかかってくるようになったからだ。914は華々しくスポットライトを浴びた瞬間に大失態を演じ、あのエドセル[訳注 『人と企業はどこで間違えるのか?』第1章に登場する]とまったく同じ状況に追い込まれた。複雑な工程の連携がうまくゆかず、スプリングが壊れ、電源も機能しなくなった。不慣れなユーザーがホチキスの針やクリップを落とし、それが内部に入り込んで動かなくなることもあった(どの機種にもホチキス・キャッチャーが取り付けられたのはそのせいだ)。湿度が高い環境では問題が起きることは予想していたが、標高の高い場所でも不具合が生じるとは思ってもみなかった。「だいたい、あのころの914は、スイッチを押してもうんともすんとも言わないことがしょっちゅうだった」とベッカーは言う。とりあえず動き出しても、まともに機能しないことが多かった。たとえば、ロンドンで大々的に開催された最初の展示会は散々だった。わざわざウィルソンが登場し、人差し指でうやうやしくスタートボタンを押したのに、コピーが出てくるどころか、電流を供給する大型発電機のヒューズがとんでしまったという。ゼログラフィのイギリス・デビューはそんな調子だった。このときの状況を考えると、のちにイギリスが国外最大の914ユーザーとなったのは、ゼロックスの粘り強さとイギリス人の忍耐力のたまものといえるだろう。
午後はある社員の案内で、ロチェスターから数マイル離れたオンタリオ湖畔近くの田舎町ウェブスターを訪れた。ベッカーが屋根裏で奮闘していたころとは似ても似つかない開発製造施設があると聞いたからだ――現れたのは、現代的な工業用建物が並ぶ巨大な施設だった。1万平方メートル近くはありそうな建物は、ゼロックス社のすべてのコピー機(イギリスと日本の関連会社で製造されている製品を除く)が組み立てられている工場だ。それより小さくてしゃれた建物では研究開発が行われていた。活気あふれる製造ラインを見学しながら、私は説明を受けた。製造ラインは2交替制で1日16時間稼働しているが、複数ある製造ラインでもここ数年は需要に追いつかないという。目下、この施設では2000人近くが働いているが、労働組合は全米合同衣服労働組合の支部になっている。この変わった組み合わせは、かつてロチェスターが繊維業の中心地として栄え、この地域では同組合が最大の勢力を誇っていたことの名残だそうだ。
案内役に再びロチェスターまで送り届けてもらうと、今度は地元の人々がゼロックス社とその成功についてどう感じているのか調査するため取材に出かけた。すると人々が複雑な思いを抱いている様子が浮かび上がった。ある地元のビジネスマンは次のように語ってくれた。「ゼロックスはロチェスターに貢献してきた。もちろん、昔からこの町の権力者はイーストマン・コダックだし、今でも地元企業じゃダントツで最大手だ。だけど、ここのところゼロックスも二番手として成長著しい。そんなライバルの出現はコダック社にとって少しも害にはならない――それどころか、いろいろと利点があるはずだ。おまけに、地元で新興企業が力をつければ地域も潤い、雇用も増える。だがその1方で、ゼロックスに対する反感もある。この辺の産業は19世紀から続く古いものばかりだから、新三者には必ずしも寛容じゃないんだ。ゼロックスが急成長したとき、そのうちバブルがはじけるぞと思ってた連中も多かった――いや、はじければいいと期待していた。加えて、ジョセフ・ウィルソンとソル・リノウィッツへの根強い反感がある。彼らはいつも人間の価値がどうこうと言ってるのに、がっぽり儲けているわけだから。まあ、そういうものだけど――成功するということは」
私は続いてジェネシー川のほとりにそびえるロチェスター大学を訪れ、学長のアレン・ウォリスから話を聞いた。長身で赤みがかった髪のウォリスは統計学の専門家であり、イーストマン・コダック社(同社は長年にわたりロチェスター大学のサンタクロースとして最大規模の資金提供者である)を含め、いくつかの地元企業の社外取締役を務めている。ロチェスター大学はゼロックス社に対して好意的だが、それにはいくつかの理由がある。第1に、この大学はいわゆるゼロックス長者である。ゼロックスへの投資からもたらされた含み益は1億ドルに達し、すでに1000万ドルを換金している。第2に、ゼロックスも毎年コダックに次ぐ多額の寄付を行っており、つい最近は大学に対して600万ドル近くの出資を約束している。第3に、ウィルソン自身がロチェスター大学の卒業生であり、1949年から理事会のメンバーとなり、59年からは理事長を務めてきた。
「現在、コダックとゼロックスは多額の寄付をしてくれていますが、私は62年にこの大学の学長に就任するまで、企業が大学にこれほどの大金を寄付する例は聞いたことがありませんでした」とウォリス学長は述べる。「どちらも寄付の見返りとして求めるのは、大学が最高レベルの教育を提供することだけです――自分たちのビジネスに役に立つ研究をしてくれといった要請はいっさいありません。もちろん、大学の研究者たちはゼロックスと技術的な課題について活発な意見交換をしています――それはコダック、ボシュロムといった企業も同じです。ですが、彼らが大学を支援するのはそのためではありません。ロチェスターを魅力的な場所にして、優秀な人材を引き寄せたいのです。大学はゼロックスのために研究をしたことはありませんし、それは今後も変わらないでしょう」
翌朝はゼロックスの幹部のオフィスを回り、経営の舵を握る3人の最重要人物に会った。最後はウィルソンで締めくくることにして、まずはリノウィッツを訪ねた。1946年に弁護士として「単発」の仕事を任され、そのままウィルソンの右腕となった人物だ(ゼロックスが有名になってから、リノウィッツは実際よりもっと高い役職に就いていると思われることが多かった――つまり、CEOと間違われることが多かった。ゼロックスの役員たちは、長年ウィルソンに仕えてきたリノウィッツがどうしてCEOと誤解されるのか不思議でならなかった。ちなみに、ウィルソンは66年の5月まで社長を務め、その後は会長に就任している)。
私は文字どおり走り回っているリノウィッツをつかまえた。彼はちょうど米州機構[訳注 1951年発足。南北アメリカの国々の諸問題の解決を目指す国際機関]のアメリカ大使に任命されたところで、ロチェスターとゼロックスに別れを告げ、新天地のワシントンへ旅立つ準備をしていた。50代のリノウィッツは意欲と情熱と誠実さを持ち合わせた精力的な人物という印象を強く受ける。彼はほんの少しの時間しか取れないことを謝ると、早口で言った。彼個人の意見としては、ゼロックスの成功は自由企業を理想とする古くからの精神が今でも生き続けている証であり、ゼロックスに成功をもたらしたのは理想主義と粘り強さ、リスクを冒す勇気、そして情熱である。彼はそれだけ言うと、手を振って去っていった。私はまるで、地方遊説中の候補者の短い演説を聞いた気分になった。だが、そうした演説を聞いた有権者によくあるように、私はすっかり心を奪われた。リノウィッツはごくありふれた言葉を使っただけだが、彼が語ると本来の意味より新鮮に聞こえるのだ。私は、ウィルソンもゼロックス社も彼を手放すことになり、残念に思っているだろうと感じた。
次に見つけたのはピーター・マッカラーだ。ウィルソンの会長就任後、1968年にCEOに就任した彼は、見るからに後継者にふさわしい風格を漂わせている。檻の中の動物のようにオフィス内を行きつ戻りつし、ときどきスタンディングデスクの前で足を止め、何やら書き付けたり、口述録音機に向かって短くつぶやいたりしている。リノウィッツと同じく民主党を支持するリベラルな弁護士だが、カナダ生まれの明るく社交的な性格で、40代前半という若さからゼロックスの新世代を象徴する存在であり、会社の将来の方向性を決める人物だ。
「目下の課題はどう成長するかです」。彼は歩き回るのをやめ、落ち着かない様子で椅子に浅く腰かけるとそう口を開いた。ゼログラフィ市場は飽和状態に近く、今後も大幅な成長を見込むのはどう考えても不可能であり、ゼロックスは教育関連の技術開発に力を注ぎ始めているという。彼はコンピューターや教育機器について例を挙げ、「コネチカットで書いたものが、数時間後にはアメリカ中の学校で印刷できるシステムをつくることも夢じゃない」と言った。私はこれを聞いて、ゼロックスが追い求める夢のなかには、たちまち悪夢に変わるものがありそうだと心配になった。しかし、彼はこうつけ加えた。「すぐれたハードウェアは必要だが、それに気を取られて教育の内容が二の次になる危険性がある。内容が疎かになったら、いくら素晴らしい機械があっても意味がない」
マッカラーは1954年にハロイド社に入社したそうだが、これまで3つのまったく異なる企業に勤めてきたような感じがするそうだ――59年までは危険で刺激的な賭けに夢中になっていた零細企業、59年から64年までは勝利に酔いしれる成長企業、そして今では多角化を目指す巨大企業。どの時代がいちばん好きかと尋ねると、彼はしばらく考え込み、ようやく口を開くとこう言った。「わからない。以前はもっと自由な雰囲気があった。会社の誰もが具体的な問題について考えを共有していた。たとえば、労使関係とか。ところが、最近はそういう感覚がない。社内では重圧が大きくなり、人間味が失われつつある。昔に比べてけっして楽ではないし、この先も楽になることはないだろう」
ジョセフ・ウィルソンについて何よりも驚いたのは、案内されたオフィスの壁が古風な花柄だったことだ。ゼロックスの頂点に立つ人物の趣味としては、あまりにも似つかわしくない気がした。だが、彼の家庭的で少しも威圧感のない物腰は壁紙の雰囲気とぴったり合っていた。50代後半の小柄な彼は、私の訪問中ほぼずっと厳粛ともいえる真剣な表情で、ゆっくりと言葉を選びながら質問に答えてくれた。まず、親の会社を継いだ経緯を尋ねると、じつはそんなつもりはなかったという答えが返ってきた。大学では第2選考で英文学を学び、大学に残って教鞭をとるか、財務・管理部門で働くことを考えていたそうだ。しかし、卒業後ハーバード・ビジネススクールに進み、そこで首席になったことと、いろいろな事情が重なり、ビジネススクールを修了するとそのままハロイド社に入社したという。彼はふとほほ笑んで言った。「それで今に至っているわけです」
ウィルソンがとくに熱を込めて語ったのは、ゼロックスの非営利活動と企業責任についての持論だった。「この件についてはいくぶん反感を買っています」と彼は言う。「私が言いたいのは、株価の下落で腹を立てている株主のことだけではありません――それなら危機からは脱しつつありますからね。気がかりなのは地域社会から反感を持たれていることです。あからさまな言い方ではなくても、地域の人々が心のなかで『この成り上がりときたら、何様のつもりだ』と思っているのが直感的に伝わってくることがあるのです」
私は国連のシリーズ番組に反対する手紙が殺到したとき、社内に不安が広がったり、弱気な意見が出たりしなかったかと尋ねると、彼はこう答えた。「組織として私たちが揺らぐことはありません。会社の誰もがほぼ例外なく、批判されるおかげで私たちが世の中に伝えようしている信念に、つまり、国際協力こそが私たちの課題であるという信念に注目が集まると思っていました。国際社会は協調なくしては成り立たず、ひいてはビジネスも成り立ちません。私たちはあの番組を放送したことで、健全な経営方針を全うしたと信じています。だからといって、ほかのやり方を否定するわけではない。たとえば、私たち自身がジョン・バーチ協会の会員だったら、番組を放送していたかどうかわかりません」
ウィルソンはゆっくりと続けた。「企業が重要な社会的関心事について立場を表明すれば、つねに自分自身が問われることになります。大切なのはバランスです。ただ当たり障りのないことを言っているだけでは与えられた影響力をむだにしてしまう。だが、すべての重要な問題について立場を明らかにすることもまた不可能です。たとえば、国政選挙について立場を公表するのは企業の役目だとは思いません――ソル・リノウィッツは民主党で私は共和党ですから、これはありがたいことです。大学教育、公民権、黒人雇用などの課題は、明らかにわが社が取り組むべきものです。たとえ反対意見の多い立場であっても、支持すべきことは支持する勇気を持ちつづけたいと願っています。今のところまだ、そういう状況に置かれたことはありませんが――つまり、市民として果たすべき責任と良好なビジネスが対立したことはありません。それでも、いずれそういうときがくるかもしれません。いつか非難の矢面に立たされる日がくるかもしれない。あまり宣伝はしていませんが、私たちは黒人の若者が掃除以外の仕事につけるよう支援しています。この取り組みには労働組合の全面的な協力が必要なので、いったんは協力を取りつけました。ところがかすかな変化から、蜜月が終わったことに気がつきました。組合には根強い反対意見があったのです。それは由々しき火種であり、大きくなったら経営に深刻な問題をもたらす恐れがあります。反対派が数十人から数百人へとふくらんだらストライキへと発展しかねません。もしもそうなったら、ひるむことなく組合の幹部と闘いたいと思っています。とはいえ、実際のところはわからない。いざそうなったとき、自分がどうするか確実に予言することはできませんが、とにかくそうすべきだと思っています」
ウィルソンは立ち上がって窓辺にたたずむと、ゼロックスが現在取り組むべき最大の課題は、会社がこれまで培ってきた個人と人間性を尊ぶ精神を維持することであり、それは今後さらに大きな課題となるだろうと言った。「私たちはすでに、この精神が失われつつある兆候に気づいています。新しい社員に伝えようと努力していますが、西半球の各地に2万人の社員を抱えるようになった今では、ロチェスターの1000人だけを相手にしていたころとはまるで事情がちがいます」
取材を終えるにあたり、私もウィルソンのかたわらに立って外の景色を眺めた。どんよりとした薄暗い朝だった。ロチェスターの天気はほぼ1年中はっきりしないそうだ。私はウィルソンに、こんな重苦しい天気の日には、古きよき精神を守れるかどうか不安にならないかと問いかけた。彼は小さくうなずいてこう言った。「これは永遠に続く、勝つとも負けるともしれない闘いなのです」