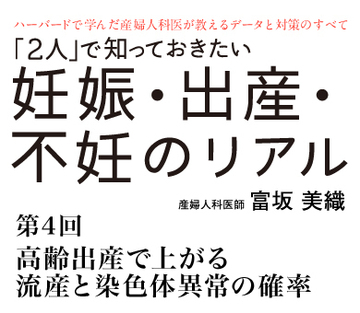チェン教授らは、一般集団における新型出生前診断の精度に関しては情報が限られており、新型出生前診断と確定診断の結果の不一致に懸念を示しています。特に企業は、低リスクの妊婦における稀な染色体異常の検出にまで、新型出生前診断を拡大しています。チェン教授らは、新型出生前診断は、確定診断を提供するわけではないので、「DNAに基づく非侵襲的出生前スクリーニング(DNA-based noninvasive prenatal screening)」と呼ぶべきだと主張しています。また、米国産婦人科学会、米母体胎児医学会の推奨するように、スクリーニングの陽性結果を得た妊婦は、確定検査をうける必要性があることを主張しています。
この3つの報告を受けて、同日のニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌の論説で、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(University College London:UCL)児童健康研究所(Institute of Child Health)のリン・チキ教授は、「新型出生前診断は、ダウン症の検出に際してはすべての妊婦にとって従来の非確定診断より優れていることが明白だ。ただし、他の染色体異常のスクリーニングには、臨床応用の前にさらなる検証が必要である」と結論づけています。
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1502441
ルール作りは置き去りのまま
新型出生前診断の市場は36億ドルに拡大
米国では現在、低リスクの35歳未満の女性に対する新型出生前診断について、3つの学会(米国産婦人科学会、米母体胎児医学会、国際出生前診断学会)が推奨しない立場をとっていますが、新型出生前診断は将来的に、定期検査になるという見方もあります。実際、ボストングローブによると、2011年以降米国では45万〜80万件の新型出生前診断が行われ、2019年には世界で36億ドルの市場になることが予想されています。
http://www.bostonglobe.com/metro/2014/12/14/oversold-and-unregulated-flawed-prenatal-tests-leading-abortions-healthy-fetuses/aKFAOCP5N0Kr8S1HirL7EN/story.html
ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンで議論されているように、疑陽性の問題点が解決されないまま新型出生前診断の適応が低リスクの女性まで拡大すると、妊婦の不必要な不安や恐怖などの感情をあおったり、健康な胎児の中絶が増える可能性があります。また、新型出生前診断の適応疾患が拡大する可能性もあり、胎児が疾患や障害をもっているために中絶を選択するという倫理的問題も生じるでしょう。今後ますます個人が選択や決断を迫られることはもちろんですが、それに委ねるだけでなく社会としてのルール作りといった対応も必要となってくるでしょう。