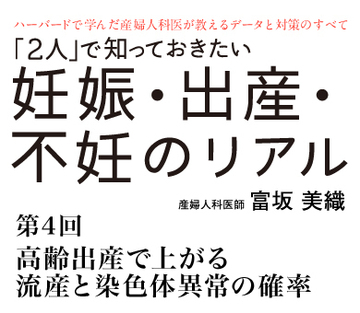高齢出産が増えるなか、技術の進展もあって、遺伝学的検査のひとつである「新型出生前診断」のニーズは高まっています。受診率も高まっていますが、その精度はどの程度信じられるものなのでしょうか。仮に陽性判定が出ても、その後の確定診断が必須であり、確定診断で悪い結果が覆されたとしても妊婦は不安な気持ちを払拭することはできません。今回は同検査を巡る最新の議論を取り上げます。
「新型出生前診断」(=母体血胎児染色体検査、Noninvasive prenatal genetic testing:NIPT)は、母体の血液中に、胎盤を通過して循環する赤ちゃんの無細胞DNAの断片を分析して、赤ちゃんの染色体を調べる遺伝学的検査です。日本では、2013年4月に保険適用外の検査として始まりました。現在の対象は21トリソミー症候群(ダウン症候群)、18トリソミー症候群、そして13トリソミー症候群の3つの染色体の数的異常症のみです。
日本のNIPTコンソーシアムの調査によると、開始後2014年3月末までの1年間で、7740人の女性が新型出生前診断を利用し、1.8%にあたる142人が陽性と判定されました。
http://www.nipt.jp/nipt_04.html
新型出生前診断は“診断”と名称についていますが、確定診断をつける検査ではなく、従来あった胎児超音波スクリーニング検査や母体血清マーカー検査と同じ、リスクを推定するスクリーニング検査ーーつまり非確定検査にすぎません。検査の結果が陽性であっても、実際の染色体の数の異常を検出するために、羊水検査や絨毛検査の確定検査による診断が必須です。
それでも、なぜこれほどまでに新型出生前診断が普及したのでしょうか。
それは羊水検査・絨毛検査のように穿刺操作が必要なく母体血で検査できて母体への負担が軽く流産率が0%だからです。確定検査のための羊水検査では0.3%、絨毛検査では1%と低いながらも流産の可能性があります。
また、新型出生前診断は陰性的中率(陰性と判断された場合、実際に染色体異常がない確率)を示す精度が大変高いのが特徴です。つまり陰性と判断されたら、羊水検査などの確定的診断をしない、という選択ができます。
新型出生前診断が陽性のため、確定検査を受けた女性のうち117人が真の陽性であり、残りの13人には異常は認められませんでした(=疑陽性)。詳細は、21トリソミー症候群が、新型出生前診断で陽性と判定された71人のうち、3人は疑陽性(陽性的中率95.9%:陽性と判断された場合、実際に染色体異常がある確率)、18トリソミーが陽性と判定された36人のうち8人は疑陽性(陽性的中率81.8%)、13トリソミーが陽性と判定された10人のうち2人は疑陽性(陽性的中率83.3%)でした。
一方、新型出生前診断で陰性と判定された1人の妊婦に18トリソミー症候群が陽性(陰性的中率0.1%)と確定しました。この新型出生前診断で陽性とされて、羊水検査で染色体疾患と確定した117人中110人が、中絶を選択したことが話題になりました。
現在米国では、この「疑陽性」の問題が、専門家やメディアなどで大きな議論を呼んでいます。2015年4月1日、世界で最も権威のある医学誌のひとつ「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン(The New England Journal of Medicine:NEJM)」のオンライン版に、同時に3つの新型出生前診断に関する報告が掲載され議論を呼びました。NEJMの報告は、世界中の医療従事者に注目され、将来の医療政策の決定などに大きな影響を及ぼします。