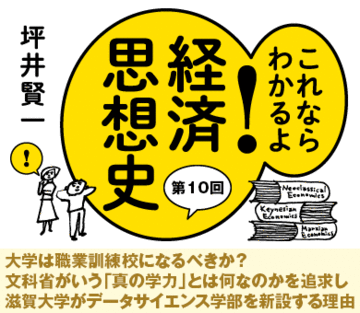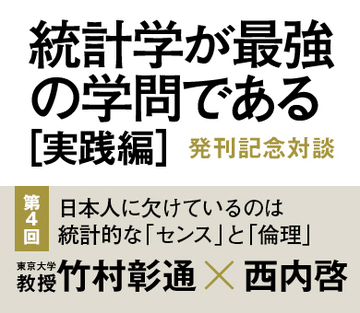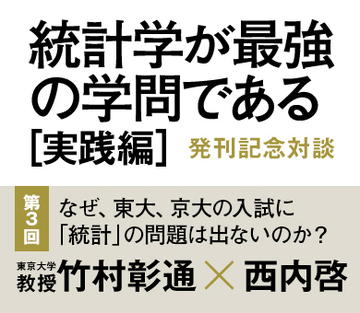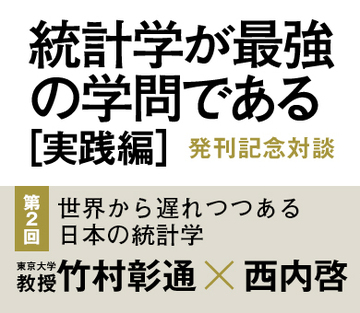統計学といえば日本では長らく、経済学部や工学部の一部(学科ですらない!)という位置づけにありました。しかし遂に日本で初めて、独立した“統計学部”が登場します。その名も「データサイエンス学部」。前回の滋賀大学長の佐和隆光先生と『これならわかるよ!経済思想史』著者・坪井賢一(ダイヤモンド社取締役)の対談でも話題にのぼりましたが、滋賀大学に2017年度から設置予定です。同学部設立に向けてデータサイエンス教育研究推進室室長として陣頭指揮をとる竹村彰通教授(現在、東京大学大学院情報理工学系研究科と両学に在籍)に、統計学の面白さや従来の統計学教育の問題点、新学部における教育内容のほか目指す人材像などについて聞きました(敬称略)。
−−−−「データサイエンス学部」のお話に入る前に、まず統計学とはどんな学問か、改めて伺えますか。
竹村 ひと言でいうと、「データを分析するツール」です。データというのは数字であることが多いのですが、それを解析して情報を取り出し意思決定までつなげるために必要な理念や手法を学んでいきます。
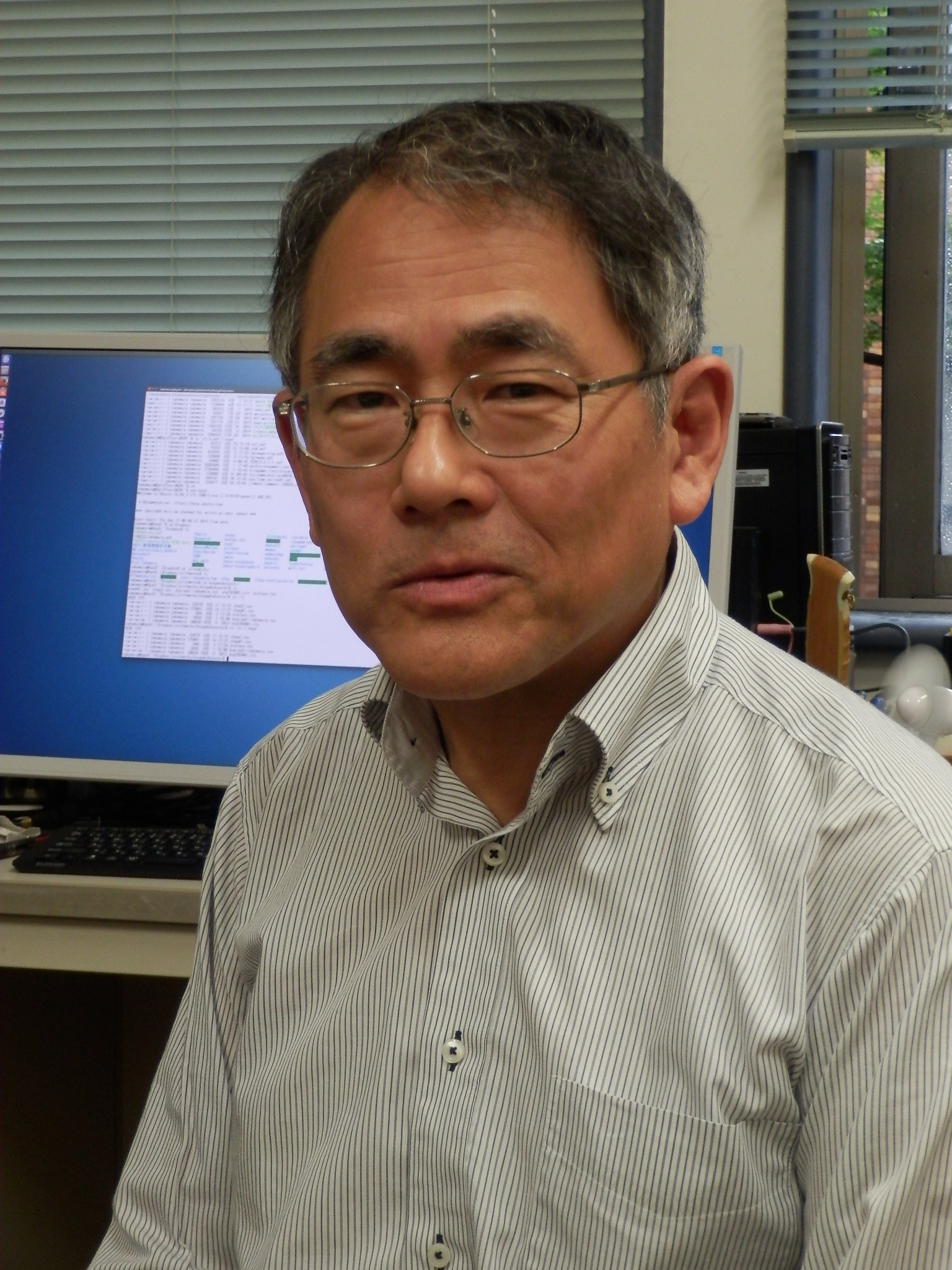 竹村彰通(たけむら・あきみち)プロフィル 1976年東京大学経済学部経済学科卒業。1982年に米国スタンフォード大学統計学科 Ph.D.米国スタンフォード大学統計学科客員助教授、米国パーデュー大学統計学科客員助教授を経て、1984年東京大学経済学部助教授に就任。1997年より東京大学大学院経済学研究科教授、2001年より東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻教授。2015年より滋賀大学データサイエンス教育研究推進室室長兼務。2011年1月~2013年6月には日本統計学会会長を務めた。主な著書に『多変量推測統計の基礎』『統計 共立講座21世紀の数学(14)』(ともに共立出版)がある。
竹村彰通(たけむら・あきみち)プロフィル 1976年東京大学経済学部経済学科卒業。1982年に米国スタンフォード大学統計学科 Ph.D.米国スタンフォード大学統計学科客員助教授、米国パーデュー大学統計学科客員助教授を経て、1984年東京大学経済学部助教授に就任。1997年より東京大学大学院経済学研究科教授、2001年より東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻教授。2015年より滋賀大学データサイエンス教育研究推進室室長兼務。2011年1月~2013年6月には日本統計学会会長を務めた。主な著書に『多変量推測統計の基礎』『統計 共立講座21世紀の数学(14)』(ともに共立出版)がある。
個人の生活で統計を活用する事例としては、たとえば体重の推移を記録して客観視できるデータをとり、生活改善に向けた方策を検討して、食べる量を減らしたり運動量を増やして健康体を取り戻す、といったことがありますね。こういうデータに基づいて対策を打つ一連の作業は大きな組織ほど重要になってきますが、1番大事なのは国家です。いくら税金がとれるか、どのぐらいの軍隊を維持できるか、といった国の力をさまざま測る社会的な背景をもって統計学というのは発展してきました。「統計学」という英語「statistics」の語源が「国家」を表すというのも、お聞きになったことがあるのではないでしょうか。
−−−−近年は「ビッグデータ」時代と呼ばれ、民間企業でもデータ活用の重要性に対して一層注目が高まっています。
竹村 取れるデータ量は少し前から着実に増えていましたから、急に「ビッグデータ」現象が起きたわけではありません。データの重要性が増したのと同時にこれを分析するスキルも重視されるようになる中、日本ではその対応が遅れている印象があるので、注目が集まるのは良いことだと思います。
また、「ビッグデータ」という言葉が流行った影響から、学生たちのあいだでも統計学に対する関心が急激に高まってきたのは嬉しいですね。純粋に統計学をやりたいというより、ウェブサービスで使われている機械学習についての知識を深めるために統計学を学びたいというのが実際の動機に近いかもしれませんが、データ解析そのものに興味をもつ若者が増えるのは喜ばしいことです。
−−−−データやその分析の重要性が増すなか、統計学の実力差でいうと日本がアメリカに大きく水をあけられていることに竹村先生は危機感をお持ちだと伺いました。
竹村 圧倒的な差があります。人口比でいうとアメリカは日本の2.5倍ぐらいですが、統計の力の差でいうと感覚的には20倍ほどでしょうか。控えめに言っても10倍の差はあるでしょう。たとえば毎年9月に開催される日本の統計関連学会総会の参加者は800人(会員数1500人)程度なのに比べて、アメリカ統計学会には1万人近い人(会員数1万8000人)が集まりますから、単純計算で10倍以上です。
それに企業内のデータ・サイエンティストでいえば、アメリカでは統計を学んできた専門家がいるのに対し、日本企業だと内製化されていて、その会社の中で数字に強そうな“できそうな人”に勉強させて育てるといったレベルで長らく対応してきたと思います。1980年代あたりまでは、この仕組みで特に品質管理の面など成果も上がったと思うのですが、データ量が圧倒的に増えてその解析・活用の専門性が不可欠になった今では、もっと数学も統計も専門に勉強した人でないと太刀打ちできない状況になっています。たとえば製造業におけるイノベーションをもっと起こすには、そうした人材が不可欠ではないでしょうか。