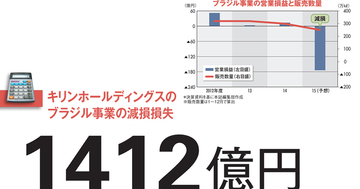銀行の自己資本をめぐる国際的な議論が最終局面を迎えている。合意内容に基づいて試算すると、メガバンクの自己資本は欧米勢と肩を並べそうだ。だが、収益力は劣勢に立たされている。
7月16日、各国の銀行監督者たちはスイスのバーゼルで、自国金融の浮沈をかけた金融戦争さながらの熱い攻防を繰り広げていた。
主要国の銀行監督当局でつくるバーゼル銀行監督委員会が開いた中央銀行・銀行監督当局首脳会議。日本からは日本銀行の白川方明総裁と、金融庁の三國谷勝範長官が出席し、徹夜もいとわず一歩も引かない交渉を展開していた。
そもそも、議論がスタートしたのは昨年春のこと。2008年に発生した世界的な金融危機の再発を防ごうと、銀行の自己資本をこれまでよりさらに厚めに積ませることで合意。これまであった自己資本比率に関する規制、いわゆるバーゼル2を強化したバーゼル3を定めるべく、各国の当局間で議論を重ねてきた。
その過程で浮上したのが、「狭義の中核的自己資本(コアTier1)」。昨年12月には、コアTier1を業績悪化時に配当が止められる普通株と内部留保に限定、貸出金などのリスクアセットで除したコアTier1比率を一定割合積ませる方針が打ち出された。
しかし、この定義をめぐって日本は猛反発。もともと自己資本比率が高く、しかも普通株が中心の英米に有利で公平性を欠くというのが理由だ。当初、孤立していた日本当局は、途中からギリシャ危機の影響をモロに受けていたドイツやフランスなどと手を組み、一気に巻き返しに打って出る。
途中、米当局が、交渉の場に姿を見せないといった強硬手段まで取って自国に有利な規制を導入しようと画策するが粘り強く説得。結果、コアTier1の範囲の拡大に成功して合意にこぎ着けた。
今回の合意で邦銀に有利に働く点は大きくいって二つ。一つは、将来の税金の払い戻しを見込んで資産に計上している「繰り延べ税金資産(繰り税)」。このうち、普通株の10%相当分まで算入が認められ、繰り税の割合が大きい邦銀にとっては、コアTier1比率を1%程度押し上げる効果があると見られている。