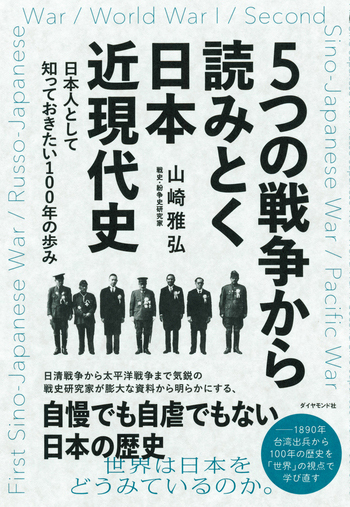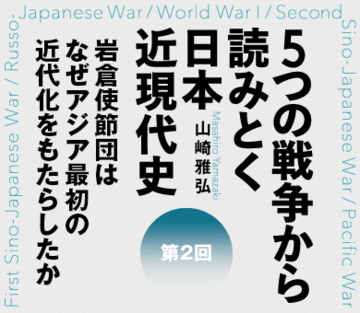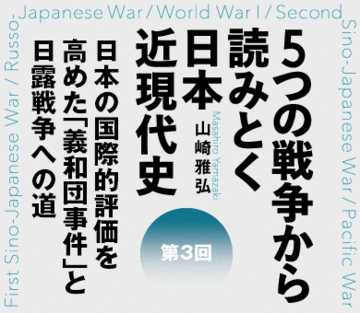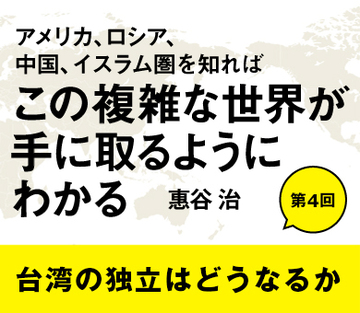近刊『日本会議 戦前回帰への情念』(集英社新書)が発売4日でたちまち重版・4万5000部突破の気鋭の戦史・紛争史研究の山崎雅弘による新連載です。日本の近現代史を世界からの視点を交えつつ「自慢」でも「自虐」でもない歴史として見つめ直します。『5つの戦争から読みとく日本近現代史』からそのエッセンスを紹介しています。第4回は親日国として知られる台湾における日本統治時代の実相を解説します。

日本統治時代の銅像が
破壊されずに今なお残る台湾
現在の台湾は、東アジアでも特に日本人や日本文化に対して好意的であるため、日本の一部には、台湾の人々が日本による統治の開始から一貫して「親日的」であったかのような認識を語る人も存在しています。
同じ日本の植民地であった朝鮮(韓国)とは異なり、現在の台湾には日本統治時代に功績のあった日本人を顕彰する銅像や記念碑などが多く存在しており、約50年にわたる日本統治時代を全否定するような歴史解釈は見られません。
例えば、疫病が蔓延していた台湾の衛生面を改善して伝染病の撲滅などに貢献した医学者の堀内次雄、台湾南部で大規模なダムと水路を組み合わせて広大な平野を一大穀倉地に作り替えた土木技師の八田與一、品種改良を重ねて台湾の気候に合った「蓬萊米(ほうらいまい)」を生みだした農学者の磯永吉と農業技師の末永仁、台湾中心部の日月潭(じつげつたん)という湖に巨大な水力発電所を建設して島内の工業化を支えた実業家の松木幹一郎などの日本人が、現在の台湾でも「台湾の発展に寄与した功労者」として称えられています。
フランスへの売却をとめた後藤新平の統治施策
日本統治下における台湾での教育行政も、朝鮮と同様に「日本人の優位確保」と「現地住民の日本的慣習への同化」に重点が置かれましたが、朝鮮の場合と違っていたのは、日本人と台湾人(漢人)に加えて、主に山岳で暮らす原住民が、異なる文化を守りながら暮らしていたことでした。
そのため、日本統治時代の台湾には、日本人、台湾人、原住民の三種類の学校があり、日本人学校は設備も教員の質も高くされていました。一方、伝統的な固有文化を重んじる原住民の教育施設には、監視の意図も含めて日本の警察が関わることもありました。
樺山資紀の後を継いだ、第2代総督の桂太郎と第3代総督の乃木希典は、共に陸軍大将で、武力による支配を基本的な方針としていたため、台湾の民衆の心をなかなか掴めずにいました。台湾の統治が日本政府の思い通りに行かないことに業を煮やした国会では、台湾をフランスに売却してはどうかという意見も出始めました。
しかし1898年2月に第4代台湾総督として児玉源太郎が就任し、本国の政務に多忙だった彼の実質的な代理として民政局長(のち民政長官)の後藤新平が実務を取り仕切るようになると、次第に台湾の情勢も安定していきました。
軍人ではなく、医師から衛生行政に転じた経歴を持つ後藤は、日本や西洋の生活水準をいきなり台湾に導入するのではなく、まず綿密な現地調査を行って、台湾の人々が欲しているもの、困っていることなどを把握し、現地の慣習を尊重しながら、さまざまな分野の制度や技術を導入する手法をとりました。
中毒患者が多かったアヘンについても、一律に厳禁する代わりに、中毒者を登録させて購買状況を管理し、重症の患者には副作用の少ない良質のアヘンを販売しながら治療を勧め、軽症になったら吸引を禁止するという「阿片漸禁策」で、中毒患者を減らすことに成功しました。後藤はまた、台湾の治安を脅かす山賊など(当時の日本側呼称で「土匪(どひ)」)に対処するため、各地区ごとに「保甲」と呼ばれる自治組織(民家10戸で1甲、10甲で1保を形成)を創設させ、警備や生活環境の改善、相互の連絡強化などを行わせました。
日本統治時代の「負の歴史」
しかし、台湾の学校や歴史博物館では、日本統治時代にたびたび発生していた「抗日闘争」や「民族運動」の歴史も、動かしがたい事実として教えており、この時期が当時の台湾人にとって「バラ色の時代であった」と全肯定されているわけでもありません。
台湾における抗日闘争は、1895年の「台湾平定」宣言の後も散発的に発生しており、1911年に中国で「辛亥革命」が起こると、それに刺激を受けた漢人系台湾人は、1912年から1915五年にかけて、台湾各地で武装蜂起しました。
その主なものを列挙すると、1912年の林杞埔(りんきほ)事件と土庫(どんご)事件、1914年の太魯閣(タロコ)事件と大湖(だいこ)事件、東勢角(とうせいかく)事件、南投事件、六甲事件、関帝廟事件、1915年の西来庵事件などでした。このうち、最大の武装蜂起は台南で発生した西来庵事件でしたが、10ヵ月にわたる鎮圧作戦で2000人近くが逮捕されて、約100人が処刑されました。
この事件の後、漢人の抗日闘争は下火となりましたが、15年後の1930年には、山岳地帯に住む非漢人の原住民による大規模な抗日闘争が発生します。当時の台中州能高郡霧社(むしゃ)で起きたことから「霧社事件」と呼ばれるこの事件は、日本統治時代に起きた最大の悲劇として、現在の台湾でも語り継がれています。事件の発端は、同年10月7日に発生した、原住民の若者に対する日本人警察官の暴力事件でした。
先に述べた通り、台湾総督府は土地の権利が明確でない土地を国有地として接収する政策をとっていましたが、原住民の社会では伝統的に「個人や法人による土地の権利所有」という概念がなく、集落ごとの共有地のような形で農業や狩猟を行っていたため、総督府によって土地を不当に奪い取られたという恨みの感情が高まっていました。
また、日本側が企画した土地開発などの建設事業に、原住民をなかば強制するような形で従事させたことも、日本に対する敵愾心を高める一因となっていました。そして、日本人警察官の理不尽な暴行という事件によって、原住民の間で鬱積した不満がついに爆発し、10月27日にセデック族などの集落に属する約300人の原住民が、日本の駐在所をあちこちで襲撃した後、霧社公学校で行われていた運動会を襲い、女性や子どもを含む日本人約140人を殺害するという惨事が発生しました。
これに対し、台湾総督府は日本軍と警察、そして日本に協力的な原住民部族などを投入して反乱勢力の掃討作戦を開始しました。日本軍は、大砲と機関銃、爆撃機、催涙ガスなどの近代兵器を容赦なく投入して反乱勢力を追い詰め、12月には抗日蜂起は実質的に粉砕されました。反乱勢力側の死者数は、700人とも1000人とも言われています。
日本統治時代の台湾には、官僚や警察官、商工業者を中心に、大勢の日本人が移住しており、その数は1905年の約6万人から、霧社事件の3年前に当たる1927年には20万人に増加していました。しかし、文化の違いなどに起因する紛糾や摩擦は、台湾でも日本人と現地の住民の間で繰り返し発生しており、日本人が日本統治時代の台湾について語る際には、こうした「負の歴史」にも一定の注意を払う必要があります。