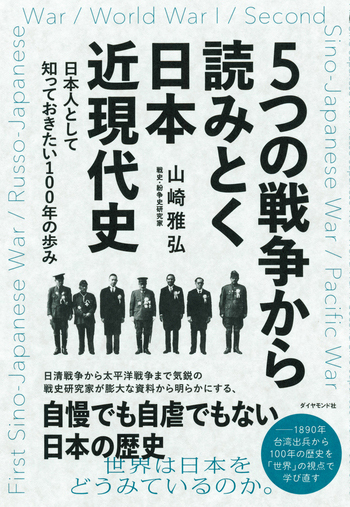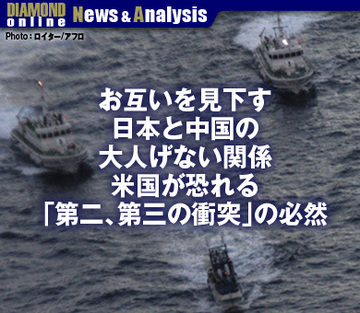近刊『日本会議 戦前回帰への情念』(集英社新書)が発売4日でたちまち重版・4万5千部突破の気鋭の戦史・紛争史研究家の山崎雅弘氏による新連載です。日本の近現代史を世界からの視点を交えつつ「自慢」でも「自虐」でもない歴史として見つめ直します。『5つの戦争から読みとく日本近現代史』からそのエッセンスを紹介しています。第1回は開国から急速に力をつけた日本と清国との戦争の歴史の陰に隠れたゲリラ戦の存在を紹介します。

開国から日本が「帝国主義」へいたる道すじ
1871(明治4)年の「岩倉使節団出発」から、1905(明治38)年の「日露戦争終結」までの35年は、いわば「井の中の蛙」であった日本が近代国家としての第一歩を踏み出し、欧米諸国の実情を目の当たりにして驚きつつ、大国となるために何が必要なのかを必死に学んだ時期でもありました。
世界で通用する国際法というルールを勉強し、自分たちの行動規範を少しずつそれに合わせていくことで、日本という国を発展させるのと共に、日本が外国の植民地にならないようにする「強さ」を身につけていきました。
その過程では、当時の欧米諸国がアジアやアフリカなどの「植民地」に対して行っていた「帝国主義」の流儀を、日本も真似ることになりました。現在もなお政治的な後遺症が残る、韓国(朝鮮)や中国(清国)に対する「大日本帝国」の支配権拡大は、実質的にこの時代から始まったと言えます。
日清戦争は、日本から見た「主観的歴史」では「朝鮮の独立国としての地位を確立して、日本周辺の安全を確保するための、正当な軍事力の行使」でしたが、清国と朝鮮は当然のことながら、それぞれ日本とは異なる認識を持っていました。
清国は、1882(明治15)年に朝鮮との間で「中朝商民水陸貿易章程」という条約を締結し、前文で「朝鮮は清国の属国」と明記しており、朝鮮を「完全に清国の影響下から脱した独立国」と見なす日本側の考え方を認めるつもりは全くありませんでした。
もし、それを認めてしまったなら、今まで朝鮮と同様に清国を「世界の中心」と理解してきた東アジア諸国に対する清国の面子と威信は丸つぶれとなり、清国の支配から脱しようという動きが、あちこちで発生しかねないと思われたからです。
歴史から忘却された「日本軍と朝鮮人ゲリラの戦い」
しかし、日本軍と正面から組み合った戦争で清国軍が完敗を喫したことは、清国にとって想定外の打撃となりました。この敗北により、清国を「東アジアの支配者」と位置づける「華夷秩序」は根底から揺るがされ、イギリスとのアヘン戦争での敗北(1842年)以来低下していた清国の欧米列強への発言力はさらに失墜し、英独など各国は清国の政治的弱体化に乗じる形で、新たな利権を求めて中国大陸へと進出することになります。
一方、戦場となった朝鮮半島では、日本軍と清国軍による戦争が勃発したのに伴い、先の「甲午農民戦争」で立ち上がった武装農民たちが、日本軍部隊を「侵略者」と見なして銃口を向け、ゲリラ戦を展開するという、新たな事態が発生していました。
日本で出版された「日清戦争」の文献では、ほとんど触れずに済まされていますが、日本軍が朝鮮の王宮を武力で占領した上、朝鮮政府を脅して独立宣言を発表させたことに反発した大勢の朝鮮人が、開戦翌月から日本軍に対する抵抗の戦いを開始したのです。
これに対し、現地の日本軍は前線で清国軍と戦いつつ、後方では朝鮮人のゲリラとも戦うことを強いられました。しかし、欧米列強が注視する清国軍との戦いでは、国際法をきちんと遵守して戦う姿勢を見せた日本軍でしたが、貧弱な兵器しか持たない朝鮮人の農民ゲリラに対しては、情け容赦なく徹底的な掃討作戦を実施し、降伏した朝鮮人も「捕虜」とは見なさずに、見せしめの効果を狙って住民の目の前で殺したりしました。
こうした日本軍の朝鮮人抗日ゲリラに対する行動は、後のベトナム戦争におけるアメリカ軍の行動とよく似ていました。農民ゲリラは、彼らに好意的な農村の住民にまぎれて行動するため、ゲリラの掃討を行う軍隊は、住民がゲリラを助けたり匿ったりしないよう、武器で脅して恐怖心を植え付けるなどの強圧的な方策をひんぱんに使用しました。
日清戦争当時の日本軍が、抗日ゲリラの掃討で用いた非人道的な手法は、当時戦いに参加した日本軍人の日記や手紙にも生々しく記されています。しかし、抗日ゲリラ掃討作戦の実情は、日本の陸軍参謀本部が編纂した戦史書では実質的に無視され、作戦で死亡した兵士についても「清国軍との戦いで戦死」という形式に記録が書き替えられました。