リクルートホールディングス
関連ニュース
第7回
リクルートに挑むビズリーチの勝算、人材ビジネス儲けのカラクリ
ダイヤモンド編集部
人材ビジネス業界は過去最高益を更新する企業が続出するなど活況を呈している。だが、旧来のビジネスモデルを破壊する可能性を秘めるテック企業が急成長するなど、大手も安穏としてはいられない状況だ。

第4回
人事のプロや経営者が絶賛!評価・給料を決める最先端の「科学的手法」
ダイヤモンド編集部
人事の領域に科学的手法を取り入れる最先端人事部が激増している。評価・給料の決め手が公平で客観的なものになればなるほど、働き手にも「生産性アップ」という覚悟を強いることになる。
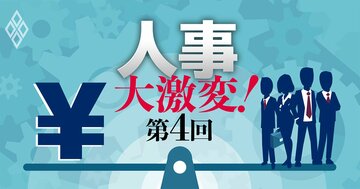
予告編
人事部が採用難と働き方改革で機能不全、あなたの評価・給料が危ない
ダイヤモンド編集部
かつての社内エリート集団、人事部がピンチに立たされている。欲しい人材の採用難と働き方改革関連法への対応のダブルパンチに見舞われ、戦略人事を遂行できなくなっているのだ。人事部の機能不全は、われわれ働き手である社員の評価・給料にもダイレクトに負の影響をもたらしてしまう。企業人事部と全ての働き手に緊張感がみなぎる人事大激変の現場を実例満載でレポートする。
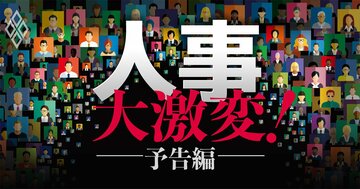
世界の急成長企業と『サザエさん』の三平さんに共通する精神
flier
聞き慣れない言葉「カスタマーサクセス」。そしてそれは「日本企業にこそ必要」であるそうだ。これはどういったことか?
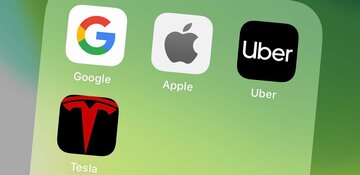
リクナビ内定辞退率問題で厚労省激怒、「データ購入企業」にも鉄拳
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
労働者保護を原則とする厚生労働省が、怒り狂っている。就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリアが就活学生の内定辞退率予測データを大企業に販売していた問題についてだ。厚労省の怒りの矛先は、個人情報のデータを販売したリクルートキャリアのみならず、購入したビッグカンパニーへも向いている。

内定辞退率問題だけではない!「リクナビショック」で人材業界全体が震え上がる理由
ダイヤモンド編集部,相馬留美
「リクナビ」を利用した内定辞退率データを企業に販売していた問題が、人材業界全体を震え上がらせている。個人情報保護の観点だけではなく、人材データの利活用のあり方そのものが問われている。
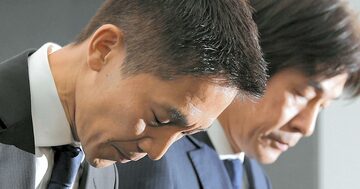
副業解禁ムードのなか、あえて問い直すリスクと「本業でやれること」
石原直子
副業への関心が高まっており、実際に副業をする人も増えている。安倍政権が副業・兼業を後押しする姿勢を見せており、企業のなかにも副業解禁をうたうところが出てきている。しかし、副業解禁にはいくつかの落とし穴がある。実際に副業をしている人や、副業をしたい人による副業の理由が、所得を増やしたいという切実なものであり、過重労働や健康被害のリスクもある。雇用者は副業をする前に、自分の本業で自分に給与を支払ってくれる企業のなかで、自分がすべきこと、できることを本当にやり尽くしているのかを点検する必要がある。

リクナビの「内定辞退率予測」問題から考える個人データ利用の未来
山崎 元
就職情報サイト「リクナビ」を運営するリクルートキャリアに対して、就職活動に臨む学生の同意を得ずに「内定辞退率」の予測を企業に販売していた問題で、政府の個人情報保護委員会は8月26日に是正を求める勧告を出した。同委員会が勧告を出すのはこれが初めてだ。

第8回
リクナビの「内定辞退率」データ提供は何が問題だったのか、弁護士が解説
BUSINESS LAWYERS
8月1日、就職情報サイト「リクナビ」を運営する株式会社リクルートキャリア(以下、リクルートキャリア)は、同社が提供していた「リクナビDMPフォロー」サービスにおいて、いわゆる「内定辞退率」データをクライアントである採用企業に提供していたことを公表。その際、ユーザーである学生の個人データの扱いや同意の取得方法等が適切だったかが問われています。

第18回
「何だ、その会社は」と思ったIndeedとリクルートが恋に落ちたワケ
ダイヤモンド編集部,相馬留美
今や、リクルートホールディングスの売上高の約46%が海外事業だ。世界に打って出た同社の次の一手とは。峰岸真澄・リクルートホールディングス代表取締役社長兼CEOに聞いた。

第17回
リクルートが「ただのテックカンパニー」と一線を画する理由
ダイヤモンド編集部,相馬留美
2019年3月期決算では過去最高の売上高を叩き出したリクルート。就任時から「リクルートをITカンパニーに変える」と豪語してきた、峰岸真澄・リクルートホールディングス代表取締役社長兼CEOは、今何を語るのか。

第12回
医学生、小説家、起業家… やりたいことをやってきた でも、人生の大半は苦しかった/石井大地・グラファー創業者・CEO
ダイヤモンド編集部,深澤 献
人と違うことをやる、リスクを取ってでも新しい道を行く──。イノベーターとして活躍する若きリーダーたちは、どんな原体験に支えられ、どう育ってきて、そのたくましさを得たのか。今回は、東京大学医学部から文学部に転じ、小説家として文藝賞を受賞、その後、プログラミングや事業開発に携わり、行政手続きのIT化で起業した石井大地さんです。

リクルート幹部が断言「買収したインディードとはビジネスの棲み分けができる」
ダイヤモンド編集部,千本木啓文
週刊ダイヤモンド2019年5月11日号は「人事大激変! あなたの評価・給料が危ない」です。人工知能(AI)などを駆使した企業が人材ビジネス業に参入し、業界秩序を変えようとしています。迎え撃つ業界最大手、リクルートの小林大三常務に今後の展望などを聞きました。

「トイレの混雑」を改善したリクルートの超アナログな方法
相馬留美
「エレベーター渋滞」「会議室不足」という積年の課題に、アナログな方法を駆使して挑んできた株式会社リクルートの佐野敦司・総務統括室室長と総務チーム。そんな彼らが満を持して取り組んだのが「トイレの混雑」の解消だった。

人事のプロや経営者が絶賛、最先端の「科学的人事手法」とは
ダイヤモンド編集部
人事の領域に科学的手法を取り入れる最先端人事部が激増している。評価・給料の決め手が公平で客観的なものになればなるほど、働き手にも「生産性アップ」という覚悟を強いることになる。

第5回
リクルートの人事、その本当のすごさは「人件費の調整能力」にあった
青田 努
「売り手市場」のいま、採用に強い会社は何をしているのか? その実態を採用のプロが解説。

「会議室不足」を改善したリクルートのアナログな方法
相馬留美
会議室がいつも満室で、なかなか予約が取れない。こんな社員の不満も多かったリクルート。そこで、同社の総務部が解消しようと立ち上がった。まず行ったのが、利用実態の把握だ。しかしその方法は、ちょっとデジタルで、アナログなものだった。

新入社員は短期間で劣化する 日本人の「仕事への熱意」は世界最低レベル
AERAdot.
新しい年度がスタートし、新入社員の初々しい姿が街にあふれるこの季節、桜の花色に誘われるように初心を思い出し、新たな目標を立てた人も多いだろう。

「エレベーター渋滞」を改善したリクルートの超アナログな方法
相馬留美
高層ビルのエレベーターの待ち時間は、とかくやきもきするもの。そんな不満を解消したいと立ち上がった企業がリクルートだ。リクルートの総務は、エレベーター渋滞を解消するため、実験を実施。実にアナログな方法で渋滞を改善させたという。

「ポイント投資バトル」が勃発!加速するプレーヤーの参入
松崎のり子
共通ポイント界で昨今ブームになっているのがポイント投資だ。貯まったポイントをそのまま使うのではなく、投資信託や株式投資などでバーチャル的に運用してもらおうという動きが広がりつつある。その実態についてお伝えしよう。
