学閥としての
パブリック・スクール
日本の学閥は出身大学で分けられる場合が多いですが、イギリスではパブリック・スクールごとの学閥、特にザ・ナイン(編集部注/世界的に有名なパブリック・スクール9校の総称。ウィンチェスター校、イートン校、セントポールズ校、シュルズベリー校、ウェストミンスター校、マーチャント・テイラーズ校、ラグビー校、ハロウ校、チャーターハウス校)の学閥が強いようです。
独特の言い回しによって、どのパブリック・スクール出身かが分かる仕組みにもなっています。例えば、イートン校では、冬はフットボール(サッカーのこと)、夏はクリケットをする芝生のフィールドをメソポタミア(Mesopotamia)なんて呼んでいます。また、アブラカダブラ(Abracadabra)とはイートン校の基本的な時間割のこと。生徒手帳(Fixtures)に載っています(図表1-10)。
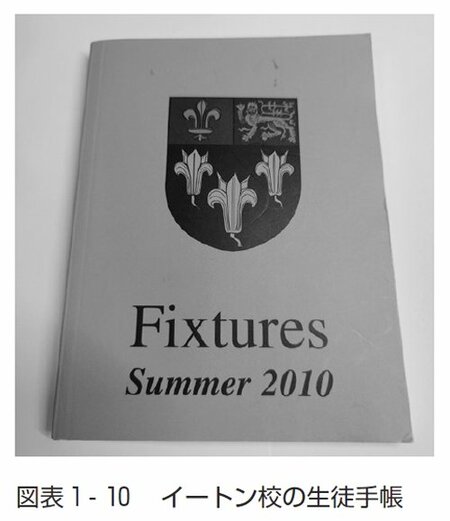 同書より転載
同書より転載
ちなみに、この言葉の正確な語源については、専門家の間でも意見が分かれているようですが、古い言葉だそうです。悪霊を追い払う「魔除け」の言葉であったり、魔法をかける時の呪文であったり、また「ちんぷんかんぷん」という意味もあります。
他方、ラグビー校では「おい、朝礼でボジャー(bodger)が10時にバグ(bug)に集まれって言ってたぞ!」と叫んだ場合、それは、「おい、朝礼で校長が10時に図書館に集まれって言ってたぞ!」という内容になります。
辞書によると、本来「bodger」とは「昔ながらに森に住み、伐採した木から椅子を作る人(Collins English Dictionary)」、「bug」は「虫、プログラミングの欠陥(バグ)、バイ菌」という意味です。かなり違った意味になっていますよね。先生のことも、ハロウ校では「ビークス(beaks)」と呼んでいます。
「ハリー・ポッター」でも、グリフィンドールの生徒のためのコモンルーム(生徒のための休憩室、社交室)に入る時の合言葉「カプート・ドラコニス(ドラゴンの頭:0 caput draconis)」がありましたよね。



