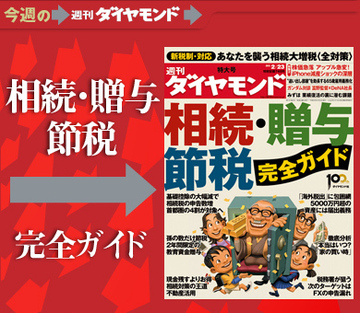財政・税制(8) サブカテゴリ
第6回
株価が大きく変動している。今回は、本連載の第4回「円安は企業利益をどう変化させるか――シミュレーションモデルによる分析」に示したモデルを用いて、現実の株価の評価を試みることとしよう。
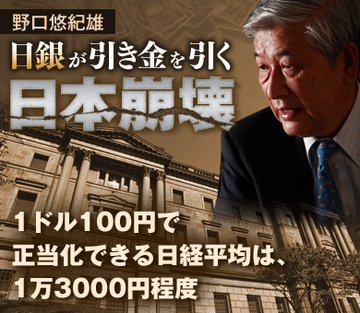
第50回
異次元金融緩和に潜むリスクがジワリと顕在化しつつある。リスクを大きくしないためには、「出口戦略」が重要だ。その中核をなすのは、政府の財政再建に向けてのコミットメントである。このことの認識を政府がしっかり持つことがリスク軽減に役立つ。
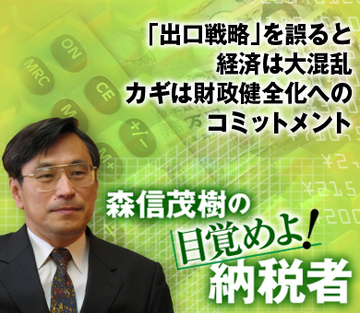
第7回
財政健全化を推し進めるには、社会保障給付費の抑制は最重要課題だ。抑制策の筆頭が「後発医薬品の使用促進」。だが、果たして医療費のうち薬剤費はどのくらいを占めるのか、政府統計や資料のどこを探しても適当なものが見当たらない。
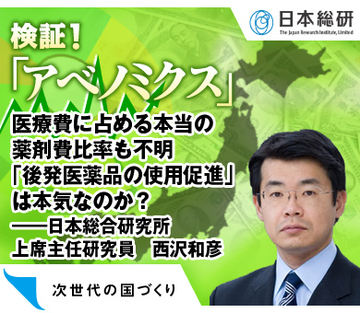
第85回
2014年1月1日より、NISA(ニーサ)と呼ばれる個人投資家向けの少額投資非課税制度が始まる。少子高齢化時代における資産形成は、そもそもどのように考えればいいのだろうか。NISAの導入を契機に、今回は、この問題を考えてみたい。
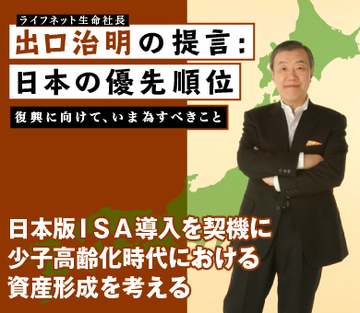
第5回
1-3月期実質GDP(国内総生産)は、対前期比年率で3.5%の増加となった。これをアベノミクスの効果と見る向きが多いだろう。しかし、詳細に見ると、そうとは言えない面が多いのである。
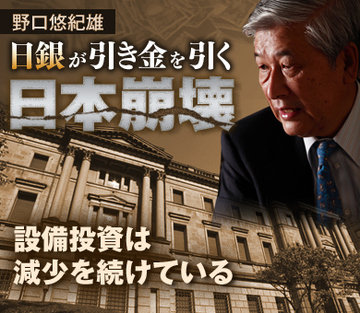
第6回
低金利状態が長期化している現在、「財政運営のリスク」は表面化していない。だが、財政の持続可能性を市場から疑われ、市場金利が一度上昇を始めたらどうなるのか。欧州危機の経験をたどりながらみてみよう。

第4回
上場企業の決算発表が続いている。これに対して、「円安によって企業が大幅増益」というトーンの報道が多い。株価上昇を支えているのも、そうした見方であろう。企業の利益増加は、本当に円安だけによって生じているのだろうか?そして、今後はどうなるのだろうか?
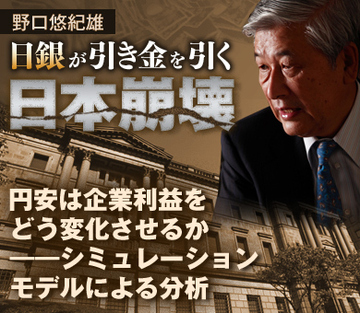
第3回
安倍内閣の経済政策が本当に内容のあるものか、それとも見かけ倒しのこけおどしのものかという判断は、成長戦略によってなされることになる。今回は、「成長戦略で何が必要か?どのように評価するか?」という問題を考えよう。
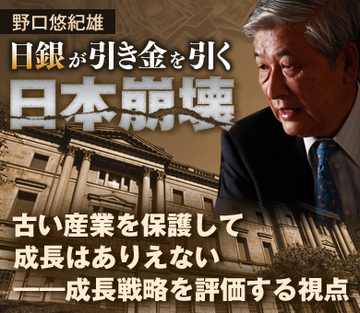
第4回
安倍政権は、中長期的な財政再建策の具体化には、未着手の状態にある。日本総研の試算では、名目3%という高成長でも、2020年度で財政赤字は50兆円にも達する。この深刻な問題から「逃げた」財政政策運営で済ませることは、もはや許されない。

第48回
消費税率の引き上げを1年後に控え、政府は様々な規制を検討している。買いたたきや転嫁拒否行為の禁止は当然だかが、価格表示まで規制するのは、事業者の創意工夫を抑制し、消費者利益を損なうことになりかねない。
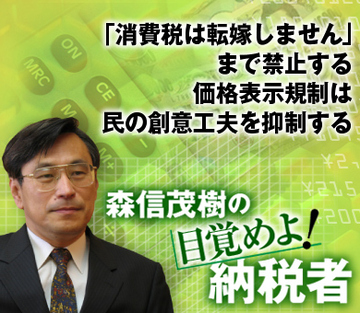
第2回
日本銀行の「次元の異なる量的・質的金融緩和政策」に対して株式市場や為替市場では、緩和策を効能書きどおりに受け取って、株高と円安が進んだ。しかし、プロの市場である国債市場では、国債利回りの乱高下が生じた。
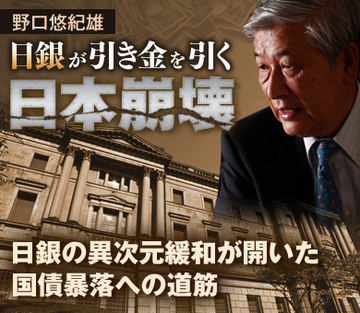
第47回
英国のキャメロン首相は、スタバ英国法人支払う法人税額が少ないことに激怒した。だが、こうした多国籍企業の租税回避措置はいまのところ合法。税収不足悩む先進国政府は今夏のサミットでこの問題を取り上げる。
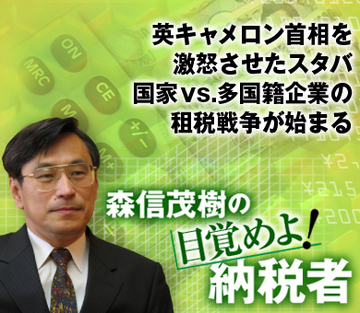
第32回
EUの小国で地中海に浮かぶ島国・キプロスで、銀行封鎖・預金課税という荒療治が始まった。直接の原因はキプロスの銀行がギリシャ国債を大量に買い込み、大穴をあけたためだ。この危機は果たして他人事なのだろうか。
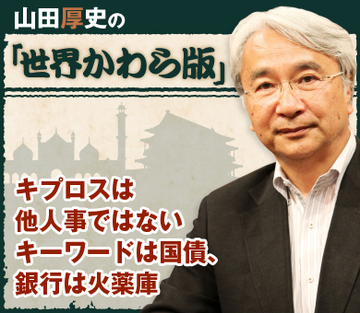
第107回
地方自治体の行財政改革を図るため、国が推し進めた「平成の大合併」から今年で14年が経過。合併に伴う特例の期限切れが迫り、合併した自治体を悩ませる。さらに、合併によって膨れ上がった公共施設の老朽化問題も襲いかかる。思わぬダブルパンチに右往左往する自治体の現状に迫った。

第46回
この4月から導入される予定の「教育資金贈与税非課税措置」が盛り上がっている。金融機関はビジネスチャンスをうかがう一方、教育費の定義や、どうしたらきちんと徴収できるかを決めておかないと、混乱は必至だ。
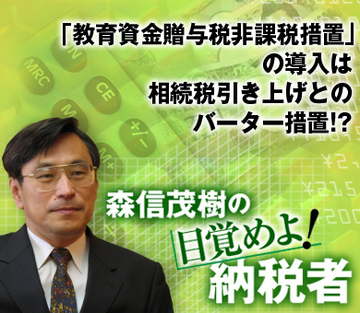
第45回
私は旧大蔵省時代に「焼酎・ウイスキー税制格差問題」で、WTOおよび日米交渉を経験した。そこで痛感したことは貿易交渉は法律論議ということ。だからTPP交渉にあたっては、優秀な渉外弁護士の全面的な支援を求めるべきだ。
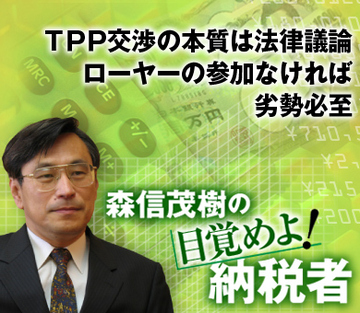
第782回
2月15日から2日間にわたってモスクワで開かれた主要20カ国・地域財務相・中央銀行総裁会議(G20)は、「競争的な通貨安を回避する」との声明を採択して幕を閉じた。ここ2年ほど、G20のテーマは専ら欧州債務問題が中心だったが、今回は「通貨安競争」。背景には、昨今の急激な円安がある。
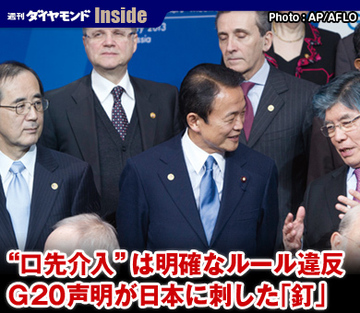
第76回
モスクワで開かれていたG20は、2月16日夜に共同声明を採択して閉幕した。各紙は軒並み一面のトップで報じたが、日経新聞の見出しによれば、「アベノミクス薄氷の支持」という結果となったようだ。ところで、G20は何故、これほどまでに注目されるのだろうか。
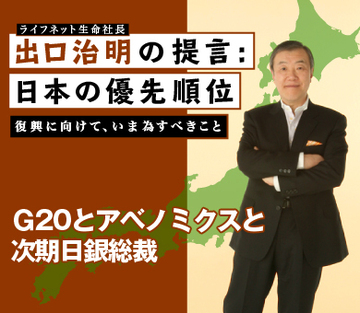
第44回
今回の税制改正議論で最後までもめた案件に、消費税の軽減税率導入がある。もし軽減税率を導入するなら、インボイス制度は絶対に欠かせない。その理由を述べてみよう。
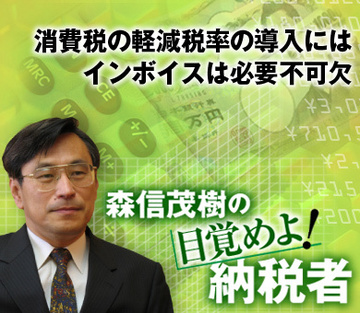
13/02/23号
来年から消費税が増税される。単純計算で14年4月以降は6兆円、15年10月以降は、約10兆円の増税が待ち構えている。2013年度税制改正で与党が減税と強調する2700億円より、はるかに大きな数字だ。減税の先には、大増税時代が待っている。