後藤順一郎
第101回
昨年夏に、「老後2000万円問題」がメディアで炎上したのは記憶に新しいのではないでしょうか。この炎上では「2000万円」という金額のみが一人歩きしてしまった感がありますが、結果的には多くの日本人が老後の生活資金について関心を持つことになったと言う点では、意味があったと思います。

第100回
今回の寄稿で当連載もめでたく100回を迎えることになりました。月に1回の連載ですので、期間で見ると8年4カ月ということになります。我ながら長く続いたものだなぁと思いながら第1回を確認してみると、「PPK(ピンピンコロリ)」を題材にして連載を開始していました。PPKは亡くなる直前まで元気なことを意味しており、その回ではPPKの人が多く「ぴんころ地蔵」まで建立した長野県佐久市を例に紹介していました。

第99回
毎年、年末になると公表される税制改正大綱の中で、厚生労働省からは確定拠出年金(以下、DC)の加入要件の変更等の案が、そして金融庁からは少額投資非課税制度(以下、NISA)の仕組みを少し変更し積み立て重視とする案が発表されました。

第98回
年が明けて心機一転、何か新しいことを始めようという人は多いと思います。特にオヤジ世代の皆さんの中には、自分のキャリアや人生設計を見つめ直した人もいるでしょう。中でも、少し先の人生に思いをめぐらせ、老後資金を形成しなくては、と決意した人も多いのではないでしょうか。

第97回
前回、日本人の寿命がさらに延び、男性の平均寿命が81.25年(平成29年は81.09年)、女性の平均寿命が87.32年(平成29年は87.26年)になったとお伝えしましたが、長寿化は何も日本のみで起こっているわけではなく、他の国でも起こっています。

第96回
2019年7月に平成30年の簡易生命表が公表されました。もはや毎年恒例といっても過言ではありませんが、今回も男女ともに平均寿命を伸ばして最高値を更新しました。

第95回
前回のコラムでは、2019年8月下旬に公表された公的年金の財政検証結果を受け、全体として所得代替率が将来どうなるのか、「100年安心」の年金として設計されたときの公約である50%の所得代替率を引き続き達成できる状況になっているのかを確認しました。今回は全体論ではなく、世代ごとに年金額がどうなるのかを見ていくことにします。
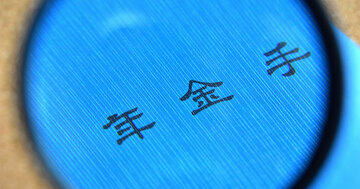
第94回
2019年8月27日にようやく公的年金の財政検証結果が公表されました。前回、2014年に実施した際には6月上旬に提示されたのですが、「老後2000万円」問題の影響もあってか、3カ月程度遅れての公表となりました。

第93回
総務省がまとめた家計調査には、当然、退職金などをもらった人も含まれており、それを考慮しても毎月5万円程度足りないということなのです。「そんな殺生な…」との声が聞こえてきそうですが、状況はさらに悪化しています。そこで今回は、日本の退職給付制度の現状を確認しつつ、改めて自助の必要性について考えてみたいと思います。

第92回
今回は2000万円に話を戻し、この金額をオヤジたちが準備することがどのくらい大変なのか検証したいと思います。今回の金融庁の報告書に対する主な批判として、平均のみで議論をした点がまずかった、との意見が多かったため、ここではいくつかのケースに分けて考えてみたいと思います。

第91回
人生100年時代には公的年金以外に「2000万円」が必要との情報を金融庁が発信し、新聞やTV、そして国会でも大きく取り上げられました。この金額の根拠は、直近の家計調査で、高齢夫婦無職世帯の実収入が月額20万9198円に対し、支出が26万3717円(含む直接税、社会保険料)で、その差額が5万4519円となっており、その30年分ということで1963万円≒2000万円と計算しているようです。

第90回
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、公的年金は5年に1回、健康診断のような位置づけで財政再計算を実施しています。これにより、現在の公的年金の財政状態がどうなのか、今後様々な経済環境の中で、将来の受給者にどのくらいの年金を給付できるのかを推定しています。前回実施した2014年から5年経過しているため、現在、国は財政再計算を実施しています。

第89回
2019年は株式市場が混乱している中で始まりました。その後、株式市場はアメリカを中心に相応に回復しているものの、引き続き変動性が大きく、「俺たちの老後のお金は大丈夫なのか?」と心配しているオヤジも多いと思います。

第88回
2019年2月に企業年金全般を管轄している企業年金連合会から、確定拠出年金(以下、DC)実態調査結果が公表されました。この実態調査では2017年度のDC実施企業の状況や加入者の運用状況をまとめているのですが、今回はこのレポートからDCの現状をひもといてみることにします。

第87回
年金積立金管理運用独立行政法人、通称GPIFが、2018年10~12月期の運用実績を公表し、14.8兆円の損失を出したことが明らかになりました。これは新聞でも報道されましたので、皆さんもご記憶に新しいと思います。この報道に対して、様々な方面から批判が出ています。

第86回
前回はお金の話を離れ、長野県・小布施町を例にしながら、幸福論や“ワクワク”といった観点から今後の働き方についてお話ししましたが、今回は私の本業であるお金の話に戻りたいと思います。

第85回
“ワクワク”することは幸せにつながる、という考え方があります。自分のやりたいことや特徴を理解したうえで夢や目標を持っていれば、自然と“ワクワク”し、人生に幸福を感じ、そして幸福感を感じている人ほど生産性が上がるようです。

第84回
『国民皆年金』を実現すべく国が様々な制度を導入した結果、皆が年金を受給できるようにはなりましたが、今後年金額を自動調整する仕組みによって年金額が減ると予測されています。実質的にその金額では国民の老後を守ることができないため、自助努力を促すために、新たな税制優遇付きの「貯蓄枠」を導入する動きが出てきました。

第83回
現在の平均余命でさえ、大半の女性が90歳以上まで生きる状態となっているのに、今後は医療技術の進歩でますます長生きになる可能性は高くなっています。このような状況に対応するには、老後にどんな資産運用をすればよいのでしょうか?

第82回
当連載のタイトルは「オヤジの幸福論」ですが、最近、「おっさん」という言葉が話題になっています。その「おっさん」というのは、年齢や性別とは関係なく、凝り固まった価値観やルールに縛られている人たちと定義されています。では資産形成や投資において「おっさん」的な凝り固まった価値観やルールとは何なのでしょうか?
