
秋山進
営業のみなさん、商談前に「予習」しなくていいの?
会社にいるとひっきりなしに営業電話がかかってくる。会社の問い合わせアドレスには数限りない案内メールが入る。あるいは、知り合いから、ある人と会ってやってほしいと頼まれることもよくある。だが、実際に会ってみると全く中身のない面会で終わってしまう。会いたいと言ってきたはずの相手がまともに予習をしていないことがあまりにも多いためだ。なぜこうなってしまっているのだろうか。

社内分断の深刻化、花形部署の凋落…日本企業を待ち受ける経営課題2023
国内で新型コロナウイルスが初めて発見されてから、丸3年が経過、企業組織の在り方は様変わりした。多くの会社は4月が新年度のスタートであるから、現在は2023年度の事業計画がかなり固まってきた頃だと思う。そうした中で、予想される来期の組織づくりや課題のトレンドをまとめていきたい。

「出世を望まない」で生きられる人は、かなり幸せである理由
“積極的に出世をしたくない人“はかなり幸せである。社内外の評価や報酬のためにプレッシャーと対峙(たいじ)するよりも、自分のやりたいことだけをやっていた方がよいと割り切れるからだ。「80歳まで現役」が現実的になっている今、「出世」か「出世放棄」かの二択ではなく中間的な道もあることを知っておいたほうがよい。

「仕事の反省術」で、能力がそのままでも仕事の成功確率は格段アップ
最近のサッカーの試合後のインタビューでは「今日の試合でまた課題が見つかったので、そこを修正して次に臨みます」というのが決まり文句になっている。本場のヨーロッパで活躍する優秀な個が生まれてきた背景には、この振り返りによる課題の発見と修正の習慣化があると思われる。一般社会人の我々は、そのような習慣を持っているだろうか。サッカーの例に鑑みれば、いかに凡人の我々であっても、正しく振り返りができていれば、今の能力のままでも、もう少しましな仕事ができて、成果も上がるはずである。

サッカーW杯「解説者・本田圭佑」で日本中が感じた世代交代の重要性
カタールで行われたサッカーワールドカップは全試合の放送が行われたことで、多くの解説者の解説を聞くことができた。中には最新の動向(技術)に対する理解が浅く、自分がプレーしていた時代の昔のイメージでしか戦術の良しあしを論じることができない人もいた。視聴者のレベルが上がり、求められる解説のレベルも上がっているのにそれに応えられない人はもう不要ではないか。これはそのまま、ビジネスや会社組織にも同じことがいえる。

議論が白熱しない「オンライン会議」で生産性を飛躍的に上げる方法
本連載では過去2回にわたって、東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授と対談した。研究データに基づいた興味深い知見をうかがうことができた。その中でオンライン会議が議題にのぼったが、対談を振り返り、また私自身のこれまでの経験も踏まえて、オンライン会議についての個人的な見解を述べたいと思う。

「スマホ依存で人類絶滅」を脳科学者が本気で危惧する理由
オンラインコミュニケーションは脳にどのような影響を与えるのかをめぐって「脳トレ」や認知症の研究で知られる川島隆太教授と人気連載「組織の病気」の秋山進氏が対談する後編。前編では、脳の同期をテーマにリズムを使う効用やオンライン会議は脳が参加しないという事実が明らかになったが、後編では、スマートフォンによる言語コミュニケーションの阻害や、ICT漬けで人類はついに滅びへとかじを切ってしまったという教授の危惧、ICT教育構想のずさんさにまで話が及んだ。

「オンライン会議は脳にとって質の悪い紙芝居」脳科学者が訴える危険性
リモートワークは一部の会社では当たり前になったが、オンラインのみのコミュニケーションでは仕事に支障が生じると、リアルとのハイブリッドにしたり、リアルの割合を増やしたりする会社もある。オンラインコミュニケーションは脳にどのような影響を与えるのかをめぐって「脳トレ」や認知症の研究で知られる川島隆太教授と本連載『組織の病気』著者の秋山進氏が対談。前編ではなぜオンライン会議では脳が対面していると認識しないのか、脳の同期を使った場の盛り上げ方、聴衆をひきつけるテクニックなどの話題が出た。

組織の中には必ず過大評価される人がいる。このタイプは上手に敵を排除し、自分の立場を良くして、最終的には権力を握る。大勢の人から高い評判を得る。話も巧みなので、メディア受けも良い。ただし問題は、エネルギーのほとんどがいかに見せるかに焦点が当てられ、取り組む問題でさえ、他人にウケる耳になじみの良いことにのみ限定されがちなことだ。こうした人は経営が順調なときは良いが、構造改革を図らなければならない時代には向かない。このタイプを経営トップなど重要なポストに就ける動きがあればそれは危険である。

大企業が今育てるべき人材…プロデューサー、ディレクター、職人のどれ?
企業組織、特にものづくりの企業組織には大きく分けて「プロデューサー的」「ディレクター的」「職人的」の三つの人材タイプが必要だろう。それぞれ違う役割・仕事なので単純な比較はできないが、人材不足が深刻な今の日本企業にとって最も必要とされているのは「プロデューサー」だ。その理由と育成するために必要なことを解説する。

「部下のプレゼン能力が低すぎる」と嘆く管理職の残念な勘違い
プレゼン研修ではいろいろなことを習う。構成、シートの作り方、声の出し方、間の取り方。もちろん上手なほうがいいに決まっているから、練習に価値はある。しかし、ここにひとつ大きな疑問が生まれる。そもそも聞くほうの能力が高いのであれば、プレゼンそのものは本来それほどうまくなくても問題はないはずではないか。

「聞く力」を持つ人がやっている、聞くだけじゃない本当のこと
「聞く力」がある人とはどんな人か。実はその力を有していないにもかかわらず、「自分は聞く力がある」と本気で思い込んでいる人が存在する。単に人の話にじっくり耳を傾ければいいというわけではない。特にリーダーが持つべき本当の意味での「聞く力」について解説していこう。

リモート時代に評価される「優秀な管理職」の条件とは
リモートワークで直接会う時間が減り、会社に行ったとしてもフリーアドレスなため、同僚と直接会って、業務そのもの、業務に関係しそうな周辺の話題、その他いろいろなことについて情報交換する時間は激減している。このような状況下にあって、現在特にリーダーに求められる要件は一体何だろうか。

日本経済の停滞ぶりが「失われた○○年」と形容され、「日本は変わらなければならない」と言われ続けて久しい。米国や中国と比較して異なる点を見つけては、日本は遅れていると自虐的に指弾する。しかし、日本経済が遅れていてガラパゴスだという論は、果たして100%正しいのか。ノーベル経済学賞候補に名を連ねたこともある経済学者の著書から読み解こう。
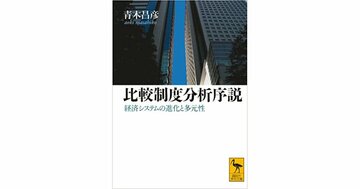
カーリング日本代表の選抜方法を変えるべきではないか
組織において変革を実行するのがいかに難しいか。変革実行には何が必要か。今回は北京五輪でも注目されたカーリング日本代表チームの選抜方法を基に(1)最強チームを作るにはどうすれば良いか、(2)ビジネス的視点では何が最適か、(3)実際に運営可能か、の3つの観点から考えてみる。

最先端の機械翻訳は、松尾芭蕉を訳せるか
Google翻訳やDeepLなど、機械翻訳の進歩がすさまじい。どのような技術革新があったのか。さらに精度が上がるとコミュニケーションはどう変わるのか。また日本人が英語を勉強する必要がなくなる日が来るのか。長らく機械翻訳に携わる第一人者のNTTコミュニケーション科学基礎研究所 協創情報研究部 言語知能研究グループ上席特別研究員・永田昌明氏と本連載『組織の病気』著者である秋山進氏が2回に分けて「進歩がすさまじい機械翻訳の現在と未来」について語り合う。後編では、機械翻訳が今後どのように発展し、人の言語運用はどう変わるのか、英語学習はどうなるのか、社会へのインパクトについて話題が広がった。

「暗黙知」という言葉は日本語として普通に使われている。現場の人が日々の仕事の中で蓄積してきた熟練の技やノウハウなどの「暗黙知」を「形式知化」するなどという使い方が、ビジネスでは一般的だろう。しかし名著『暗黙知の次元』では、暗黙知はもっと広い意味で定義され、生物の知の運動そのものを指す。人間社会がその暗黙知によって激変するかもしれない未来を、読み解いていこう。
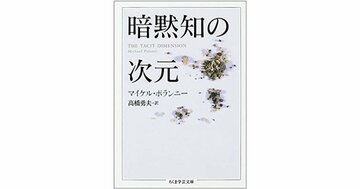
進歩がすさまじい「機械翻訳」、その理由をトップ技術者に聞く
Google翻訳やDeepLなど機械翻訳の進歩がすさまじい。どのような技術革新があったのか。さらに精度が上がるとコミュニケーションはどう変わるのか。また日本人が英語を勉強する必要がなくなる日が来るのか。長らく機械翻訳に携わる第一人者のNTTコミュニケーション科学基礎研究所 協創情報研究部 言語知能研究グループ上席特別研究員永田昌明氏と本連載『組織の病気』著者である秋山進氏が2回に分けて「進歩がすさまじい機械翻訳の現在と未来」について語り合う。前編では、機械翻訳の発展、ニューラルネットワークの画期的な技術革新について、詳しく、わかりやすく解説してもらった。

何でも「ダメ出し」「否定」する上司の問題点
何かを提案した際に、「“それ”、以前失敗したんだよね。うちでは無理だよ」とか、「“それ”、ちょっと前に検討したんだよね。で、やらないことになった」などと、ろくに話を聞かないで否定する上司がいる。実はこのような言い方をする上司は、わずかな例外を除いて、驚くほどNGの判断基準が適当である場合が多いのだ。

「言うべきことを言わない」と金融庁が糾弾したみずほ銀行から学べる本当の教訓
「みずほ銀行のシステムトラブル」は大きな社会問題になった。事件の印象をさらに強くしたのが、金融庁による業務改善命令の文書だ。文書によると、社員の「言うべきことを言わない、言われたことしかしない姿勢」がシステム上、ガバナンス上のトラブルを起こした真因だという。では、この「言うべきことを言わない」「言われたことしかしない」というのはいったい何のことを指すのか。考えてみると意外に難しい。
