
秋山進
ビジネスのあり方は大きく変わったが、学歴は今も重要なのだろうか。結論をいうと、学歴はグローバル社会においてますます重要になっている。そうした中、日本人はグローバルエリートとの競争において厳しい状況に立たされているといえる。なぜなのか。二つの理論を踏まえて解説したい。

無頼派、新戯作派の小説家であり、戦後に『堕落論』で時代の寵児となる坂口安吾が1936年に発表した『日本文化私観』をご存じだろうか。安吾の日本文化についての解釈は、コロナ禍で今何を価値判断の基準にしてよいのか迷える私たちにとっても、格好の指針となる。
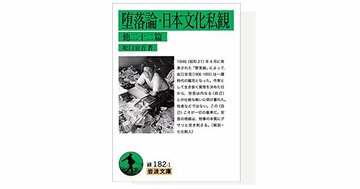
上司が部下に愛想を尽かす4つのパターン、見放されたらどうする?
小言を言われるのはまだマシな方かもしれない…。上司から愛想を尽かされたり、見放されたりするのは、なかなかつらい状況だ。上司が部下を“見放す”のはどんなときなのか。考えてみよう。

上司を手玉に取る人がやっている「関係ずらし」のテクニックとは
上司との関係は、多くの会社員が頭を悩ませる問題の一つだ。しかし、簡単に上司と良好な関係を構築することができる人はいる。中には、上司を手玉に取って自分の思い通りに誘導しているように見える人もいる。そういう人は、どのように関係性を作り上げているのだろうか。

土居健郎著の大ベスセラーとなる日本人論『「甘え」の構造』は、学術的文脈では批判や議論も多いが、会社員にとって示唆に富んでいる。論や見解の妥当性を議論するのではなく、本書に登場する見立てを援用して、現代の会社や職場での人間関係の作り方を考えよう。
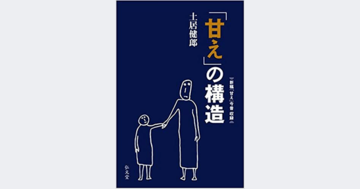
「遅咲き出世」がますます難しくなっている3つの理由
若手のころは特に目立つこともなかったが、管理職に就いたあたりから少しずつ成果を出し始める…そんな“遅咲き”の人にとって、今は厳しい時代だといえる。企業を取り巻く環境の変化が、遅咲きさんの登用をよりいっそう難しくしているのだ。

大した能力がないのになぜか、上司にかわいがられて出世していく人がいる。そうした人たちがリーダーとして適性があるかというと、甚だ疑問である。なぜ「上には気に入られるが、下からは支持されない」人が出てくるのか、どの組織でも一度は見聞きしたことある疑問について考えてみたい。
![なぜ「能力がないのに出世する人」は絶滅しないのか[21年GWセレクト]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/0/360wm/img_b0d1a10579b2342f780e33e391d860b044076.jpg)
いい加減な「ガバガバ納期」がまかり通る、非生産的な職場の特徴
社内における「納期設定」は根拠のないものであることが少なくない。なぜいい加減な納期がまかり通るのか。また、こうしたいい加減な納期が設定されてしまうことの弊害とは何か。考えてみよう。

世阿弥を敬愛するジャパネットたかた創業者の高田明氏と観世流能楽師の武田宗典氏と、世阿弥の名言を取り上げながら、風姿花伝の最重要キーワードでもある「花」にまつわる言葉の数々を取り上げて議論する。

世阿弥を敬愛するジャパネットたかた創業者の高田明氏と観世流能楽師の武田宗典氏と、世阿弥の名言を取り上げながら、現代社会に役立つ「プレゼン術」の極意を語り合います。

世阿弥を敬愛するジャパネットたかた創業者の高田明氏と観世流能楽師の武田宗典氏と、世阿弥の名言を取り上げながら、現代社会を生き抜くヒントを語り合う。今回は『花鏡』に登場する世阿弥の名言「初心忘るべからず」について解説、議論する。

出世の道が途絶え、自分の会社員人生に希望が持てず、“ひねくれ”てしまう中高年社員は少なくない。実は能力が高いのに、くすぶっている彼ら彼女らを企業はどう生かしていくことができるのか。

「余人をもって代えがたい」トップが組織に居座る真の問題点とは何か
大きな権力を持ったトップが組織に居座ることは往々にしてある。なぜそのような状況が続くのか。また、そうした人間がトップにいることの問題とは何か。

会議の席で「わきまえない」人とは?5つの視点で考える
東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会元会長の森喜朗氏の発言が物議をかもし、そのなかで、「わきまえない」という表現がさらに波紋を呼んだ。今回は森氏の発言内容とは関係なく、一般に、特に会議の席で「わきまえない」とはどういうことなのかを考えてみたい。

世阿弥の名著『風姿花伝』は、オンライン時代に役立つ心得が満載だった!
オンラインでのコミュニケーションが中心になりそうな時代。この時代を生きるヒントとして今回取り上げるのは、約600年前の能楽書『風姿花伝』だ。現代のビジネスパーソンがオンラインでいかに振る舞いをいかにすべきかに通じる神髄を伝えている。
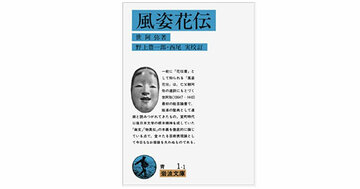
第162回
はやりの理論を聞きかじっても組織が良くならないワケ、取り組むべき王道は?
組織づくりや組織の運営方法においては、“トレンド”のような理論が注目を浴びることが度々ある。ただ当然ながら、そうした理論に飛びついたからといって組織が良くなるわけではない。重要なのは、どんな組織にでも応用可能な基本的な取り組みである。

一流経営者がコロナ禍のコミュニケーションに感じている本質的な課題
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、コミュニケーションの仕方も大きく変わった。ある経営者は、コロナ禍で直接顔を合わせてのコミュニケーションが難しくなったことで、「将来のビジネスのための仕込み」に影響が出ていると話す。その理由とは?

近代国家としての日本が成立する過程において、500の企業を育て、約600の公共事業に関わった「日本資本主義の父」渋沢栄一。2021年のNHKの大河ドラマで採り上げられることもあって、その講演録『論語と算盤』が改めて注目されている。
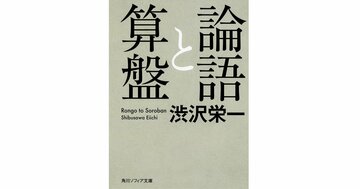
第160回
目立った実績がなくても「順調に出世する人」は、何をしているのか
目立った実績がなくても、常に人事考課もよく、順調に出世していく人がいる。そういう人たちの行動や考え方からは、組織で賢く巧みに生き延びる処世術を大いに学ぶことができる。

第159回
多くの企業が自社の重要課題を解決するために、外部のコンサルタントを活用している。しかし、コンサルを入れても全くその成果が出ていない会社も少なくない。コンサルをうまく使える会社と、使えずに失敗する会社にはどんな違いがあるのだろうか。
