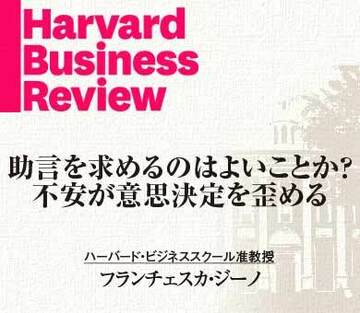フランチェスカ・ジーノ
グーグルの社員食堂に学ぶ、人々を「そっと動かす」秘訣。従業員の行動を変えるには、変更を強要するのではなく、意思決定が行われる「場」に少しだけ手を加えてみてはどうだろう。

第5回
ディズニーで学んだ、離職率を60%下げる新人研修の方法
「あんなに研修を受けさせたのに、すぐに辞められてしまった……」研修をしても福利厚生をよくしてもなかなか解決しない離職率の問題。ディズニーが新人を使命に忠実で知識豊かな人材に変える手法に着目した著者が、どうすれば会社と新人の双方にとって「よい選択肢」を提示できるか、解き明かします。

第4回
好況下で伸ばしたCEOと不況下で持ちこたえたCEO、どちらがすごいのか?
新しいCEOを選ぶ時、過去に成功を収めた華々しい経歴を持つ人と、ほとんどの企業が撤退した業界で結果を出してきた人とでは、あなたが信頼するのはどちらの人でしょうか? 「対応バイアス」という人間心理を手がかりに、どうすれば「正しい情報」に基づいて意思決定できるのか、解き明かします。
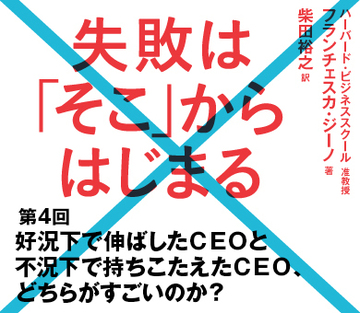
第3回
フェイスブックとトム・ハンクスが教えてくれる「評価」の難しさ――どうすれば公正な制度を構築できるのか?
従業員をやる気にさせるための評価システムを作ったはずなのに、かえってモチベーションが下がってしまったこと、ありませんか? トム・ハンクスの「悲劇」とフェイスブックの「恐るべき仕組み」から、どうすれば公正な評価制度をつくれるのか、解き明かします。
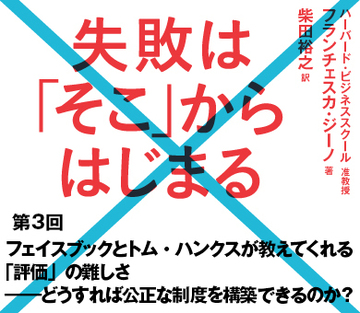
第2回
なぜコカ・コーラは顧客を裏切る意思決定をしたのか?
綿密に計画を練り上げてゴーサインを出したはずのマーケティングプランが、まったく逆効果に終わったこと、ありませんか? 「顧客のため」を思ってやったことが、大ブーイングを浴びてしまったコカ・コーラ社の事例から、どうすれば顧客の本当のニーズを拾い上げて意思決定できるのか、解き明かします。
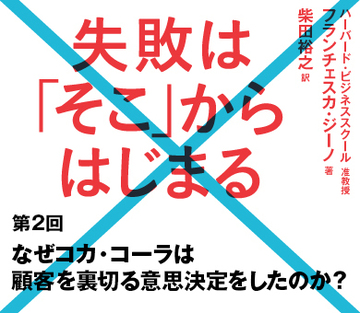
第1回
なぜCEOは「貴重な助言」を無視するのか?――ウォルマートとグリーンスパンの「避けられた失敗」
勉強も、ダイエットも、貯金も、マーケティングプランも……綿密に計画を練り上げたはずなのに、気がついたら失敗していた、という経験はありませんか? 元FRB議長のアラン・グリーンスパンやウォルマートのような、世界一流の人や企業の大失敗から、「しくじらない」意思決定の原則を解き明かします。
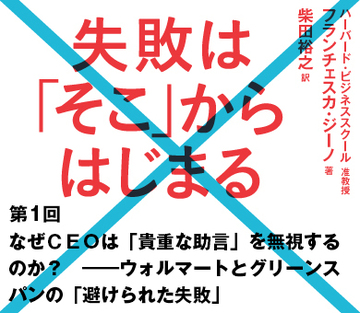
職場での不正行為は、明らかな悪意があって始まるものではない。むしろ、最初は「ほんの端数を切り上げただけ」といった小さな無分別から始まるという。実験によって、人の倫理観が失われていくプロセスと不正防止の手がかりが示された。

対人コミュニケーションにおける第一印象を左右するものの1つに、「握手」がある。では、交渉の際に握手をするのとしないのでは結果に違いが生じるのだろうか。ハーバード・ビジネススクールの行動科学者が、興味深い研究を報告する。

重大な決断には不安がつきものだ。それを和らげるために、他者に助言を求める。この「不安」と「助言への依存」が意思決定に及ぼす影響を実証した、研究結果を報告する。本誌2014年3月号特集「意思決定を極める 」の関連記事、最終回。