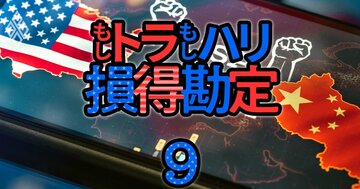西濵 徹
米中摩擦の「漁夫の利」を得てきたベトナムは、2025年にトランプ米政権の関税政策で試練を迎えた。相互関税は当初46%とされたが協議で20%へ引き下げたものの、迂回輸出には40%課税という不確実性が残る。輸出・GDPは堅調でも、対内直接投資、通貨の動向にリスクが残る。

インフレ再燃を受け、ブラジル中央銀行は利上げを重ね、政策金利は15%と約20年ぶりの高水準に引き上げられた。個人消費は低迷気味だが、トランプ関税の影響はそれほど大きくはなく外需は堅調である。足元の景気・企業マインドも改善傾向にある。足元はインフレが落ち着きつつあることもあり、株価指数は最高値を更新した。2026年以降のブラジル経済の行方を検証する。

トランプ関税と米中対立に翻弄された2025年の新興国経済。米中対立の“先送り”は輸出依存度が高い新興国には追い風だ。インドやブラジル、メキシコなど注目の新興国の先行きや、米中対立の“次の舞台”の候補となりそうな地域について展望する。

中国経済は足元で供給サイドがけん引役となり、鉱工業生産や米国以外への輸出が景気を下支えしている。一方、不動産不況や雇用回復の遅れ、節約志向の拡大で家計部門の力強さは欠く。米中摩擦はいったん緩和したものの、内需喚起策の効果は息切れしつつあり、需給ギャップ拡大によるデフレ圧力が強まる構図に変化はない。

トランプ政権の政策不確実性とFRBの利下げでドル安圧力が強まるなか、金価格の最高値圏推移が追い風となり南アフリカの通貨ランドは堅調だ。南アの漸進的利下げでも実質金利は高止まりして、資金流入を支える。足元のGDPは持ち直すが、対米関税や投資停滞など実体経済の弱さが残り、市場との乖離には警戒を要する。

トランプ米政権の関税政策は新興国経済に波及し、トルコも例外ではない。ロシア産原油を巡る2次関税リスクに加え、通貨リラの不安定や内需の鈍化、輸出不振、政治不信が重なり、表面的な景気底入れ感とは裏腹に不透明感が強まっている。

トランプ米政権による相互関税政策は、フィリピン経済には限定的な影響とみられる。一方、内需拡大と利下げ継続が景気を下支えしている。インフレ鈍化も追い風となっている。政局ではマルコス家とドゥテルテ家の対立が激化。経済状況以上に注目を集めることになりそうだ。

アルゼンチンは長年の財政悪化と通貨不安に苦しんできたが、自由至上主義を掲げるミレイ大統領の下で大きな転換点を迎えた。大胆な構造改革とインフレ抑制策により経済指標は改善傾向を見せ、国際的な評価も高まりつつある。一方で、対中関係の再構築や対外収支の課題、そして政治的安定性といった懸念も根強い。10月には中間選挙を控えており、改革の行方は国民の審判に委ねられることになる。

韓国で行われた大統領選挙で革新系の李在明氏が勝利し、即日就任する異例の政権交代が実現した。経済格差や少子高齢化といった構造的課題を抱える中、新政権は補正予算の拡充や財政出動を軸にした景気下支え策を打ち出す。外交面では「実用主義」を掲げ、日韓関係の行方にも注目が集まる。

#16
トランプ関税政策のアジア新興国への影響は米中貿易戦争が投影する形で濃淡が出そうだ。中国は米国との大幅引き下げに合意し一息ついた感じだが、米中と関係が深いASEAN諸国はダブルパンチを受けかねない。一方で中国に代わる市場との思惑から低関税とされたインドは有利な立場だったが、ここに来て微妙な様子もうかがえる。

米トランプ政権による相互関税の影響が世界経済に波及するなか、インドネシアは外需の減速とプラボウォ政権の歳出削減に直面している。公共投資の停滞や設備投資の減退、インフラ整備の遅れが景気の足を引っ張り、政権が掲げる高成長路線にも暗雲が漂う。財政運営のかじ取りの難しさが浮き彫りとなっている。

46%というトップクラスの関税をトランプ政権よりかけられたベトナム。中国からの迂回(うかい)輸出先となったために標的とされた形だ。一律10%分を除いた上乗せ分は90日間停止とされたが、影響は回避できない。

トランプ関税の主な標的となっているメキシコ経済。2024年10~12月期はマイナス成長になるなどすでに減速傾向にある。発動と猶予を繰り返すトランプ関税だが、本格的に発動となれば、その影響は極めて大きい。そうなればペソ安が再進行する公算が大きい。

タイ経済は他のASEAN(東南アジア諸国連合)よりもコロナ禍からの回復が遅れている。サービス輸出は好調だが、財輸出の先行きには不透明感が漂う。消費も投資も振るわない状況が続いており、当面は低成長が続きそうだ。

経済成長の鈍化もあり、景気対策を打ち出した中国に資金が向かい、インドの株価はさえない。トランプ米新政権の政策によるドル高期待で通貨ルピーも下落基調。インフレ懸念もくすぶるなどインド経済は苦境にある。

#24
2025年の新興国経済は、米国のトランプ新政権の通商政策に右往左往させられるだろう。メキシコやインド、ブラジルなど2025年の主要新興国経済について、関税をはじめとするトランプ政策の影響と見通しを分析する。
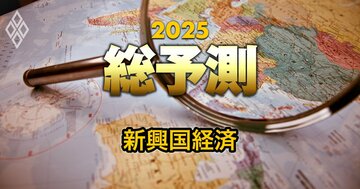
2023年に発足したルラ政権による財政赤字拡大を懸念して、通貨レアル安が進行している。堅調な景気もあり、低下していたインフレは底を打ち上昇に転じた。中央銀行は利上げに転じたものの、ルラ政権からの利下げ圧力を受けている。レアル相場は難しい局面が続きそうだ。

米大統領選挙でハリス氏、トランプ氏のどちらが勝利しても対中国強硬路線は変わらない。トランプ政権になれば中国製品への60%関税にとどまらない強硬で保護主義的な政策が取られる可能性が高い。長期停滞が続く中国経済は、回復の「出口」が見通せない状況が続く。

中央銀行であるニュージーランド準備銀行(RBNZ)は、大幅利上げでインフレの抑制に成功した。しかし、足元では景気減速に拍車がかかっている。8月に利下げに転じたが、今後もハト派姿勢を継続しそうだ。

#9
米大統領選挙でハリス氏、トランプ氏のどちらが勝利しても対中国強硬路線は変わらない。トランプ政権になれば中国製品への60%関税にとどまらない強硬で保護主義的な政策が取られる可能性が高い。長期停滞が続く中国経済は、回復の「出口」が見通せない状況が続く。