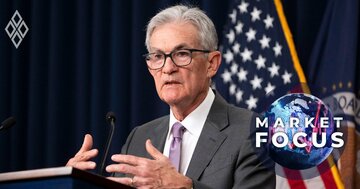田中泰輔
2月8日の衆院選へ、高市与党と野党がそろって消費税減税を公約したところ、日本の超長期国債相場が急落(金利上昇)した。市場では、日本財政が無責任な減税路線で破綻する、日本発で世界市場が危機に見舞われると、相変わらずの悲観論が浮上した。それは本当に「今そこにある危機」なのかを冷静に捉え、リスクテイカーとしての投資家目線を保ちたい。

2026年の経済見通しに無難な予測シナリオが並ぶ。しかし、投資家の多くは不穏さも感じているに違いない。そこには通常の指針・尺度が通用しない事情がある。言葉で26年はこうだと明快に語ることは簡単だ。しかし、投資ポジションというリスクを伴う行動での表現は異なる。無難な予測と不穏さを投資でどう描くか、その勝機を考える。

恒例の新年相場たけなわの季節である。2026年の円相場見通しは上下に分かれやすい事情がある。しかし、その確からしさが定まらない、アナリスト泣かせの場面である。米ファンダメンタルズ予想は、底堅さを保てるか、下振れがあるかというリスクバランスで見ている。ただし、米国の景況が同国金利を通じて円相場を動意づかせると、日本市場のリスクは増幅されかねない。市場予想をうのみにせず、情勢をきちんと理解して、相場に臨みたい。

米AI株高への連れ高に加え、高市政権への政策期待から、日経平均株価は10月に一気に5万円を突破した。月次ベースでは、30余年来の上昇率となった。その米AI株高にはバブル論争がある。一般論として、相場がバブルかの判断は破裂する前には下せない。日本株相場もまた、バブルとは言えなくても、とても平常と言えない熱量には留意が必要だ。

高市早苗氏が自民党初の女性総裁となり、首相として政権を担う公算だ。高市氏はアベノミクスの継承者として知られる。金融市場に身を置く筆者は、アベノミクスに親和的であり、高市政権に期待するところも大きい。しかし安倍政権当時とは、経済・市場環境、政策の必要性は変化している。当然、安倍相場(円安・株高)の再現にも制約がある。

米AI株相場は、まだ上昇トレンドをたどれるか、関税の悪影響が顕在化する局面をどうしのげるかを問われる場面が来る。銘柄・業種間でリバランスが発生しやすく、単純な相場ではなくなる。高値警戒の米国株からの分散投資先として循環物色されてきた日欧株、一見堅調でも根本問題を抱えたままの中国株の相場を、米国株と通貨の観点から評価する。

米国株は、トランプ関税のかく乱、景気の不確実性の下でも、AI主導のラリーを続けている。持続する相場ラリーの背景は何か。そして、その延長線上で、8~9月、10~12月をどう読み、どう対応したらよいか。正解の存在しない不確実性下での相場にいかに対処するか、そのロジック、テクニックを体感する一助として、筆者の見方、取り組み方を紹介する。

参院選に持続的な相場インパクトはあるか。選挙公約にどれほどの実現可能性があるのか。その精査なくして、相場への含意は乏しい。そもそも日本市場においては、米国の金利次第で円相場が動き、その円相場と米国株次第で日本株が動く。その先導役はほぼ外国人であり、他力本願が大きい。参院選の結果が、トランプ大統領下の米国のマクロ事情を凌駕するほど、日本のマクロ情勢を変えられるとは想定しがたい。

トランプ関税の交渉期限、米経済指標の悪化の頃合いとなる7~9月期に米日市場のリスクオフ再燃を「転ばぬ先の杖」シナリオとして注視している。昨年8月初めにかけて、米国の経済指標の陰り、株安、金利低下が円高を招き、日本株をフラッシュクラッシュさせたイメージと重なる。再びこの展開になったとき、市場が十分に織り込めていない強烈な円高リスク要因として為替ヘッジ操作が挙げられる。

米株相場は、4月の米関税リスクオフから、順当に復調路に入った。5~6月は関税ディールと経済指標どっちつかずの2つの猶予期間で、復調地合いを保てるかもしれない。7~9月には指標悪化、関税ディールの不調がリスクオフを再燃させるリスクがある。ただし、ここでの景況・市況の悪化が厳しいほど、息の長い好相場トレンドを生む可能性がある。

ドルが下落している。その背景について、トランプ政権の無謀な政策がもたらす自業自得との指摘がある一方、トランプ政権が国内製造業復活のために「第二プラザ合意」でのドル安誘導を目指すとの見方もある。米株・債券・ドルの「トリプル安」が進み、とばっちりで円高・日本株安を不安視する国内では、「リーマン級危機」といった声も出ている。だが、不安に駆られて短絡的な言葉を独り歩きさせると、リスクの実相を見損ないかねない。

米国株が急落している割に、日本株の下落率は相対的に小さい。また、ドイツなど欧州株、中国株は上伸している。このことは、米株安は自律調整を多分に含み、世界にリスクオフを伝播させる状況ではないことを示唆する。しかし、底堅い日本株は上昇力も欠いている。その背景は何か、どうしたら上抜けられるのか、日本と日本株の活路を考える。

トランプ2.0は、国際ルールを無視するかの政策を突然とっぴにぶち上げ、ディール次第で朝令暮改も意に介さない。それは場当たり的に見える一方、最終目的に向かう迂回路を綿密に練っているとも推察される。米大統領の一言一句に直接的反応を見せていた市場は、朝令暮改によるハシゴ外しにも度々遭い、目線が定まらない。不確実性を嫌う株式相場の下値は脆弱化しつつある。投資家として、不安で不透明な場面の予測情報の偏りを踏まえ、シナリオ分岐多発リスクにどう臨むべきか。

日本銀行は、日本を普通に金利のある国へ復帰させるべく、着々と利上げを進めている。しかし、「日銀『が』」と、日銀が主体的に決めているという視座では、利上げの進捗を的確に捉えきれない事情がある。日本のデフレ克服機運、企業の改革・賃上げの好循環ムードは、「米国事情『が』」許す限りという他力本願の部分が今も小さくない。そこにトランプ2.0が重なる。外部条件と日銀政策の相場インパクトと投資対応を考える。

2025年を迎え、専門家が年間予想を競い合う。ところが、25年ほど専門家泣かせの年はない。米国の政治、経済、相場の先行きに目線の定めようがなく、強弱一方向に傾けた強い予想は掲げにくい。そうかといって、それが安穏な情勢判断を意味しないことは明らかだ。25年の「まさか」を4テーマから検討し、目線が定まらない事情を浮かび上がらせる。特定の見方に肩入れすべき状況ではなく、波乱に備える柔軟性こそが重要な1年と考える。

各国の政治が先鋭化している。専制主義国家の横暴ばかりではない。西側自由主義国でも、極端な政治信条を掲げる政党の躍進が目立つ。それが国内で、政治対立の構図を生み出すこともあれば、妙にまとまることもある。我々は今、どのような政治空間を進んでいるのか。それは市場にどのような影響を及ぼすのか。

米国では、先行き見通しを立てにくいマクロ情勢が続く中、FRB(米連邦準備制度理事会)は金融政策の運営を「データ次第」とする柔軟姿勢を取っている。しかし、年初に市場は今年の利下げを6回と織り込み、4月には景気しっかりで利上げも辞さずと見通し、8月には景気後退不安が浮上し、足元では景気堅調に逆戻りとデータの振れは激しく、FRBも市場も目線を節操なく変転させている。そもそもデータはなぜこんなに振れるのか、信頼に値するのか、投資家としてどう対処するべきか。

7~9月期の日経平均株価は、主要先進国の株式相場の中でも、突出した乱高下ぶりだった。それまでの日本株高を正当化する論調がグダグダになり、情報面でも混乱しやすい場面である。しかしこれは、米景気・金利が陰る局面に想定された順当な展開といえる。日本の投資家として、まだ続き得る波乱へ備え、活路を見いだす上で、自国株の変動メカニズムをきちんと理解しておきたい。

8月の米日株、ドル円の暴落は、米景気・金利サイクルの変わり目で生じがちな典型的現象である。株式相場の暴落は、金融相場から業績相場、業績相場から逆金融相場、逆金融相場から逆業績相場への節目ごとに、危険度が異なる。今般の暴落後の相場は、下値の不安定さを当面くすぶらせるとみている。投資家として、何をチェックし、どう構えるか。

8月に入り、急な円高が日本株を過去最大幅で下落させ、世界をリスクオフ警戒でおののかせた。しかし背景は、米国株相場を牽引(けんいん)してきた生成AI・半導体株の自律反落、米景気悪化観測が招いた米金利の先安観がある。円相場も日本株も米国次第の他律的変動が主である。しかし日本では、国内株高は日本礼賛論、円安は日本憂国論がまかり通る。米景気・金利の変わり目というキナ臭い局面に見るべき相場シグナルを明らかにする。