戸田一法
一定の交通違反歴がある75歳以上の運転者に運転免許更新時の技能検査(実車試験)を義務付ける改正道路交通法が、5月13日から施行される。同日からは衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)などの機能を搭載した安全運転サポート車(サポカー)の限定免許制度も開始。既に実施されている認知機能検査や講習と併せ、母子が死亡した「池袋暴走事故」のような惨劇を防ぐための事故対策が強化される。一方、検査で不合格となれば免許が更新できなくなり、交通事情の悪い地方の高齢者にとっては厳しい措置となる。

日本からレバノンに逃亡した元日産自動車会長のカルロス・ゴーン被告(68)に対し、フランスの検察当局は21日、自動車大手ルノーの資金を不正に流用した疑惑を巡り国際逮捕状を発布した。ゴーン被告は日本の司法制度を「不公正」と批判する一方、フランスの司法制度は「信頼できる」と捜査を歓迎。訴追されても「自らの無罪を立証できる」と強弁していた。

北海道旭川市で昨年3月、中学2年の広瀬爽彩さん(当時14)が凍り付いた遺体で見つかり、その後に上級生らによる性的行為の強要などが明らかになった問題を受け、第三者調査委員会は15日、7人が関わった6項目について「いじめ」と認定する中間報告を公表した。中学校や市教育委員会は隠蔽(いんぺい)を図ろうとしたものの「文春砲」によって暴かれた事実は、おぞましい行為の数々だった。

1日施行の改正少年法で18~19歳(特定少年)の実名報道が可能になったことを受け、甲府地検は8日、殺人と殺人未遂、現住建造物等放火、住居侵入の罪で甲府市の無職、遠藤裕喜被告(19)を起訴し、実名を公表した。検察当局が特定少年の氏名を公表したのは初めて。岡本貴幸次席検事は「2人を殺害して放火した重大事案であり、改正少年法の趣旨を踏まえ、地域社会に与えた影響も深刻であることを考慮した」と説明。メディアの報道対応は分かれた。
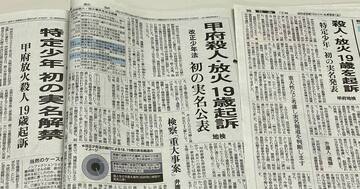
2019年の参院選広島選挙区を巡る選挙違反事件で、河井克行元法相(59)=公選法違反(買収)の罪で懲役3年が確定=から現金を受領したとして、東京第6検察審査会(検審)が「起訴相当」と議決した地元議員ら34人の事件が広島地検に移送された(3日付)。年度内にも立件される見通しだ。事件を巡っては、いったん東京地検特捜部が被買収側100人全員を不起訴としたが、処分には強い批判が相次いだ。国民の代表である検審の議決はその声に応えた格好だが、最近、検察の感覚が一般市民のそれとはずれてきていることが浮き彫りになっていた。

4月1日施行の改正少年法で、罪を犯したとして起訴された18~19歳の「特定少年」について、これまで禁止されていた実名報道が可能となる。最高検は実名公表基準について社会的関心が高い裁判員裁判の対象事件を「典型的事例」としたが、一律の明確な指針は示されていない。また実名で報道するかどうかは報道機関各社の判断に委ねられることになり、検察の発表と報道の内容にばらつきが出るのは必至だ。

日産自動車元会長カルロス・ゴーン被告(67)の役員報酬を過少に記載したとして、金融証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた元代表取締役グレッグ・ケリー被告(65)と、法人としての日産に対する判決が3日午前10時から、東京地裁で言い渡される。ゴーン被告の海外逃亡により公判は「主役不在」で続いていたが、ケリー被告が問われたのは共謀した罪で、必然的にゴーン被告に対する司法判断でもある。判決の行方が注目されるが、前例のない事件だけに識者の間でも予想が難しいようだ。求刑はケリー被告が懲役2年、日産が罰金2億円。果たして、有罪か、無罪か…。

米短文投稿サイトツイッターは、昨年上半期(1~6月)に投稿の法的な削除要請が世界で4万3387件あったと発表した。このうち日本は1万8518件と約43%で世界最多。犯罪に利用しようとする勢力が多い半面、防止と抑止に向けた監視機関が目を光らせている実態も浮き彫りになった。

東京地検特捜部は20日、5000万円余を脱税したとして、所得税法違反の罪で日本大学の前理事長田中英寿被告(75)=1日に理事長を辞任=を起訴した。大学トップとして13年にわたり君臨し、絶大な影響力を誇った田中被告。カネの面で支えていたのは日大元理事(逮捕後に辞任)の井ノ口忠男被告(64)=背任罪で起訴=で、井ノ口被告が取締役を兼務し実質的に仕切っていた関連会社「日本大学事業部」(以下・事業部)は「集金マシーン」と呼ばれていた。「日大のドン」こと田中被告の大学私物化と暴走を許したのは、井ノ口被告との蜜月関係と、田中被告の妻が経営する「ちゃんこ店」に通った歴代幹部だった。

17日午前、大阪市北区曽根崎新地の8階建て雑居ビルの4階にある心療内科クリニックから出火し、24人が犠牲となった。年の瀬の大阪・キタで起きた大惨事。大阪府警は防犯カメラの映像から、殺人と現住建造物等放火の疑いで住所・職業いずれも不詳の谷本盛雄容疑者(61)=意識不明の重体=を特定した。映像には谷本容疑者が液体入りの紙袋を受付前の床に置いてしゃがみ込んだ直後、一気に火の手が上がる様子が残されていた。犠牲者の多くは避難口をふさがれ、一酸化炭素中毒であっという間に死亡したとみられる。

千葉県八街市で6月、飲酒運転の大型トラックに下校中の児童5人がはねられ死傷した事件は、ことし人々が最も心を痛めた交通事件と言って良いだろう。自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた元運転手梅沢洋被告(60)の公判は千葉地裁で続いており、飲酒運転が常習だった事実などが明らかになった。この事件を受け、警察庁は道路交通法施行規則を改正し、来年10月から「白ナンバー」事業者に対しアルコール検知器による飲酒検査を義務化する方針を決定。運転手の呼気から基準値を超えるアルコールを検出すると、エンジンがかからなくなる装置にも注目が集まっている。

会計検査院は2020年度決算検査報告をまとめ、新型コロナウイルス対策を巡る関連事業を含めた計210件、総額2108億7231万円の無駄遣いなどを指摘し、岸田文雄首相に5日、報告書を手交した。検査院と聞けば「無駄遣いをチェックする役所」とイメージされると思うが、検査を受ける側の公務員などは別として、一般の方にはなじみがないのではないだろうか。「会計検査院」とはどんな役所か、元担当記者が分かりやすく解説してみたい。
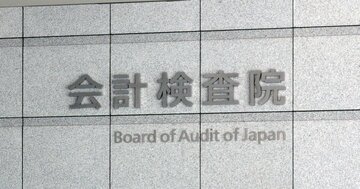
横浜市の旧大口病院(現横浜はじめ病院、休診中)で2016年、入院患者3人の点滴に消毒液を注入して殺害したとして、殺人罪などに問われた元看護師・久保木愛弓被告(34)の判決が9日、横浜地裁で言い渡される。10月22日の公判で検察側は死刑を求刑し、弁護側は心神耗弱状態だったとして無期懲役が相当と主張。久保木被告は「死んで償いたい」と述べた。家令和典裁判長は「どのような結果になろうと主文の言い渡しは最後にします」と異例の通告をしており、極めて厳しい刑が予想される。

警視庁は国から新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで立川署交通課の巡査部長の男(59)を今月3日付で書類送検し、懲戒免職処分にした。元巡査部長はあと数カ月で定年となり、退職金2000万円超が支給されるはずだったが、それもフイになった。ほかにも経済産業省キャリアや税務署、国立印刷局の職員らも給付金詐欺で立件され、いずれも懲戒免職に。明日の生活費にも事欠くのであれば「やむを得ず、のるかそるか」に賭けたのも理解できるが、いずれも行き詰まっていたわけではなさそうだ。給付金詐欺は、ちょっと調べれば簡単にばれる稚拙な手口だ。経産省は本格的な不正受給の調査に着手、その上で「身に覚えがある人たち」に自主的な返還を呼び掛けている。

カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業を巡る汚職事件で起訴された後、贈賄側に裁判で虚偽の証言をする見返りに現金の供与を持ち掛けたとして、収賄と組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の罪に問われた衆院議員・秋元司被告(49)の判決公判が7日、東京地裁で開かれる。

存在しない債務をでっち上げてメールや郵便物、電話などで支払いを求める架空請求詐欺が一時流行し、一般的に無視を決め込めば問題ないと認知されてきたが、それを逆手に取って実際に裁判所に民事訴訟を起こし、法的に債権を得て預金口座を差し押さえる手口などが散発している。少額訴訟や相手に訴訟があったこと自体を気付かれないようにする「知らぬ間敗訴」など、手口はさまざま。裁判所は訴訟手続きの申請があれば事務的に処理するため、詐欺と見破るのは不可能で、内容証明などが届いたら確認するよう呼び掛けている。
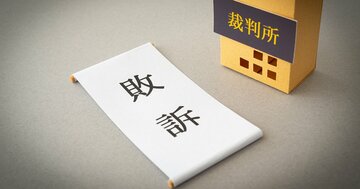
山梨県早川町の物置小屋で私立高校3年の鷲野花夏さん(18)=東京都墨田区=の遺体が見つかった事件を巡り、インターネットなどに「任意聴取の段階で新聞やテレビが速報したのは報道協定があったのではないか」「なぜこんなスピード逮捕が可能だったのか」「容疑者が殺害を認めているのになぜ逮捕容疑は死体遺棄なのか」などの投稿が相次いでいる。

東京・池袋で2019年4月、乗用車が暴走し母子2人が死亡、9人が重軽傷を負った事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)の判決公判が2日、東京地裁で開かれる。飯塚被告は乗用車のトラブルが原因だったとして無罪を主張しているが、検察側は7月15日の論告求刑公判で法定刑として最長の禁錮7年を求刑、結審した。弁護側の主張が認められれば無罪の可能性はあるが、有罪なら執行猶予のない実刑の可能性が濃厚だ。

よく「20~30代は不摂生だったのに、どうやってフルマラソンを走れるようになったのか」と尋ねられる。メタボのドシロウトが自己流でフルを完走するまでの実体験をご紹介したい。
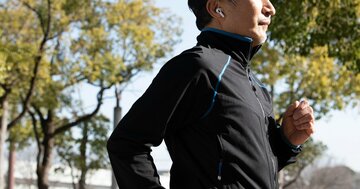
一昨年の参院選広島選挙区を巡る選挙違反事件で、東京地裁は先月、公選法違反の罪に問われた元法相で前衆院議員の河井克行被告(58)に懲役3年の実刑判決を言い渡し、地元議員ら100人全員の現金授受を認定した(河井被告は東京高裁に控訴)。しかし、東京地検特捜部は6日、100人全員を被買収で立件することなく、不起訴処分に。これに異議を唱える地元の市民団体は参院選当時に現職だった政治家40人を対象に15日、検察審査会に審査を申し立てた。河井被告に対する実刑判決と特捜部の不起訴処分で終わったかのように思われたこの事件。実は、広島の政界にとっては混乱の序章にしかすぎないのかもしれない。
