
唐鎌大輔
円安が急速に進行しても、日本銀行は金融緩和を続け、円安は日本経済にプラスであるとの姿勢を崩さない。果たして、それは本当なのか。日銀のレポート、過去の円相場と輸出動向の関係などから検証した。
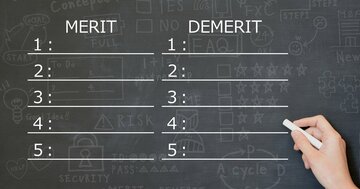
ロシアのウクライナ侵攻を契機に原油、穀物の価格が上昇している。その多くを輸入に頼る日本の貿易赤字は拡大し、経常収支も月間で赤字に転落した。経常赤字の常態化は円を支える要因の消滅を意味する。

米国金利上昇、米国株下落、ロシアのウクライナ侵攻懸念など市場はリスクオフに傾いている。以前であれば、「リスクオフの円買い」が起きて、円高がかなりの幅で進行していた。しかし、2022年に入って、円の対ドルレートは3円弱の幅の動きにとどまっている。日本の株価も主要国に比べてさえない動きが続いている。日本は市場から回避されている。

今後のドル円相場に対する市場の大方の見方はドル高円安である。この見方を覆す要因があるとすれば日本銀行の金融政策正常化かもしれない。円安がインフレに拍車を掛けることになれば、岸田政権は円安を放置できまい。そうなれば、日銀が正常化に踏み切る可能性はあるのではないか。

ドル円相場は4年8カ月ぶりの115円台をつけた。今年の変動幅は、5年ぶりの大きさになる見通しだ。インフレに対応し、金融政策の転換を模索する他の主要国の中央銀行と違い、日本銀行に政策変更の兆しはない。こうした状況下、次の大相場は円安となる公算は小さくない。

外国為替市場で、円の実質実効為替レートが1970年代前半並みの水準まで落ち込んでいる。「割安な実質実効レートはいずれ修正が進む」と考えるのは教科書的に正しいが、これを前提に為替予想を行うことは危険をはらんでいる。

PMI(購買担当者景気指数)のような景況感や心理を表す経済指標が悪化している。それを裏付けるかのように、景気の先行指標である、銅価格を金価格で割って算出される「銅/金レシオ」も低下している。中国経済の指標にも伸びが鈍化するものが目立つ。世界経済の先行きに黄信号がともりつつある。

6月の金融政策決定会合で日本銀行は気候変動対応への投融資を支援する枠組みの導入を決めた。しかし、中央銀行が企業の資源配分に介入することは中立性に反する。また、環境対応は短期的には不況やディスインフレを招きかねない。中央銀行は環境対応に距離を置くべきだ。

4月に入ってドル安傾向が続いているが、主要国通貨の中で円だけがドルに対して強くなれないでいる。それは、周回遅れの新型コロナウイルスワクチン接種、そして変異株を中心とした感染蔓延状況ゆえと思われる。ドル円の取引量も細っており、円自体への関心が低下している。

IMFの見通しでは、2021年の世界経済はワクチン接種率に優れる先進国の回復が先に立ち、新興国との格差が平時に増して拡大するという。今年後半、世界経済の正常化の過程で危機に陥る新興国通貨はどれか。いくつかのポイントを基に考察しよう。

為替市場では、米金利の上昇が一服するに伴いドル高も小康状態になり、対円では円高に引き戻されつつある。円安・ドル高局面は終わったのだろうか。わずか3ヵ月で2倍の水準になった米金利の趨勢を考えると、今後も上値は見ておくべきだ。

2020年はドルを中心に、先進国通貨において「金利のない世界」が常態化する中、経常黒字、貿易黒字、対外債権といった「需給」が強い影響力を持った。足もとで、為替を動かすテーマは変わりつつある。先進国通貨のパワーバランスはどう変化するのか。

金融市場では米金利の上昇が耳目を集めているが、これに連れて日欧の金利も浮揚し始めている。このことは、とりわけ金融システムへの不安が慢性的に漂うユーロ圏で問題視されるだろう。欧州における金利牽制の動きと、それがもたらす影響を考察する。

米国の長期金利が上昇している。金利の上昇は、株価や為替にも少なからぬ影響を及ぼす。金利がどこまで上がるかが、2021年の金融市場を見通す上での要諦になると考えて間違いない。米10年金利の動向を、いくつかの指標から徹底分析する。

新型コロナのワクチン接種が世界に先駆けて行われたイスラエルでは、その効果が見えつつある。今後、金融市場もワクチンの動向を材料視して動いていくだろう。それに関連して囁かれているのが、「イスラエルリスク」という巷説だ。
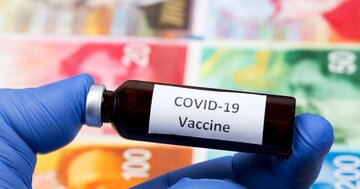
ユーロ圏の物価情勢が未曾有の悪化に直面している。12月のユーロ圏消費者物価指数は5カ月連続でマイナスとなり、リーマンショック直後に似た状況が続く。物価低迷は原油価格の落ち込みに引きずられただけなのか。危機の深奥を読み解く。

緊急事態宣言の再発令を通じて、政策に対する国民の不満が募り、それが景気の先行き不透明感につながっている。その結果、企業や家計でかつてないほど貯蓄意識が高まっている。実はこうした現状が、日本経済のリスクを緩和している側面もある。

新型コロナに振り回された2020年が終わり、2021年を迎えた。激動の時代において為替市場をどう見通すべきか、金利、株の動きも見据えながら分析する。ドル安は今後も続くのか。円はどうなるのか。そして、現在の為替に大きな影響を与える存在とは何か。大局観を持つことが重要である。

現状のドル安予想のベースには、FRBのゼロ金利政策が当面変わらない見通しと、巨額の財政赤字に伴うドルの過剰感がある。だが一方で、イエレン次期財務長官の存在がドル安を招くのではないかという意見もある。その真偽を検証しよう。

「リスクオフの円高」の威力は弱まっているが、足もとでドル/円相場は月を追うごとに下値を切り下げている。2021年に入って100円割れを起こすのではないかという懸念も高まって来た。「ドル安」という視点から、足もとの為替リスクを読み解こう。
