重石岳史
山口フィナンシャルグループ(FG)の臨時株主総会で取締役解任を諮られる前会長兼グループCEO(最高経営責任者)の吉村猛氏は、今回の解任劇をクーデターだと主張する。では、その首謀者は一体誰か。そして、なぜクーデターが実行されたのか。そこには今回の騒動の核心に迫る、根深い問題があった。吉村氏への独占インタビューで明らかにする。

山口フィナンシャルグループ(FG)で今年6月、当時会長兼グループCEO(最高経営責任者)だった吉村猛氏が事実上解任された「クーデター」事件。その吉村氏の取締役解任を諮る臨時株主総会が12月24日、山口県下関市の山口銀行本店で開かれる。株主総会直前の今、吉村氏は何を思うのか。ダイヤモンド編集部のカメラの前で吉村氏が、クーデターの真相と現在の心境を激白した。

三菱商事の新社長が近く決まる見通しだ。現職の垣内威彦社長は2022年4月で任期丸6年を迎え、退任が濃厚。垣内氏自身が「常に考えている」と言う後継者は一体誰か。最終盤に突入した後継レースに、ある異変が生じている。
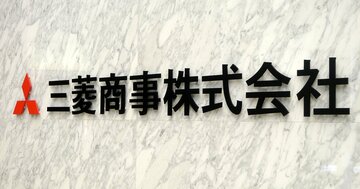
#16
野村ホールディングスは2021年4~9月期決算で、純利益が前年同期比75%減の517億円に沈んだ。競合他社の業績が堅調な中、減益幅で独り負けの決算を読み解くと、野村が抱える二大リスクが見えてくる。

山口フィナンシャルグループ(FG)の前会長兼グループCEOの吉村猛氏(現取締役)が、ダイヤモンド編集部の単独インタビューに応じた。吉村氏は12月24日の山口FG臨時株主総会で取締役解任を突き付けられているが、これを「クーデター」だと断言。解任の根拠とされる調査報告書は恣意的だとし、独立した第三者委員会による再調査を求めた。

山口フィナンシャルグループ(FG)は12月24日、臨時株主総会を開き、前会長兼グループCEOである吉村猛氏の取締役解任を株主に問う。解任の根拠とされるのが、山口FGの調査本部が作成した調査報告書だ。だが、この報告書の問題点を指摘する声が上がっている。
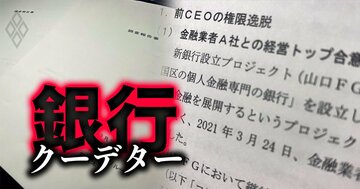
住友社員も知らない五日会、泉会、卯月会…知られざるグループ組織の全貌
『週刊ダイヤモンド』11月13日号の第1特集は『三井住友 名門「財閥」の野望』です。三井と住友。日本を代表する旧財閥系の銀行が合併し、今年20年を迎えました。この間、損保や建設など一定の業界で融合が進みましたが、三井と住友は歴史も社風も全く異なります。三井住友の知られざる20年秘史を明らかにし、二大財閥の実力を解き明かします。

山口フィナンシャルグループ(FG)で今年6月25日、当時会長兼グループCEO(最高経営責任者)だった吉村猛氏が事実上解任された“クーデター”事件。このクーデターを山口FGが事前に計画していたことを示す社内メールを、ダイヤモンド編集部が独自入手した。山口FGは事前の計画を否定しているが、虚偽説明の疑いがある。クーデターの全貌から浮かび上がったのは、著しくガバナンスを欠いた株主無視の企業体質だ。
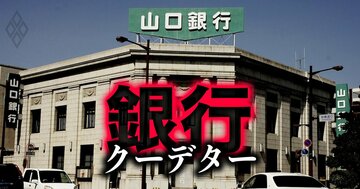
【極秘メール入手!】山口FGが虚偽説明の疑い、株主無視で前CEO解任「クーデター」の恥部
山口フィナンシャルグループ(FG)で今年6月25日、当時会長兼グループCEO(最高経営責任者)だった吉村猛氏が事実上解任された“クーデター”事件。このクーデターを山口FGが事前に計画していたことを示す社内メールを、ダイヤモンド編集部が独自入手した。山口FGは事前の計画を否定しているが、虚偽説明の疑いがある。クーデターの全貌から浮かび上がったのは、著しくガバナンスを欠いた株主無視の企業体質だ。

#18
経団連の十倉雅和会長(住友化学会長)や関西経済連合会の松本正義会長(住友電気工業会長)ら財界の顔役には、住友グループの企業経営者が目立つ。偶然の巡り合わせといえるが、住友のある特徴も財界席巻の背景にあるようだ。

#17
住友の源流である別子銅山(愛媛県新居浜市)は明治時代、乱伐や煙害で荒れ果てたはげ山だった。そこから住友は「大造林計画」を実行し、100年かけて緑が生い茂る山に再生させた。その事業を受け継ぐ住友林業には今、脱炭素化の追い風が吹く。光吉敏郎社長に、令和時代の脱炭素戦略について聞いた。
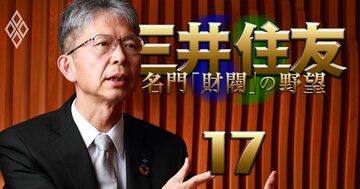
#9
住友の業祖、蘇我理右衛門が銅製錬と銅細工を開業した1590年を創業年とする住友金属鉱山は、日本の上場企業で指折りの長寿企業だ。現在の住友グループの“長兄”とも称される金属鉱山の野崎明社長に、400年を超えて受け継がれる住友の事業精神を語ってもらった。

#6
旧財閥の名前を冠していないため認知度は低いが、電機メーカーの東芝と日本電気(NEC)はそれぞれ、三井系の二木会と住友系の白水会に参加する企業だ。この2社には財閥との「100年の因縁」ともいうべき共通点がある。

#4
三井と住友という二大財閥系列の銀行同士が合併した今世紀初頭。商社業界においても、三井物産と住友商事の合併がたびたび取り沙汰されてきた。伊藤忠商事と三菱商事の「2強時代」といわれる今、時価総額で業界3位と4位に甘んじる商社同士の「大合同」は起こり得るのか。
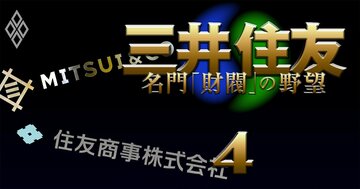
#2
2001年に旧住友銀行と三井系の旧さくら銀行が合併し、誕生した三井住友銀行。合併後の20年は、全く異なる出自と社風を持った旧財閥系銀行同士の「相克」と「融和」の歴史でもある。OBら関係者の証言を基に、銀行が歩んだ知られざる20年の歴史をひもとく。

新聞印刷用の輪転機最大手、東京機械製作所の株式を4割近くまで買い増した投資会社、アジア開発キャピタル。そのファンドを率いるアンセム・ウォン氏が初めてメディアのインタビューに応じ、買収の狙いを明かした。

東証プライム「流通時価総額100億円」の壁、“逆転合格”候補の見抜き方
『週刊ダイヤモンド』9月18日号の第1特集は「東証再編 664社に迫る大淘汰」です。東京証券取引所の1部、2部、マザーズ、JASDAQから成る市場体制が来年4月に廃止され、プライム、スタンダード、グロースの3市場に再編されます。再編で淘汰される企業と生き残る企業はどこか。企業、投資家、金融機関、そして再編を仕掛ける東証――。さまざまな思惑が交錯する大騒動の最前線に迫ります。
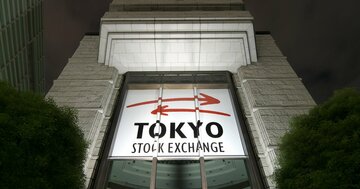
#22
来年4月に発足するプライム市場の基準を満たしていない東証1部上場企業は600社を超える。その大半が流通株式時価総額100億円に達していない中堅・中小企業だ。数十億円規模の時価総額しかない企業は、一体どのようにして高過ぎる壁を越えようとしているのか。
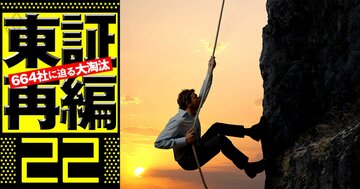
#18
東京証券取引所の山道裕己代表取締役社長がダイヤモンド編集部のインタビューに応じた。山道社長は、今回の市場再編後について「企業価値をより向上してもらえるような基準を設けるかもしれない」と述べ、上場基準のさらなる厳格化の可能性を明かした。
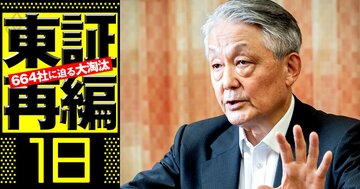
#13
日本を代表する株価インデックスであるTOPIX(東証株価指数)の構成銘柄は今、東証1部上場の全銘柄が対象だ。この構成銘柄の見直しが始まる。タイムリミットである2023年10月までに流通株式時価総額100億円に達しない銘柄は、TOPIXから完全除外されることになる。
