山口 周
【あなたは大丈夫?】優秀だったのに「40代で急に転落する人」の行動・ワースト1
優秀だったのに「40代で急に転落する人」の行動パターン・ワースト1

【心理学が証明】「人生の修羅場」で本当に強い人に共通する特徴・ベスト1
【心理学が証明】「人生の修羅場」で本当に強い人に共通する行動・ベスト1 「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

20代で成功した人の「その後」…消える人と長く活躍する人を分ける行動とは?
「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

いや怖すぎる…エリートだったのに「人生も家庭も失う人」の特徴・ワースト1
「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

こりゃ背筋が凍る話だ…人生で「家族より仕事を優先した人」の末路
「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略——自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

「人生を後悔している人」に共通する時間の使い方、ワースト1
「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略——自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

【あなたは大丈夫?】優秀だったのに人生後半で転落する人の特徴・ワースト1
「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。

今「優秀な人材」は一気に価値を失う! 今後活躍できる「ニュータイプ」の条件とは?【書籍オンライン編集部セレクション】
個人も企業も思考のアップデートが求められている今、どのようにオールドタイプ人材からニュータイプ人材へとシフトすればいいのか。大人気の山口周氏が教える、これから活躍できる人材の条件とは?

「役に立つだけの人」は淘汰される…今の時代を生き抜くのに必要なのは?【書籍オンライン編集部セレクション】
発売直後からベストセラーとなっている『ニュータイプの時代』。この新刊について、著者の山口周氏と、IT批評家の尾原和啓氏が語る対談イベントが実現。今起こっている変化の本質とは?この先有効な生存戦略とは?

山口周が断言!もはや「独学できない人」は生き残れない致命的なワケ【書籍オンライン編集部セレクション】
今ほど「独学」の重要性が増す時代はない。産業モデルが変わりつつある今、自ら学び取る力が、この先最強のスキルとなる。
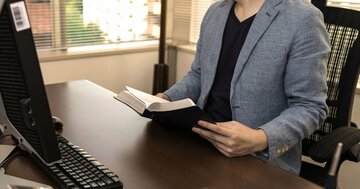
【山口周・特別講義】「こんなはずじゃなかった…」そんな人が自分を見失わず、したたかに生きる方法
コロナ禍で働き方や生き方を見直した――。そんな人たちが今「希望の書」として再び注目する山口周氏の『ニュータイプの時代』から、生きづらさに悩んでも自分を見失わず、したたかに生きる方法をご紹介する。

【山口周・特別講義】「残酷な勝ち抜きゲーム」夢中になる人ほど見落としていること
コロナ禍で働き方や生き方を見直した――。そんな人たちが今「希望の書」として再び注目する山口周氏の『ニュータイプの時代』から、「残酷な社会で勝ち抜くゲーム」に夢中になる人が見落としがちなことをご紹介する。

【山口周・特別講義】平均寿命を伸ばしても、幸せになれない理由
コロナ禍で働き方や生き方を見直した――。そんな人たちが今「希望の書」として再び注目する山口周氏の『ニュータイプの時代』から、私たちが目指すべき新しい指標についてご紹介する。

【山口周・特別講義】いかなる状況でも正しい判断ができる「意外な資質」
コロナ禍で働き方や生き方を見直した――。そんな人たちが今「希望の書」として再び注目する山口周氏の『ニュータイプの時代』から、混迷の時代に正しい判断をするためのヒントをご紹介する。
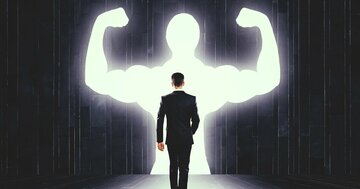
【山口周・特別講義】『ジョーズ』『ダイ・ハード』田舎刑事が最後に解決する「意外な意味」
コロナ禍で働き方や生き方を見直した――。そんな人たちが今「希望の書」として再び注目する山口周氏の『ニュータイプの時代』から、アメリカと日本で大きく異なるリーダーシップのあり方についてご紹介する。

【山口周・特別講義】「人生100年時代のヒント」アインシュタインが実践!驚きのキャリア戦略
コロナ禍で働き方や生き方を見直した――。そんな人たちが今「希望の書」として再び注目する山口周氏の『ニュータイプの時代』から、人生100年時代のキャリア戦略のヒントをご紹介する。

【山口周・特別講義】「長く、マラソン化する人生」最終的に成功した人たちの共通点
コロナ禍で働き方や生き方を見直した――。そんな人たちが今「希望の書」として再び注目する山口周氏の『ニュータイプの時代』から、ギブ&テイクの最終的な利得の差についてご紹介する。

【山口周・特別講義】「学び」を活かせる人、活かせない人の決定的な違い
コロナ禍で働き方や生き方を見直した――。そんな人たちが今「希望の書」として再び注目する山口周氏の『ニュータイプの時代』から、一億総学び社会となった今、知識や経験のアップデートのヒントをご紹介する。

【山口周・特別講義】直感と論理をしなやかに使い分ける2つのヒント
コロナ禍で働き方や生き方を見直した――。そんな人たちが今「希望の書」として再び注目する山口周氏の『ニュータイプの時代』から、直感と論理をしなやかに使いこなす2つのヒントをご紹介する。

【NHKの特集で「ニュータイプ」が話題!】山口周が語るアフターコロナにニュータイプへの転換が必要な理由
NHKの「ニュースウォッチ9」で取り上げられ、「アフターコロナ」の思考・行動様式を予言した書として再び話題になっている、山口周氏の著書『ニュータイプの時代――新時代を生き抜く24の思考・行動様式』。コロナによるパンデミックでこれまでの価値観が通用しなくなっている今、新しい時代への転換を担えるニュータイプ人材がますます求められている。果たして今、どんな変化が起きているのか。同書から一部を抜粋して、特別公開する。
