永吉泰貴
#6
医療データの利活用の意義から個人情報保護法の問題、さらにはDeNA報道まで情報法制研究所(JILIS)副理事長の高木浩光氏に見解を聞いた。高木氏は「医療データを持っている組織に二次利用の監督能力を期待しても、無理がある」と述べ、DeNAの「医療データ目的外利用」報道で浮上した構造的な課題を指摘した。
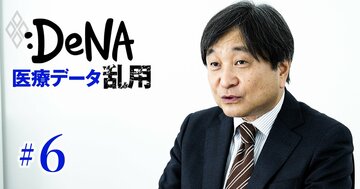
#5
ディー・エヌ・エー(DeNA)が10年もの間抱えている課題が、ゲーム事業依存からの脱却だ。それを象徴するのが社長人事である。現在の社長兼CEO(最高経営責任者)は、横浜スタジアム社長や横浜DeNAベイスターズ社長を歴任した岡村信悟氏だ。そしてDeNA が、スポーツ事業以上に高い利益目標を掲げているのがヘルスケア・メディカル事業である。そこに訪れた「医療データ目的外利用」が、次期社長レースの波乱要因にもなっている。
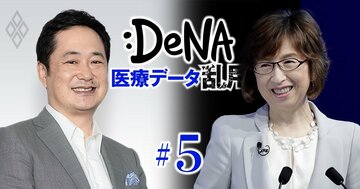
#4
コンプガチャ問題にWELQ騒動と、世間を揺るがす社会問題を引き起こしてきたディー・エヌ・エー(DeNA)。WELQ騒動後も企業体質を変えられず、自治体の医療データを目的外に利用してしまったのはなぜか。3年前の契約書で突如削除された条文と、複数の元子会社社員による証言を基に問題の構造を分析すると、WELQ騒動の調査報告書で指摘されていた課題を依然払拭できていなかったことが判明した。
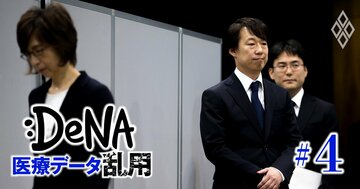
#3
DeNAが自治体から取得した医療データの目的外利用に違法性はあるのか――。ダイヤモンド編集部が入手した契約書を基に、医療データの個人情報保護に詳しい水町雅子弁護士に見解を聞いた。水町弁護士は「委託先は委託業務を超えて匿名加工情報を独自利用できない」と述べ、個人情報保護法に違反する可能性を指摘した。

#2
ディー・エヌ・エー(DeNA)はなぜ、医療データを目的外利用するに至ったのか。販売先の生命保険会社へのアプローチを調べると、その動機が見通せる。ダイヤモンド編集部が入手した実際の生保向け営業資料を基に、医療データの取得過程に無理が生じた原因を解明する。
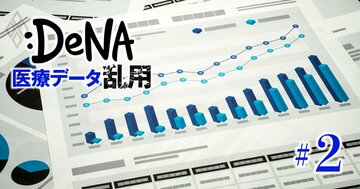
#1
ディー・エヌ・エー(DeNA)の子会社が自治体から取得した医療データについて、「製薬会社や保険会社に有償で提供した」と自治体に説明していることが分かった。DeNAはこれまで目的外利用の疑惑を否定していたが、自治体に対しては有償提供の事実を一転して認めた形だ。ダイヤモンド編集部は情報公開請求でDeNAと自治体の契約書を入手し、疑惑を検証した。
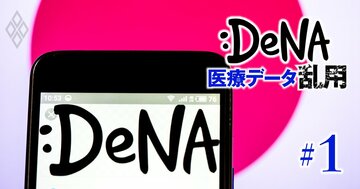
予告
DeNA「医療データ乱用」問題、目的外利用が起きた“構造”を徹底解明【内部資料多数入手】
コンプガチャ問題にWELQ騒動と、数々の社会問題を引き起こしてきたディー・エヌ・エー(DeNA)。金目の新領域に飛び付き、モラル面に問題のある企業体質は不変だ。2023年12月18日、ダイヤモンド編集部はDeNAの医療データ「目的外利用」疑惑を報じた。その後、自治体への取材で分かったのは、目的外利用は疑惑ではなく事実ということだ。開示した契約書については、個人情報保護が専門の弁護士から違法の可能性も指摘されている。DeNAの「医療データ乱用」で浮き彫りになった構造問題と、今後、医療データの利活用が適切に推進されるための処方箋を提示する。

1月19日、全国トップ地方銀行の横浜銀行が、初任給を26万円へと4万円引き上げる方針を固めた。現時点では静観する地銀も、いよいよ本格化した初任給引き上げラッシュ「第2弾」に今後追随する公算が大きい。

番外編
貸出金利の上昇により銀行が利益を得る裏で、事業会社の負担は増す。特に有利子負債が大きい企業ほど、金利上昇時の負担額は跳ね上がることになる。その衝撃度をランキングにした。

#12
金利上昇もどこ吹く風、愛知県では“名古屋金利”と称されるほどの熾烈な低金利競争が続いている。そんな金融激戦区で、愛知銀行&中京銀行の統合に次ぐ再編機運が加速している。名古屋銀行の頭取人事をひもとくと、その正体が浮かび上がった。

#11
日本銀行の政策金利は、四半世紀に渡りゼロ近辺で推移してきた。ようやく金利のある世界も見えてきたが、そのとき、企業への貸出金利はどう上がっていくのか。超基本のメカニズムと変動要因を解説する。

#4
銀行業界は、金利上昇の恩恵を最も受けるといわれる。そこで、二つの金利上昇ケースを想定し、メガバンクと大手地方銀行の純利益に与える影響を実名試算した。その結果、金利上昇が追い風になる銀行と、影響が限定的な銀行が明らかになった。また、17年前の金利上昇時と今の金融環境を比較すると、銀行は金利上昇の追い風に乗れない可能性があることも分かった。
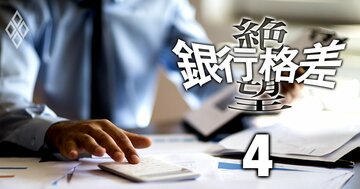
#27
2024年は本格的な金利上昇への転換点の年だ。とはいえ、20年以上低金利が続いた日本では、「金利のある世界」が想像しにくいのではないだろうか。来る「金利のある世界」が企業や私たちの生活にどのような影響を与えるのか、試算を基にした豊富なグラフ付きの大図解で解説しよう。

#13
中国経済対談の前編では、24年の中国経済の成長率が鈍化する予測について語ってもらった。要因は、雇用情勢の悪化と不動産リスクをもたらした政策の失敗だ。日本が歩んだ「失われた10年」に中国も向かってしまうのか。その可能性と回避シナリオについて、中国経済の専門家2人が前編に続いて徹底討論する。

#11
中国経済が正念場を迎えている。二桁成長が当たり前だった時代はとうに終わり、今や低成長やデフレに陥るリスクもささやかれている。果たして24年はどの道を進むのか。「失われた10年」への突入も指摘される中国経済の行く末を専門家2人が討論する。本稿は前編、後編の前編。

#9
国内の物価上昇率は、依然として2%を優に上回る高い水準が続いている。2024年の物価はどの方向に向かうのか。物価研究の第一人者である渡辺努・東京大学大学院教授に、具体的な数値でメインシナリオと波乱要因を聞いた。
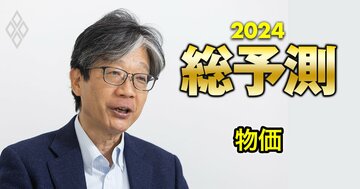
#1
2023年前半に日本株は大きく上昇したものの、その後は上値の重い展開が続いた。果たして24年中の史上最高値更新はあり得るのか。株価水準の見通しや注目テーマを、8人の専門家に聞いた。

DeNAが、自治体から提供された診療報酬明細書などの医療データを、製薬会社に販売するなど本来の目的以外で利用している疑いがあることが、ダイヤモンド編集部の取材で分かった。複数の自治体が調査に乗り出している。事実であれば、個人情報保護法に抵触する可能性もある。
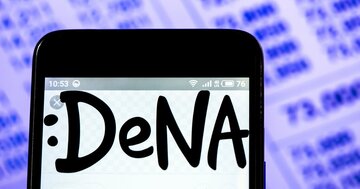
#17
役職定年による給料減を挽回できる「ライセンス認定制度」を、大和証券が8年ぶりに廃止していたことがダイヤモンド編集部の取材で分かった。経済同友会の政策提言資料でも度々評価されてきた同制度のどこに問題があったのか。この廃止により、これから役職定年を迎える氷河期世代は、学習実績ではなくパフォーマンスによって処遇が決まることになる。

#8
就職氷河期を通じて激増したのが非正規雇用者だ。日本では長らく正規・非正規の待遇格差が続いたものの、ここにきて風向きが少し変わっている。その象徴が、イオンの中核会社であるイオンリテールだ。同社は昨年から今年にかけて、正社員とパートタイマーの待遇を時間当たりで均等にした。ダイヤモンド編集部が入手した新資格体系と新給与テーブルを見ると、高いスキルを持つパートの待遇を改善し、徹底的に戦力化しようとしている狙いが浮かび上がった。
