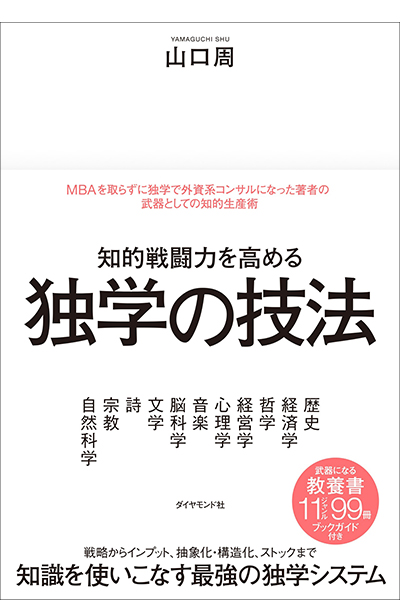レヴィ・ストロースは、南米のマト・グロッソのインディオたちを研究し、彼らがジャングルの中を歩いていて何かを見つけると、その時点では何の役に立つかわからないけれども、「これはいつか何かの役に立つかもしれない」と考えてひょいと袋に入れて残しておく習慣があることを『悲しき熱帯』という本の中で紹介しています。
そして、実際に拾った「よくわからないもの」が、後でコミュニティの危機を救うことになったりすることがあるため、この「後で役に立つかもしれない」という予測の能力がコミュニティの存続に非常に重要な影響を与えると説明しています。
そしてこの不思議な能力、つまりあり合わせのよくわからないものを非予定調和的に収集しておいて、いざというときに役立てる能力のことを、レヴィ・ストロースはブリコラージュと名付けて近代的で予定調和的な道具や知識の組成と対比して考えています。
ブリコラージュという言葉は、なんだか高尚な現代思想のコンセプトのように使われる傾向がありますが、なんということはなく、フランス語の「日曜大工」という意味です。
フランスのホームセンターに行くと、いわゆる「DIY」のコーナーにはブリコラージュと書かれているくらいですから、ごくごく普通に使われている言葉だと言っていい。
つまり、本来の文脈に戻して考えてみれば、日曜大工のように、自分で何かを作るということを前提にして、何の役に立つかわからないけれども、この材料・道具は家に置いてあると後々に便利そうだという感覚です。
これを独学のシステムに当てはめて考えてみれば、いますぐ何の役に立つかはわからないけれども、この本には何かある、この本はなんだか知らないけどスゴイ、という感覚が大事だということです。
今日とか明日に役に立つのかと聞かれれば、それはなんともわからない。だけれども、自分の中の何かと反応している、なんとも説明できないのだけど、この本を読まずにいられない、そんな感覚です。
なんともふわふわとした表現で申し訳ないのですが、この感覚はとても重要だと思っています。極論すれば、読書をどれだけその人のユニークな知的生産につなげられるかどうかは、この「この本には、なにかがある」という感度の強弱によって大きく左右されてしまいます。
この感覚は、ハンターが茂みの向こう側に獲物の存在を感じ取る感性と言い換えられるかもしれません。知的な営みである読書においても、こういった野性的な感性は必要だと思います。
話を元に戻せば、つまりブリコラージュというのは日曜大工だという話でしたが、これはこれで示唆深いと思うのです。というのも、日曜大工というのはつまり、最終的に「作る人」は自分だということなんですね。簡単なものでも、でき上がりが不器用でもかまわない、ただ、お仕着せのものではなく、あくまで自分が集めた材料で作り上げた「なにか」ができ上がるということ。
「なんとなく、これは役に立つかもしれない」という感覚で集められた道具が、後でいろいろと組み合わされることで、コミュニティの危機を回避する助けになる。同じような感覚が、独学にも必要だということです。
できるのは、後からつなぎ合わせることだけです。だから、我々はいまやっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかない。
――スティーブ・ジョブズ(スタンフォード大学の卒業スピーチより)