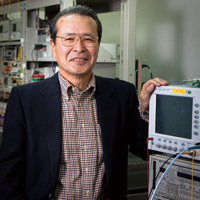 |
| ファイベスト会長 前田 稔(撮影:加藤昌人) |
「とても、間尺に合わない仕事だと思った」
2005年秋、日立製作所が出資する光部品ベンチャー、オプネクストの最高執行責任者をしていた前田稔は、人生の大きな転機を前に、逡巡していた。
「ファイベスト社長の職を引き受けてもらえないだろうか」と、その大株主であるファンドからヘッドハンティングされたのだ。日立へ入社してから、一貫して光通信・光部品の研究開発や事業化に携わった前田の「知見」と「業界の人脈」を評価されてのことだった。
ファイベストは、光通信分野の基幹デバイスを開発・製造・販売するベンチャーとして、富士通の技術者が中心となって設立された独立系ベンチャーだ。02年の設立以降、3期連続の営業赤字に陥っており、まさしく倒産の危機にあった。
ヘッドハンティングとは聞こえがいいが、“火中の栗を拾う”危険を伴う転身だ。だが、ファンドは執拗だった。「なんとかマネジメントを立て直してほしい」という再三の申し出に根負けして、「自身の経験が再建に役立つならば引き受けよう」と、覚悟をした。自分の人生を形作ってくれた何物かへの恩返しの気持ちもあった。還暦を過ぎた62歳の再スタートだった。
日立時代に2度のベンチャー事業経験
経営センスが磨かれた
社長としての初仕事は、金策に奔走することだった。
金融機関や日米欧のファンドを日参しては、「ファイベストにはマネジメント力は欠如していたが、研究開発力の高さや人的ネットワークの豊富さでは、業界随一のレベルだ。必ず再生してみせる」と熱弁を振るった。はたして、7億5000万円の出資金をかき集めた。
次に着手したのは、経営基盤の構築だ。当時のファイベストは技術者ばかりの“寄り合い所帯”で、企業経営に精通した管理部門の人材に乏しかった。原価を低減し、品質を管理し、納期を厳守するといった製造業のいろはすら身につけていなかった。経営を成り立たせる基本ルールも整備されていなかった。つまり、「企業の体を成していなかった」。
当然ながら、各事業部の責任の所在は明確ではなかった。「開発コストがかさめば開発部の責任、過大の製品在庫を抱えれば営業部の責任、というごく当たり前の原則を徹底した」。基本ルールと規律を覚えた社員たちは次第に一丸となって、予算を達成しようとする企業体質に転換した。
前田自身は根っからの技術者である。だが、企業を経営する技術は、日立時代に培っていた。38年間を日立グループという大企業体で過ごした技術者にしては珍しく、2回もベンチャー事業の経営に携わっている。
最初は、社内ベンチャー事業の担当責任者である光事業推進本部長に就任した。日立の連結従業員数約40万人のなかで、本部従業員は100人で小規模だった。それでも、本社の予算審議会で、累積した赤字の原因を経営幹部から厳しく追及される過程で、企業経営の手法を初歩からオンザジョブで学んだ。







