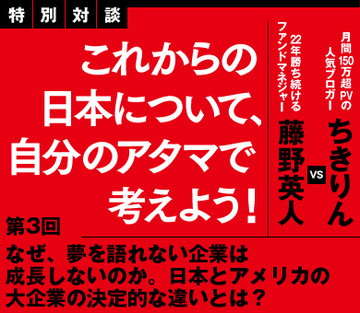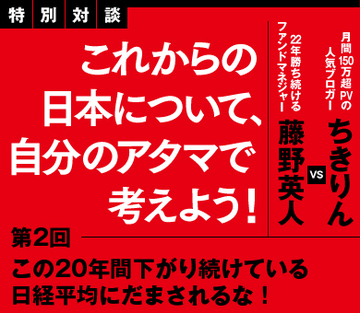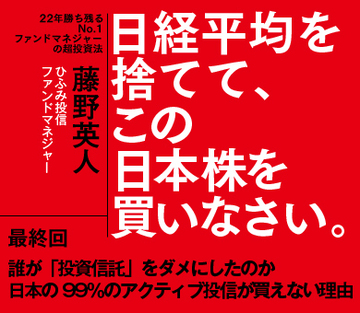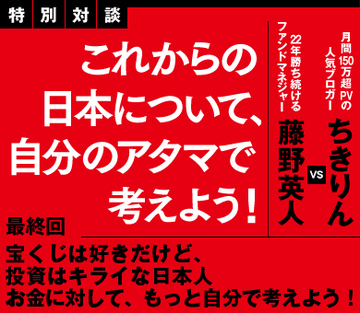雇用の流動性のなさが、
会社嫌いを増やしている(藤野)
ちきりん ただ、あえて違う視点でみてみると、そういうネガティブな労働観が増えてきたのって、ある意味グローバルスタンダードともいえませんか?
20年くらい前まで、日本企業では全社員がまじめに日経新聞を読んでました。なぜなら、全員が自分も将来、社長や経営者になれるかもという幻想を抱いていたからです。だから皆、つらくても頑張って働いていた。
一方その頃、私がアメリカのビジネススクールに行っていた時なんですが、マネージャーの仕事として「工場で働く人たちが、当日になって仕事をドタキャンする、いわゆる“ポカ休”ですが、それをいかに減らすか」というテーマで議論するんです。ケース資料には「ポカ休が20%もあるので10%にするにはどうしたらいいか」みたいに書いてあるんですけど、当時の私の感覚としては、ケースの事例とはいえ「ポカ休が20%もある」ということがまず信じられませんでした。
だけど、アメリカのマネージャーにとってはそれが切実な問題なんです。なぜならば、当時のアメリカの工場では、朝起きて気分悪いから仕事に行かないとか、今日は子どもと買い物に行きたくなったからそちらに行くとか、簡単に休んでしまう人が実際に多かったんですよね。その人たちは時給で働いているだけだから、休んでも出世に響くわけでもないし、会社にたいして何のコミットもありません。だからポカ休を簡単にやるんですよ。
アメリカでは、そういうポカ休を平気でやる層が一定以上いるという前提で会社を経営する、そのことが当時の私には驚きでした。でも、今や日本でもそういう労働者層が現れてきた、とも考えられるかな、と思うんです。一生懸命働いても報われない。どうせ時給で働いているだけだ。だったら、働きたい時間だけ働けばいいや、というような風潮です。ここでは労働が歓びとか充足感をもたらすもの、という概念は全然なくて、たんに生活費を得るため仕方なくやっていること、となってしまっています。
藤野 それもあるかもしれませんが、日本の労働環境は特殊だということがありますよね。それは「雇用の流動化がない」という面です。
ちきりん ああ、なるほど。正社員に関してはそこが大きな違いですね。
藤野 たとえば、日本人、中国人、ドイツ人、イギリス人、アメリカ人などに「あなたの会社好きですか」という統計を取った時に、「好きじゃない」という答えはいつも日本がトップです。逆に、アメリカや中国は8割の人が大好きと言っているんですね。なぜそうなるかというと、アメリカや中国だと会社が嫌なら辞めちゃうから。もしくは辞めさせられちゃうからです。
だから、今働いている会社については、ある程度気に入って働いているという人が多いんですね。それに対して日本は、会社の中はある種、家族的な関係になり、一度中に入ると辞めるという選択肢を持ちづらい。
ちきりん たしかに私の務めていた外資系企業でも、仕事が嫌な人はさっさと辞めちゃうので、残っているのはその会社や仕事が好きな人ばかりでした。日本の大企業って誰も辞めないので、少々仕事が合わないと思っても会社を辞めるのが怖くなるんですよね。
藤野 そう、すごく怖いんです。それで、会社に対して不平不満をいう。不平不満を言っても辞めさせられないという面もありますが。それで結果的に、会社が嫌い、あまり好きじゃないという人が増えるんです。
ちきりん 逃げられないと思うから、よけいに不満がたまっているんですね。
藤野 そうです。自分が選択してこの会社にいるという意識がない。すごく受け身なんですよ。本当はどこかの時点で、自分で決断してここの会社にいるのに、働かされているという受動的な意識が強い。でも嫌だったらやめて次の選択をするということが難しい。
ちきりん そういう受け身の感覚にならざるを得ないというのは、かわいそうですよね。雇用が流動化されないという問題もあるし、社員を、主体的に働くのではなくて受動的に働く人としてしか認識しない企業が多いんですよね。あの「辞令による部門移動お任せ制度」もすごい制度だと思いますし。
藤野 そうです。これはどっちが悪いという話ではなくて、働く側の問題と同様に会社サイドの問題も必ずあるわけです。これは会社側の形式的な真面目さの弊害が出ているともいえます。自分たちが社会の中でどのような価値を生み出していくのか、そのために社員とどうコミュニケーションをとっていくのかということを真剣に考えている会社は少ない。
会社は「長期的に御恩と奉公的な関係で全てを投げ出して働きなさい」ということを暗に要求しているし、若い人たちは「それは嫌だ」と思っている。その意識のかい離はすごい大きい。