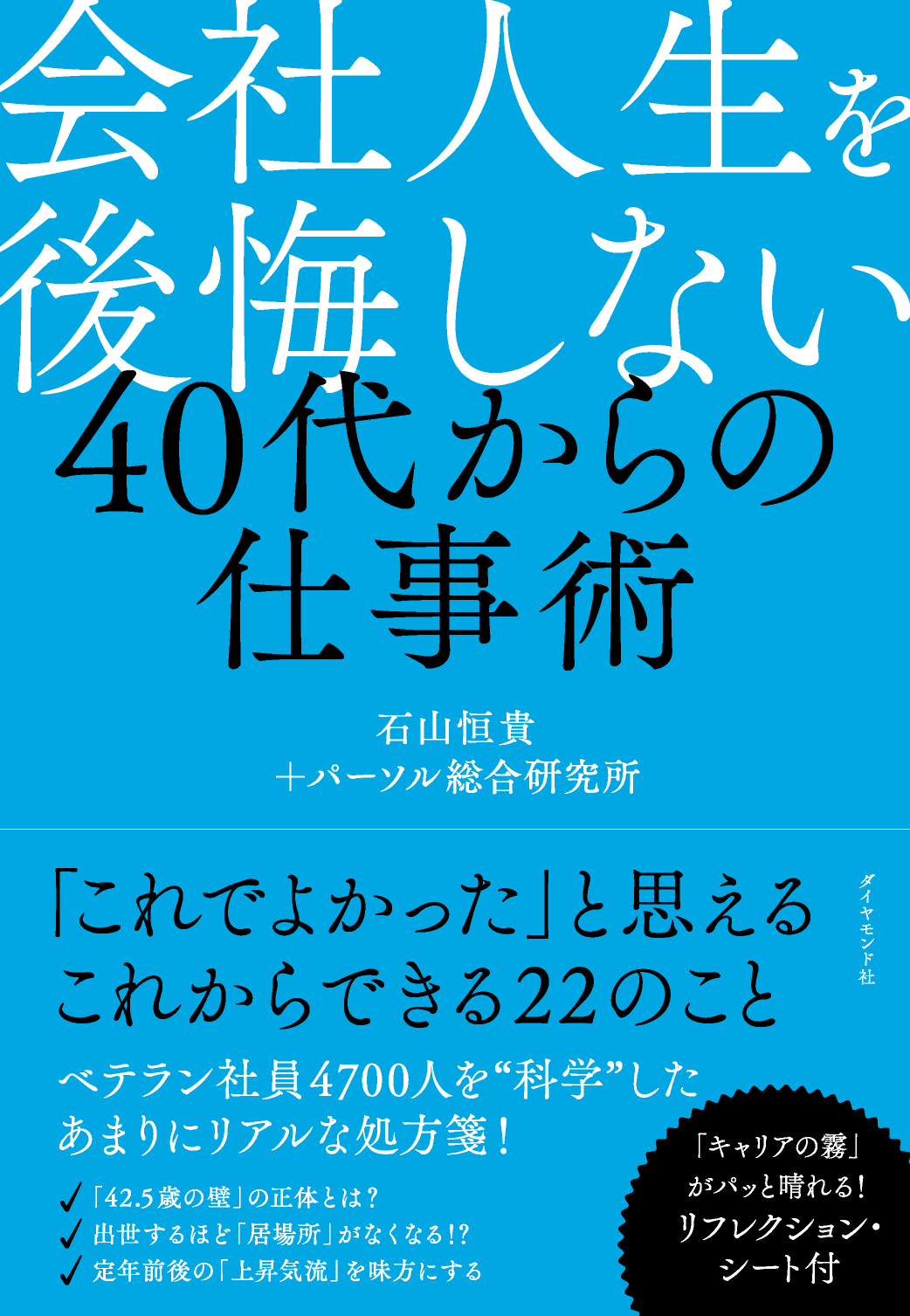「年齢」を基準にした理不尽な人事
一方、50歳前後にある「ミドル・シニア最大の谷」には、どんな原因があるのでしょうか? 結論から言えば、ここにはポストオフ(役職定年)の影響が考えられます。ポストオフとは、ある一定のタイミング(年齢)で、その時点での役職を退任する仕組みです。
これが社内の人事制度としてルール化されている企業もあり、50歳とか55歳といった特定の年齢で、役職から外される事例は、大企業を中心にかなり広く見られます。また、明示的なルールとしてあるわけではないにしろ、50代半ばあたりをリミットにして、その時点での役職を解くようにしている企業も少なくないでしょう。
年齢を基準に役職の人事を決めるというのは、国際的に見てもわが国独自の慣習だと言えます。本書では、制度的なもの(いわゆる「役職定年制」)と非公式な退任とをひっくるめて、「ポストオフ」と呼ぶことにします。
役員などに昇進する人以外は、ほとんどがこのポストオフの対象になるわけですが、この仕組みには、後輩に道を譲らせてポストを確保する以外にも、給与を下げて人件費を調整できるといった会社側のメリットがあります。役職を解かれた人は、一般社員に戻るほか、部下なしの管理職(担当部長など)になったり、関連会社へ出向したりするケースなども見られます。
「出世というニンジン」が効かなくなる瞬間
では、なぜポストオフによって、「ミドル・シニア最大の谷」が発生するのでしょうか?
いちばん典型的なのは、目標の喪失でしょう。企業で働く人たち、とくに一定の役職に上がっている人たちは、さらに上の役職に到達することをモチベーションの原動力にしています。ポストオフとは、こうした職位上昇のインセンティブが機能しなくなるタイミングなのです。
第一の「谷」をなんとかくぐり抜け、企業が提供するキャリアアップ・ストーリーに乗り続けていた人たちも、ここで突然、夢を断たれることになります。
「まだ副部長だけど、がんばれば部長に昇進できるかな……」
そうした淡い期待が"ゼロ"になるのが、このポストオフです。
そう考えると、50歳前後のポストオフが、最大の「谷」を生み出すのは、それほど不思議ではありません。企業のストーリーに乗って「昇進・昇格」を目標にしてきたのに、定年前のタイミングでいきなりすべてが"ご破算"になってしまうからです。
「会社にいきなりハシゴを外された!」
そう感じる人も多いはずです。ポストオフを経験した人が、何を目標にがんばればいいのかを見失い、パフォーマンスを低下させてしまうのは、きわめて自然なことなのです。
邪魔をするのは「賃金」よりも「プライド」
ポストオフがミドル・シニアの谷を生み出す理由は、これ以外にもたくさん考えられます。たとえば、賃金の低下というのはどうでしょうか。
いわゆる成果主義の導入からかなりの時間が経ったとはいえ、日本企業の多くでは依然として「年功」の要素が賃金に反映されています。個人の仕事内容を賃金に反映させる「役割主義」などの導入を進める企業も増えていますが、給与アップや昇進・昇格には、入社年次に応じた管理が併用されているのが実態でしょう。
これは、最も極端な見方をすれば、若いころからパフォーマンスが変わっていなかったとしても(あるいは、パフォーマンスが落ちていたとしても)、年齢の上昇とともに報酬も上昇していくということを意味します。
ポストオフで管理職を外された人は、このタイミングで初めて「給料が下がる/上がらなくなる」という経験をします。
しかし、むしろ働く人にとってつらいのは、次のような経験ではないでしょうか?
「自分よりはるかに若い社員が、自分のマネジメントを担当することになった」
ここでも通底しているのは、新卒一括採用を発端とする「年功」の文化です。ポストオフというのは、自分より早く入社した先輩、自分と一緒に入社した同期、自分より後に入社した後輩……というこのシンプルな秩序が最も大きく崩れるタイミングでもあります。

法政大学大学院 政策創造研究科 教授
一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻修士課程修了、法政大学大学院政策創造研究科政策創造専攻博士後期課程修了、博士(政策学)。一橋大学卒業後、NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。「越境的学習」「キャリア開発」「人的資源管理」などが研究領域。人材育成学会理事、フリーランス協会アドバイザリーボード、早稲田大学大学総合研究センター招聘研究員、NPOキャリア権推進ネットワーク授業開発委員長、一般社団法人ソーシャリスト21st理事、一般社団法人全国産業人能力開発団体連合会特別会員。主な著書に、『越境的学習のメカニズム』(福村出版)、『パラレルキャリアを始めよう!』(ダイヤモンド社)、主な論文に"Role of Knowledge Brokers in Communities of Practice in Japan." Journal of Knowledge Management 20.6 (2016): 1302-1317などがある。