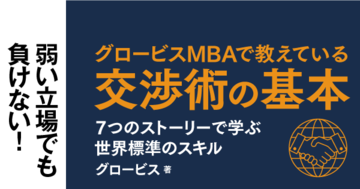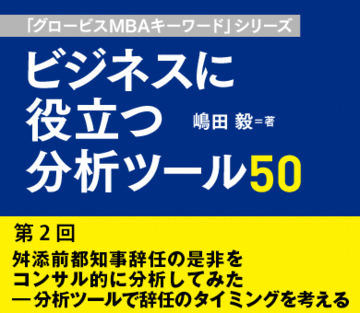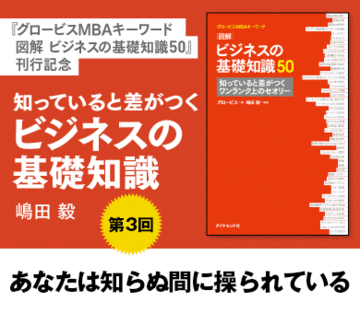なぜ、相手は「対決姿勢」を強めるのか?
 ライアン・ゴールドスティン
ライアン・ゴールドスティンクイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所東京オフィス代表。カリフォルニア州弁護士
1971年シカゴ生まれ。1910年代に祖父がアメリカに移住した、ポーランドにルーツをもつユダヤ系移民。ダートマス大学在学中に日本に関心をもち、金沢にホームステイ。日本に惚れ込む。1993~95年、早稲田大学大学院に留学。98年、ハーバード法科大学院修了。ハーバードの成績トップ5%が選ばれる連邦判事補佐職「クラークシップ」に従事する。99年、アメリカの法律専門誌で「世界で最も恐れられる法律事務所」に選出された、クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所(現)に入所。2005年に同事務所パートナーに就任。カリフォルニア州の40歳以下の優秀な弁護士に贈られる「Top20under40」を35歳で受賞する。専門は国際的ビジネス・知財訴訟、国際仲裁。「日本の味方になりたい」という願いを叶えるために、日米を行き来しながら一社ずつ日本企業のクライアントを増やし、2007年に東京オフィスの開設を実現。2010年に日本に常駐するとともに東京オフィス代表に就任した。これまで、NTTドコモ、三菱電機、東レ、丸紅、NEC、セイコーエプソン、リコー、キヤノン、ニコン、円谷プロなど、主に日本企業の代理人として活躍するほか、アップルvsサムスン訴訟など国際的に注目を集める訴訟を数多く担当。また、東京大学大学院法学政治学研究科・法学部非常勤講師、早稲田大学大学院、慶應義塾大学法科大学院、成蹊大学法科大学院、同志社大学法学部の客員講師などを歴任。日本経済新聞の「今年活躍した弁護士(2013年)」に選ばれたほか、CNNサタデーナイトのレギュラーコメンテーターも務めた。
私の経験をお話ししよう。
日本のプラスチック・メーカーの代理人として、アメリカの小さなギフトショップとの交渉を担当したときのことだ。
トラブルの原因となったのは、メーカーが生産する際に発生する半端なプラスチック・シートを、安価かつ安定的にギフトショップに供給するという契約だった。ギフトショップは、半端ではあるが質の高いシートを、商品のラッピング・デコレーションに使おうとしたのだ。
ところが、メーカーにとっては重要な契約ではなかった。ゴミとして廃棄していたものを買い取ってくれるのだから、タダ同然の値段ではあったが、「やらないよりはいいだろう」という程度の認識だったのだ。そのため、生産調整によって半端なシートの量が減ったときなどには、規定の量を供給しなかったのだ。
その度に、ギフトショップは契約の履行を要求した。
しかし、メーカーは十分な対応をすることができなかった。度重なる契約不履行に、ついにギフトショップは激怒。多額の損害賠償請求を突きつけてきたのだ。これに、メーカーも態度を硬化させた。契約内容に比して、あまりにも多額の賠償請求だったからだ。
その結果、交渉はお互いに譲らない状況に突入。ギフトショップから訴訟に打って出るという通告を受けて、急遽、メーカーから私に代理人として交渉してほしいと依頼があったのだ。
交渉は難航した。
メーカーは、契約不履行は事実だから賠償金は支払うつもりだった。ただし、支払うべき金額は、多くても請求金額の30%程度と算出していた。私から見ても、その算出根拠は合理性があると思われた。ギフトショップの請求額が、あまりにも非常識だったのは事実なのだ。
しかし、私が丁寧に説明しても、ギフトショップは一円たりとも請求額を下げようとはしなかった。むしろ、理路整然と説明すればするほど、訴訟に打って出ると強硬姿勢を強めるのだ。
「問題の本質」を見極める
なぜか?
私は、怒りに震える彼らの言葉に耳を傾けるほかなかった。
そして、わかったのだ。彼らにとって、メーカーとの契約は「夢」だった。質の高いシートを使って、工夫を凝らしたデコレーションをすることで顧客に喜んでもらう。それが、創業以来の「夢」だったのだ。
ところが、メーカーは契約を十分履行することができなかった。
いや、その対応から、ギフトショップは、「自分たちにとって、この契約はたいしたものではない」というのがメーカーの本音だと受け取ってしまった。そして、彼らは、自分たちの「夢」を足蹴にされるような感覚を覚え、深く傷つき、怒りを爆発させたのだ。
彼らも、自分たちの請求額が非常識なのは重々承知していた。しかし、それ以外に、彼らの怒りをぶつける方法がなかった。逆に言えば、彼らにとっては「お金」の問題ではなかった。実際、裁判になれば私たちが算出した賠償額になるだろう。その金額は、彼らが負担する訴訟費用と大差なかったのだ。
これは、誠実に謝罪するほかない……。
彼らは謝罪を求めてはいなかったが、何らかの形で私たちの誠意を示さなければ、和解することができないのは明らかだった。そこで、私は、「いきなり訴訟に打って出るのではなく、調停のプロセスに入りませんか?」と彼らに提案。調停の場で、メーカーから誠意を伝えるほかに和解する方法はないと考えたからだ。
彼らは、自分たちの話にじっと耳を傾け、一定の理解を示した私の立場に配慮してくれたのだろう。メーカーに対する強行姿勢は崩さなかったが、私の提案には応じると譲歩してくれた。
しかし、あまりにも謝罪が遅すぎた。
結局、調停は失敗に終わり、訴訟に突入。裁判で私たちの主張が認められはしたが、メーカーを傷つけることが目的だったギフトショップにとっては、それは決して「敗北」ではなかった。なぜなら、メーカーは、長期間に及ぶ訴訟対応に追われるとともに多額の訴訟費用を負担しなければならなかったからだ。