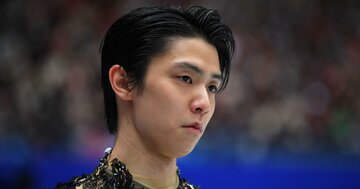逆境でもへこたれない子を育てるためにはどうすればいいのでしょうか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
逆境でもへこたれない子を育てるためにはどうすればいいのでしょうか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
コロナ禍の影響で、親子で過ごす時間が増えると、どうしても子どもの欠点ばかりが見えてきてしまうもの。しかし、あなたの子どもに一番影響を与えているのは、他ならない親自身なのです。『伸びる子どもは○○がすごい』(日経BP社)の著者の榎本博明氏は、今は、自分自身を見つめなおすべきと語ります。
へこたれない子は
何が違うのか
逆境でもへこたれない子は、自分は頑張り抜くことができるといった感覚を身につけているものである。実行できる子は確実にいるが、それがわかっていてもできない子もいる。
たとえば、毎日30分間英語の勉強をすれば英語の授業がよくわかるようになるとわかっていても、それを実行できる子と実行できない子がいる。
その背景には、困難に直面するとすぐに諦める心理がある。粘ることができない。頑張り続けることができない。
私が学生たちと話していて、「もうちょっと頑張ってみたらどう?」みたいなことを言うと、「いいんです。どうせ無理だから」「意志が弱いから無理です」「頑張ったっていいことないし」などと言う者がいる。頑張って困難を乗り越えたという経験がないから、最初から諦めているのだ。
親たちは、子どもを傷つけてはいけないという配慮のもと、厳しさを排除し、挫折を経験しないで済むように手厚く保護し、優しく接する。そうした保護空間で彼らは過ごしてきたために、傷つくこともなく、追い込まれることもないままに、学校段階を駆け抜けてしまう。
「挫折すると傷つくから、自信をつけさせるために本人が少し努力すれば届くような目標を与えて成功体験を積み重ねるように導けばいい」などといわれる。
だが、社会に出ればいくら頑張ってもうまくいかないことだらけであり、挫折の連続である。すでに社会に出る前から、行きたい学校に進学できない、部活でいくら頑張っても試合に勝てないなど、多くの子が挫折を味わうことになる。
各県の優勝校が出場する甲子園でも、最終的に優勝するのは全国でただ1校であり、他のすべての学校の野球部の選手たちは挫折に涙を流しているのである。箱根駅伝で優勝した1校以外のすべての出場校、そして予選敗退したすべての大学の駅伝部の選手も、挫折に涙しているのである。
社会に出てからの職業生活も似たようなもので、挫折の連続が待っている。そこで必要となるのは、挫折からはい上がる力である。
そうしてみると、教育や子育てで大事なのは、過保護にして挫折から守ってやることではなく、挫折を経験させつつ、挫折に負けない力をつけさせることのはずである。頑張って逆境を乗り越える経験をさせることである。「自分もやればできる」と思えるようになる。だから厳しい状況でも頑張り続けることができるのだ。
そのために必要なのは、適度な負荷をかけること、困難に直面させることである。子どもが挫折しないように先回りして障害を取り除こうとすれば、結局は逆境に弱い人間になり、将来子どもが苦労することになる。