日本に来て、差別のようなものを感じなかった
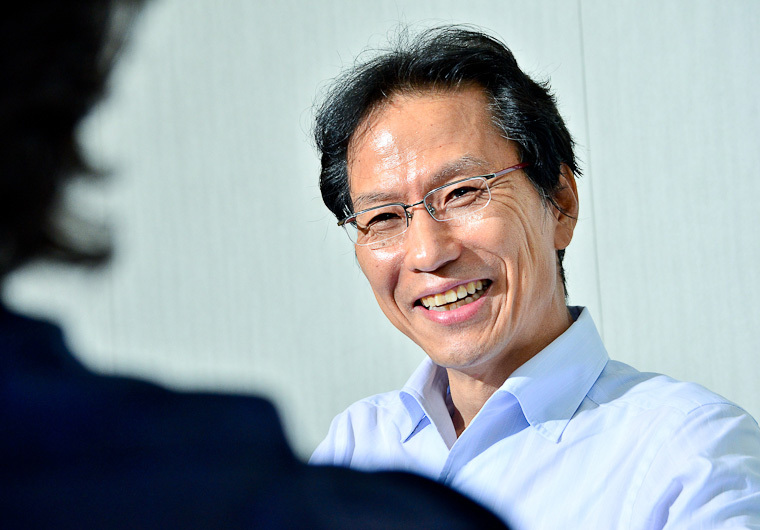
姜 それはすばらしい考え方だと思います。僕は後にドイツに行くんですが、やはり孤立感を味わうんです。ちょっと歯車が狂うと、被害者意識が頭をもたげてしまう。ほんとのちょっとしたことで、そうなるんですね。『悩む力』で取り上げた夏目漱石という人は、おそらくその被害者意識から歯車が狂って、ロンドン留学時代にノイローゼになってしまったんだと思う。
特に韓国から日本に留学する場合は、日本の方が思う以上に、いろいろなことにセンシティブになるでしょう。さらに、日本に来る前の過剰な思いもからんでくる。それで日本に来て、意外と自分が思ったイメージとは違って、親切にされてびっくりして構えてしまったり、やっぱり違和感があって固まってしまったりするんですよね。
でも、そうするとキムさんは、韓国に帰りたいとは思わなかったんですか。そもそも帰るつもりがなかった?
キム 当初はそうではなかったんですが、日本、アメリカ、ドイツなど、いろいろな国に住んで考えが変わっていきました。特に国籍に関する考え方がそうでした。他者と接するとき、それが日本人であれ、アメリカ人であれ、イギリス人であれ、ドイツ人であれ、自分の中での国籍という概念の優先順位がどんどん低くなっていったんです。
自分のパスポートを出すときはもちろん、日韓戦のサッカーを見るときとか、そういうときには、たしかに韓国を応援したくなります(笑)。でも、日常生活の中では、排他的な意味での愛国心というものを持たないよう、冷静に見られるようになっていきました。その点では、学者というのは都合のいい職業でした。
それともうひとつ、僕は日本に来て、差別のようなものを感じなかったんです。その理由は、いい人との巡り会いが大きかったと思っています。運も良かった。例えば僕の妻は日本人ですが、20歳のときに出会ったとき、彼女の両親がいつも僕を家に招いてくれて、さらに家族旅行にも僕を連れて行ってくれたんです。お正月が来る前の、大掃除まで一緒に手伝ったりして。これは、楽しかったし、とてもうれしかった。
こういう形で、これまで自分があまり味わったことのないような家庭の温かさというものを、日本で味わうことができたんですね。こんな経験をすると、国籍の話がどうだとか、そういうものはまったくなくなってしまいました。
もちろん韓国で19年も過ごしていましたから、どんなに客観的に見ようとしても、どうしても不条理に見えるものも当初はありました。それこそ日本に来たばかりの頃は、姜さんが出ていた「朝まで生テレビ」を見て、ものすごく応援していたんですよ(笑)。
ただ、今思えば、その頃の自分にはまだ客観的で落ち着いた歴史観がなかった。危ない自分だったと思います。両者の意見をちゃんと理解しようとせず、対極の理解の前の段階で、片方の肩を持ってしまった。その視線で見ると、すべてが偏った考えになってしまう。とんでもなかったですよね。今は、ずいぶん成長したと思います(笑)。
姜 どちらかのサイド、という思想というのは、やっぱり危険ですよね。何が話されているかではなく、どちらのサイドにいるかだけで、話していることが裁断されてしまう。何かの問題が起きると、国籍というサイドが、人と人との関係を引き裂いてしまうこともある。
実のところキムさんが見ていた20年前の「朝まで生テレビ」では、僕はかなり戦略的に動いていたんです。というのも、まだそのときは、日本がとても強いときだったから。日本のあの頃は、世界のGDPの18%くらいを占めていたんです。世界の6分の1です。わずか1億2000万人の人口で、これだけの数字を一国ではじき出していたんですね。
僕が背負わないといけないと思ったのは、日本は非常に大きな国であるという感覚でした。ところが、一般の個々の日本の人は、それが実感できるような暮らしをしているわけではなかったわけです。国家として自分たちが大きいという感覚もない。だから、日本の国が海外でどう見られているか、どんな影響力を持っているのか、多くの人は、なかなか実感としてわからなかったんです。
そういう時代に、僕はどちらかというと、クリティカルな言動をあえてしようとしました。それをしないといけなかった。世界は、日本に強国としての怖さを感じていましたからね。ところがこの20年で、世界に占める日本のGDP比率はどんどんどんどん下がってきてしまったでしょう。もう当時の半分以下にまで収縮してしまっている。国家が弱ってしまったんです。
キム だから、あの頃とはまったく違う言葉で、今は日本に向かわれるのですね。

![[北欧現地インタビュー:社会保障と制度編]北欧が世界幸福度ランキングでトップにいる理由](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/b/360wm/img_bb7eed7cfe33033b3d63f522ad0ddfb0127125.jpg)

