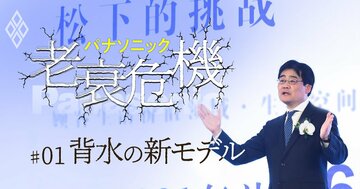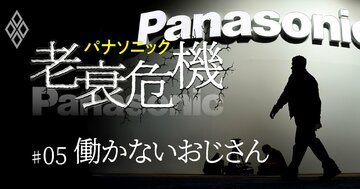グローバルで負け続ける日の丸電機。再び世界で存在感を示すために、肝に銘じるべきことは何か(写真はイメージです) Photo:PIXTA
グローバルで負け続ける日の丸電機。再び世界で存在感を示すために、肝に銘じるべきことは何か(写真はイメージです) Photo:PIXTA
垂直統合的な巨大開発組織が
重荷となった総合電機メーカー
3月2日の日本経済新聞朝刊『経済教室』欄に「規模に合う複数の収益源を 電機業界生き残りの条件」という論考を寄稿した。この寄稿では、日本の規模の大きな電機メーカーは、その規模を支えるために必要な事業が求められるので、開始時点では小規模なビジネスでしかない新規事業だけでは、会社が支えられないという話をした。
前世紀、日本の総合電機メーカーはその規模を生かして、垂直統合的な巨大開発組織を使い、新たな技術と製品を世の中に送り出すことで、成功のパターンをつくり上げてきた。しかし、国際的に分業が進む中で、垂直統合的な製品開発組織や企業の規模がなくても主要なコンポーネントを外部から調達したり、製造を外部に委託したりすることで、会社の規模以上の製品開発が行えるようになった。
そうなると、巨大な総合電機メーカーはスピードの遅さや冗長性といったマイナス面が目立つようになり、むしろ小規模の専業メーカーの方が小回りが利き、変化の速い技術や市場の環境に適合できるようになった。
ダイソン、ボーズといった専業メーカーは、高付加価値な製品を発売し、規模を追求しなくても十分に利益を出せる程度の規模感の企業であり、組織と事業範囲の小ささがメリットになっている。アップルはもはや小規模な企業ではないが、PC、スマホ、タブレットといった特定の事業に集中し、詳細な設計や製造も外部に委託することで、ひとつひとつの製品のつくりこみに集中し、付加価値の高い製品を世の中に送り出してきた。
また、事業領域が広がり過ぎないことから、アップルのブランドや世界観をわかりやすく的確に消費者に伝えることができ、いたずらに規模を追わない事業を行うことができている。